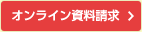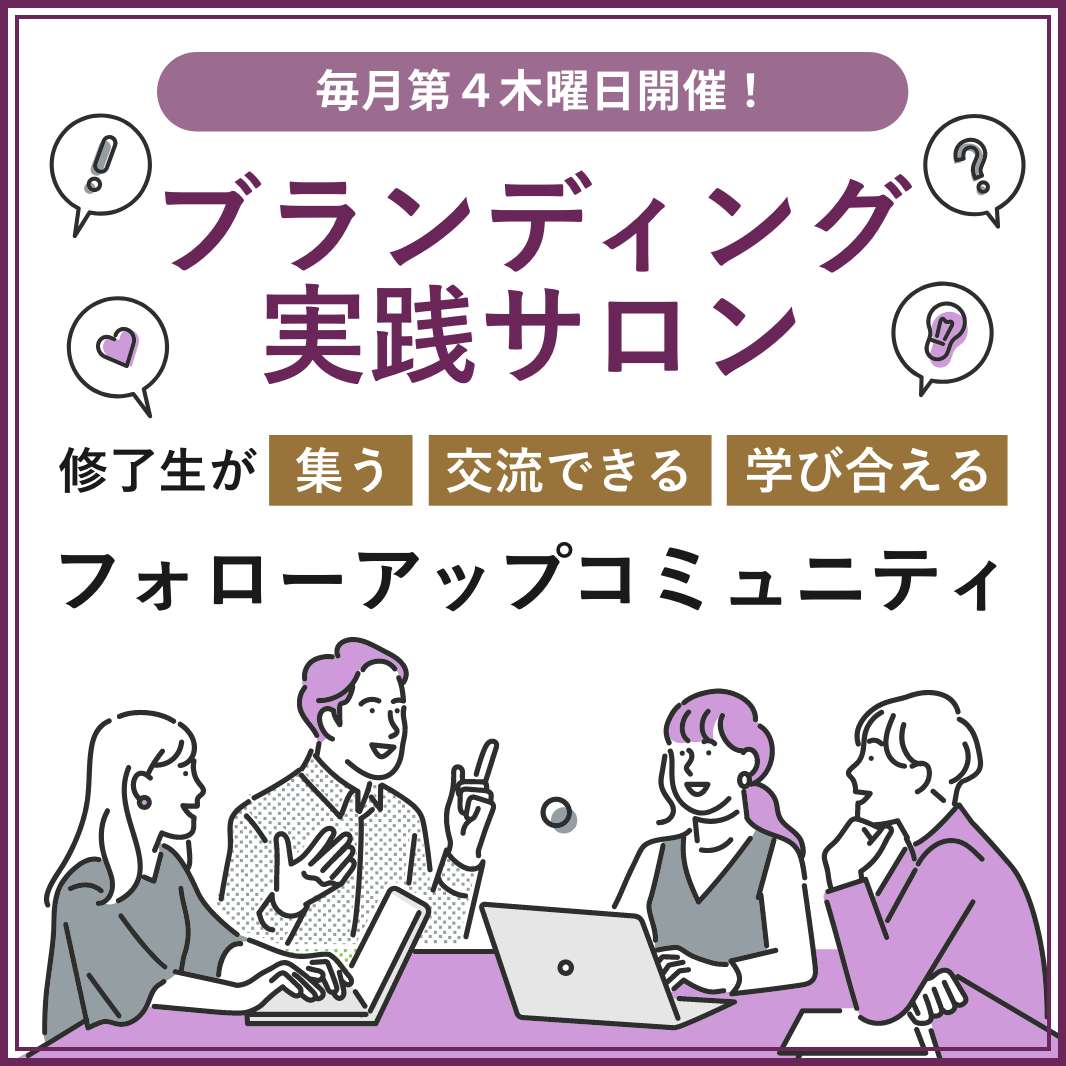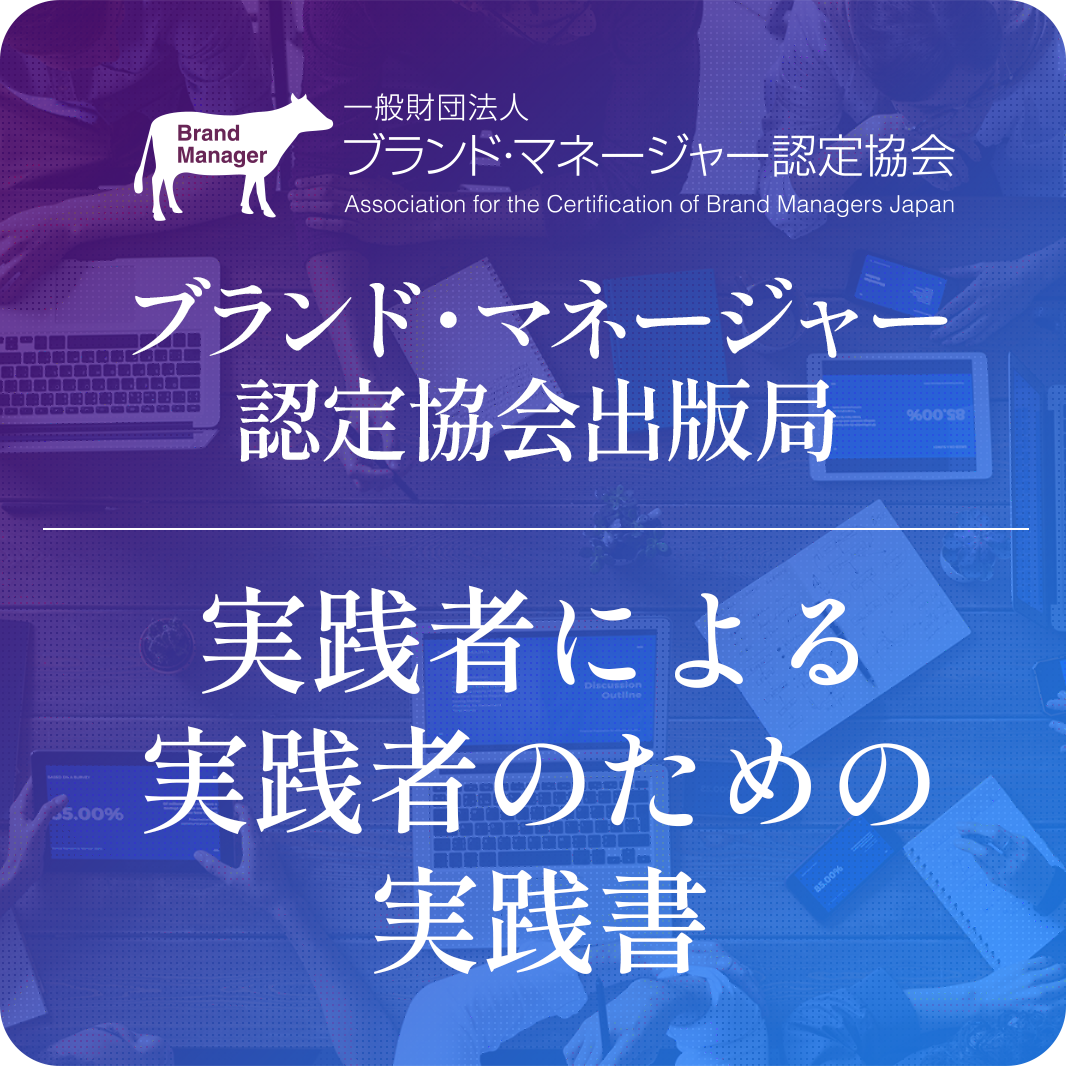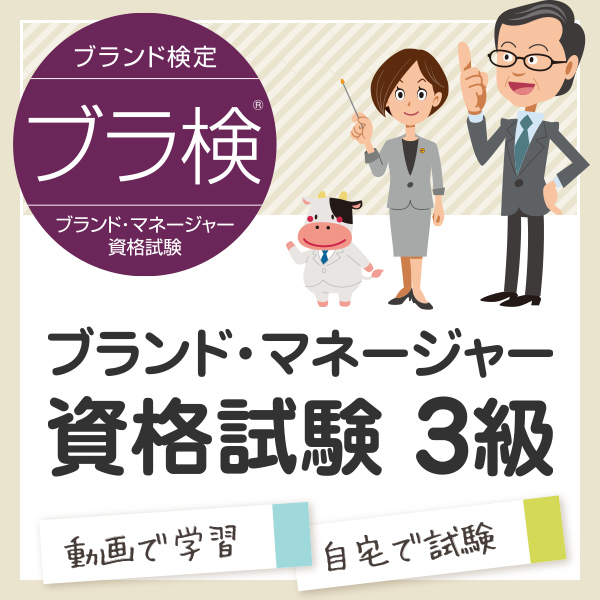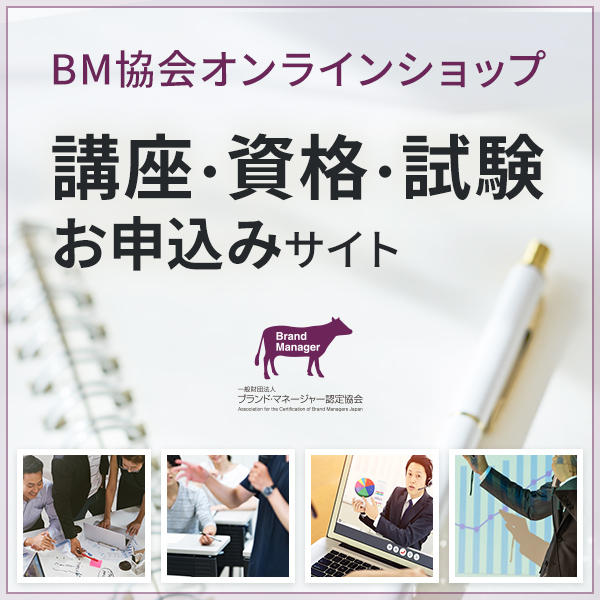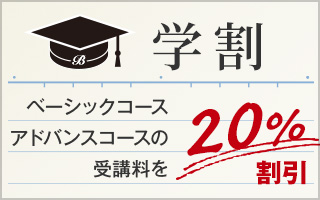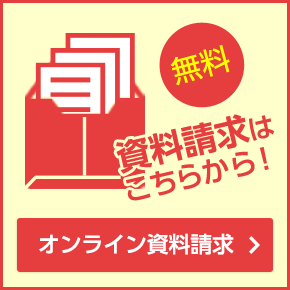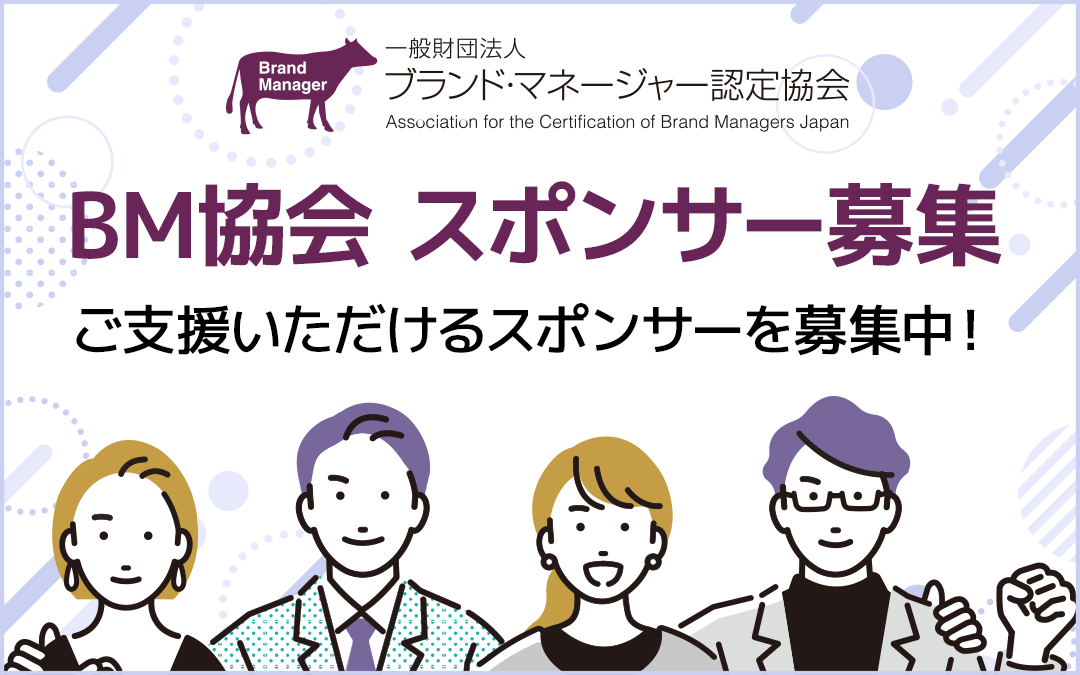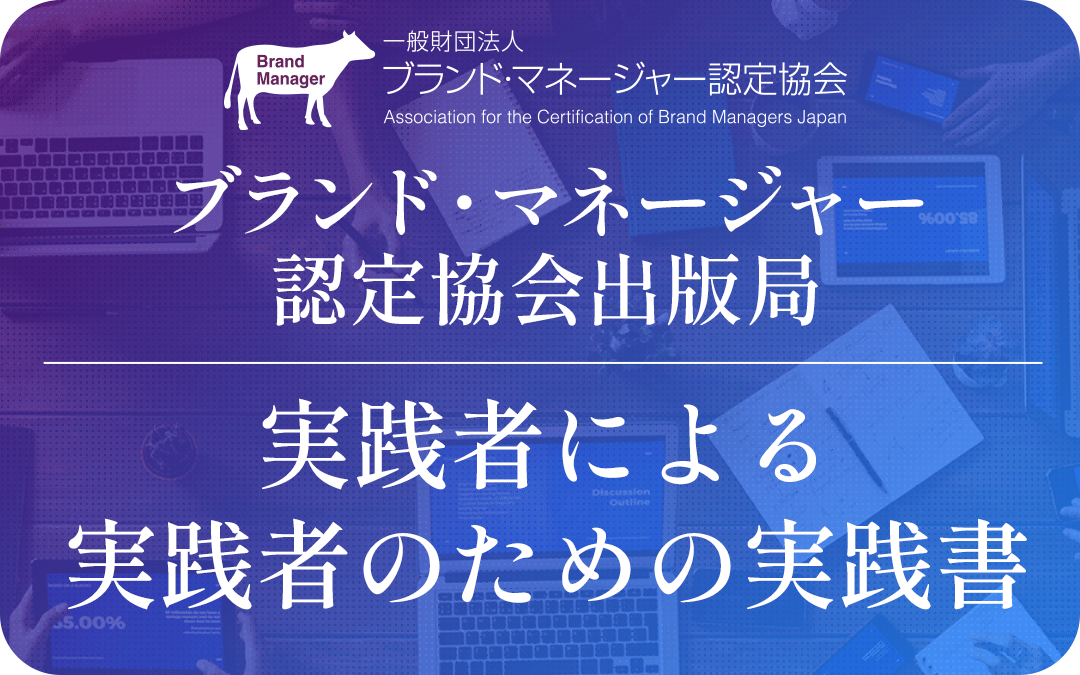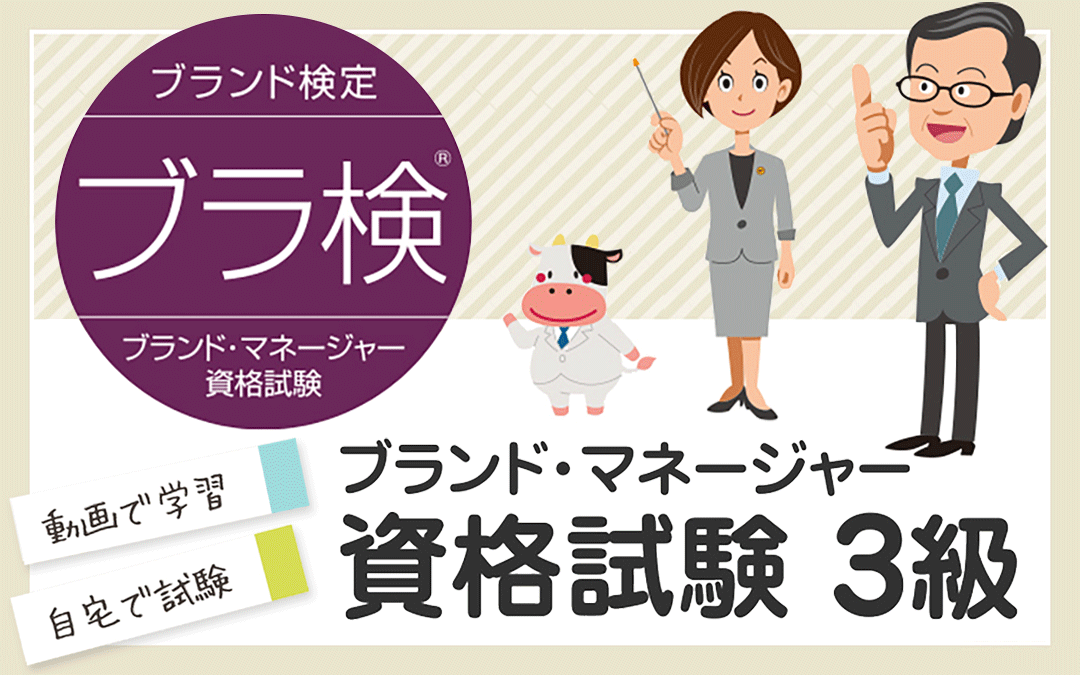ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >長崎秀俊氏
コーポレートブランドとパッケージが商品に与える影響とは?(前編)
長崎秀俊氏
【プロフィール】
目白大学 社会学部教授
ブランド・マネージャー認定協会 顧問
長崎 秀俊氏
大日本印刷、インターブランドジャパン、明治学院大学、昭和女子大学、立教大学の講師を歴任し、2014年に目白大学准教授に就任、2018年教授に昇任。マーケティング、ブランディングに精通し、インターブランドジャパンでのストラテジーディレクターとしての実務経験を活かした実践的な研究教育を得意とする。大学で教鞭をとりながらブランドコンサルタントとして実務も続けている。高尾登山電鉄、銀座中央軒煎餅など実績多数。2001年9月、公益財団法人 吉田秀雄記念事業財団 助成研究 佳作受賞(「ロングセラーブランドのパッケージアイデンティファイア効果の研究」にて店内プル活動としての製品戦略と店外プル活動としての広告戦略を考察)。主な著書に「イラストで理解するブランド戦略入門」(三弥井書店)など。
聞き手:一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 ディレクター 能藤
コーポレートブランドやパッケージ、CSVの研究などで精力的に活動している目白大学社会学部教授の長崎秀俊氏。特にパッケージ研究では、パッケージを認識させる要素として「パッケージアイデンティファイア」という概念を提唱。他に類を見ない独自の研究を行っています。同氏にコーポレートブランドや商品パッケージについて、さらに近年話題の概念であるCSVやSDGsなどとブランドの関係についてお話を伺いました。
「マーケティングに一生関わりたい」と思った
聞き手
コーポレートブランドやパッケージ研究など、ブランドに関わる独自の研究をされています。そこに至るまでに、どのような経緯があったのでしょうか。
長崎
大学のゼミでマーケティングを学び、非常に面白いと思ったことが原点ですね。そのときに「マーケティングに一生関わりたい」と思ったんです。卒業研究ではパッケージに取り組んだのですが、そこでパッケージの力で物が売れるということがわかり、卒業後は大日本印刷に入社していろいろなメーカーの方と一緒にパッケージを作らせていただきました。

聞き手
具体的には、どのようなことを担当されていたのでしょう。
長崎
包装事業部で提案型の営業をしていました。たとえば、クライアントが明治製菓であれば、面白い開け方をするような“容れ物”を提案するんです。ただ、やはり川下の仕事なので、クライアント主導の企画が多いんですね。それで「何もないところから考える」というマーケティングの面白さを味わえる場に行きたいと思うようになりました。
そこで、転職のきっかけ作りとして、大日本印刷で働きながら通えてマーケティングコースがあった法政大学の社会人大学院(夜間)に入り、最新のマーケティングと、日本での研究が始まりだしたブランディングを学びました。
修士課程を卒業し、博士課程に進むタイミングで、外資系のブランディングエージェンシーであるインターブランドジャパンに転職したんです。
聞き手
法政大学の大学院ではどのような研究をされていたのでしょうか?
長崎
運がいいことに、法政大学経営大学院で教えられている小川孔輔先生と、現在中央大学の大学院で教えられている田中洋先生がブランド研究をされていたんです。そこに夜間で2年間通い、修士論文はパッケージとブランドをくっつけた研究を提出しました。博士過程は小川先生の研究室で学びました。博士課程でブランディングのセオリーを研究しながら、同時にインターブランドで実務を経験するという素晴らしい体験ができました。
聞き手
インターブランドは外資系最大手のブランディングエージェンシーですね。ブランディングの手法も、日本企業とは異なるのでしょうか。
長崎
そうですね。インターブランドで、海外と日本ではブランドの認識も使い方も違う、ということを学びました。たとえば、ある日本の機器メーカーに呼ばれ、「ブランドのコンセプトを作りたい」と依頼されたことがあったんです。海外支社から要請されたから、と。その会社には経営理念やミッションはありましたが、内容は「社会のためになる」「社会に貢献する」など抽象的なものだったんです。それは海外支社にとって「どの会社でも言っていることで、ブランド・アイデンティティとは言わない」ということだったんです。海外では、実際に自社しか言えない差別性をもったコンセプトが欲しかったわけです。
聞き手
インターブランドで経験を積まれたあとは、大学で教鞭をとる道に進まれています。どのような背景があったのでしょう。
※掲載の記事は2020年1月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。

無料で会員登録できます