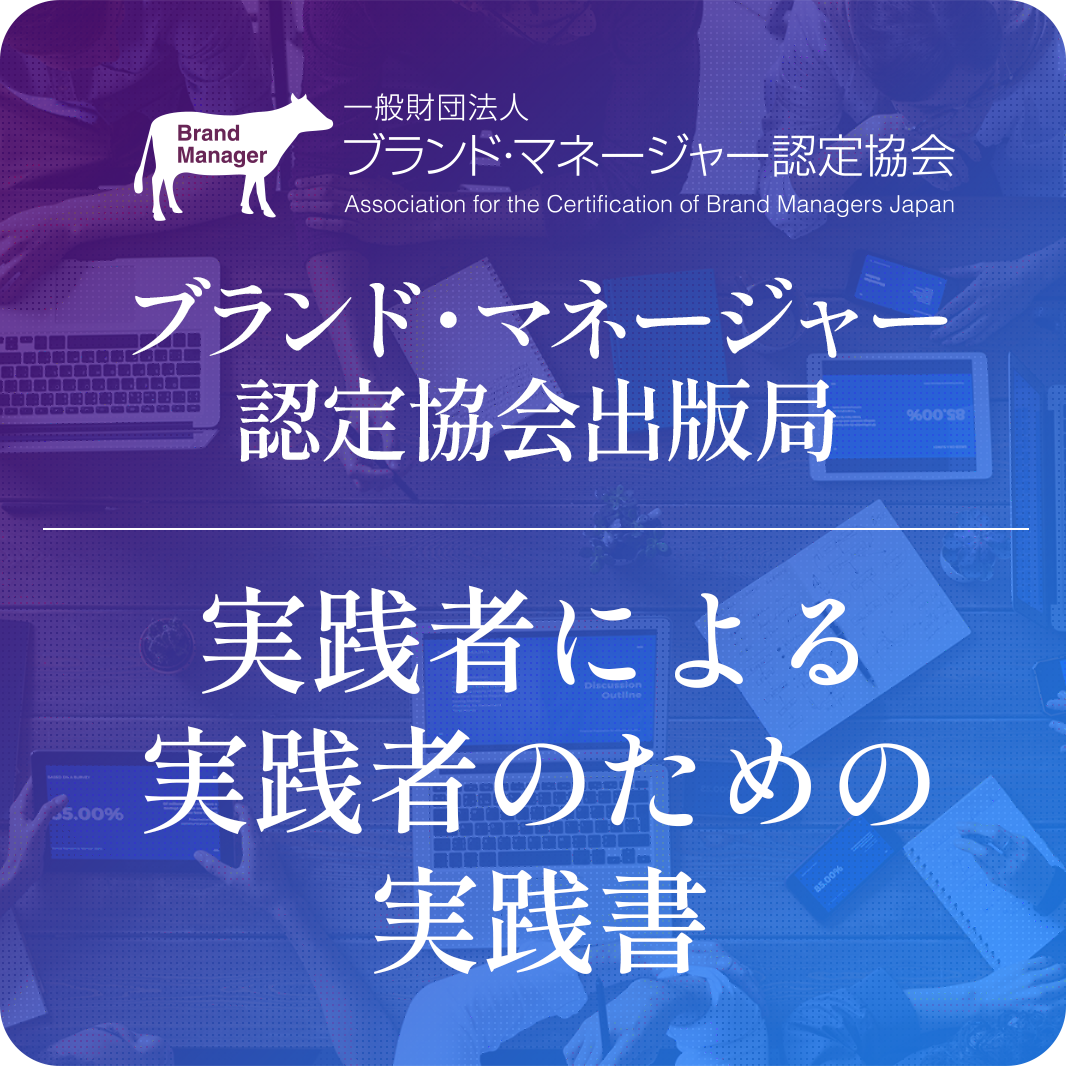ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >浅田 克治氏 Vol.1
本質を見極める思考からつくりだされるクリエイティブワーク – 前編
浅田 克治氏 Vol.1 ASADA DESIGN アートディレクター
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【浅田氏のプロフィール】
ニューヨーク在住の世界的なアートディレクター。
多摩美術大学グラフィックデザイン科卒。
ボツフォードケッチャムインターナショナル東京支社および
ニューヨーク支社を経て1981年独立。
同年8月、ニューヨークに「ASADA DESIGN」を設立。
ティファニー、日本航空、ニューヨーク現代美術館(MoMA)、
ナカミチ、TDK、Japan Image Communications (JIC)、旭硝子、
オリンパス、MRC (ハイエンドオーディオ機器)、 Krell (ハイエンドオーディオ機器)、
Emerson Spa & Resort、Index Holdings,Inc.、 William Lipton Ltd.(アートギャラリー)、
非営利団体フレンズウィズアウトボーダー、ピクトリコ(三菱製紙)、
千山窯(砥部焼)等、多数の商品のアートディレクションから
デザインコンサルタントを勤める。
人々の考え方ががらりと変わる時代
聞き手
浅田さんはずいぶん前からアメリカで仕事されていますが、渡米されたのはいつごろですか。
浅田
ニューヨークに渡って40年近くになります。
渡米したころはアメリカのアドバタイジングはものすごい力を持っていました。
アメリカの国自体が力を持っていて、どのクライアントも非常に勢いがあり、製品とエージェンシーの考えがマッチした時代でした。
僕が渡米したのは1973年ごろでしたので、その勢いがちょっと落ち着いたころですね。
マジソンアベニューというところにケッチャムというエージェンシーがあって、そこで丸10年間アートディレクターをやっていました。
聞き手
独立されたきっかけは?
浅田
ずっといろいろなことをやっているうちに、僕自身は一体何者かと思い始めてきたんです。
ニューヨークのエージェンシーで仕事をしているからといって、果たしてクリエイターとしての本当の力があるかどうかなんて分からないじゃないですか。
エージェンシーのアカウントマネジャーが仕事を取ってきて、クリエイティブに仕事が下りてきて、プレゼンテーションして、OKが取れて、年間の予算をもらって、3~4年回して、またプレゼンする。
でもそれは、会社という組織の中の一アートディレクターであって・・・、と思いながらも10年間その会社にお世話になって きっちり仕事をこなしていました。
で、やはり自分で試したくなって、もしこれが駄目ならまた考えればいいと思って会社を退職し、浅田デザインを開設したんです。
聞き手
独立されたのは何年前ですか?
浅田
30年前です。会社を飛び出て、ティファニー、日本航空、ニューヨーク現代美術館などさまざまな仕事をこなしました。
でも、このままニューヨークだけで活動していると、日本の若いアートディレクターやクリエーティブディレクターたちと接触がありません。
だから、僕が日本に帰ってきて、僕が経験してきたことを伝える機会をつくっていくべきだと感じて、それで年に3、4回日本に帰ってくるようになったんです。
聞き手
今の時代をどう捉えていますか。
浅田
今の時代は、環境というか、人のものの考え方が変わっていくのがよく分かります。
海の向こうから見ると特によく分かる。
その「人の考え」と今の「時代」がマッチしないと、もののエネルギーというのは出てこないんです。今まであったものの積み重ねでは前に行かない。
それはもはや過去のものです。いい悪いは別にして、今の人たちが何を考えて何を求めているか、そこからものが生まれてこないと価値はありません。
だから、企業も今すごく悩んでいると思います。
「ものができました、どういう風に売ればいいですか」ではなくて、「何を作ればいいのか」というところから考えなければなりませんから。
今までの経験則の積み重ねでものが動く時代ではなくなってしまったんです。
特に東日本大震災のような大きな災害があると人のものの考え方が大きく変わります。
あれだけの大災害が起こると、企業、エージェンシー、クリエイター、デザイナーというレベルではなく、まったく違うものの考え方が同時にこないと駄目。
あれだけの大きな震災を体験すると、人のものの考え方というのは、生きるということはどういうことなんだろうと、そこから始まってくる。
考えもしないことが起こると、環境が変わるし、ものの考え方がからりと変わる。
それが今、みんなが共有しなければならないことだと思います。
聞き手
全ての思考の前提としてですね。
浅田
そう、前提として何が起こるか分からない時代に 突入してしまった。それは天災もあり、人災もあります。
聞き手
ヨーロッパの金融危機もそうですね。私たちはまさに考えもしなかった時代に入っています。

デザイン力とはものを省く力
聞き手
今はときどき日本に帰ってきて、今後を担う人たちをシェアしたりされているのですか?
浅田
イヤ、まだそこまでの話はできていませんが、いろいろな人とお会いさせてもらいます。例えば、今回の帰国では、ある焼き物(食器や器など)のメーカーの社長さんとコピーライターの方とお会いするのですが、3年前に、ある人から「焼き物をニューヨークに紹介したい」という打診がありまして、そのときはソーホーのギャラリーで焼き物の展示会を開けないかということで、その話をニューヨークに持ち帰ったのです。
で、3カ月後に再び東京でお会いしたときに、テーブルの上に焼き物をどんなに美しくディスプレーしても何も伝わらないと思うと伝えました。
焼き物というのは、生活の中にあって使って初めてその価値が出るものだと思う。
そこで、私の知っているレストランと交渉して食器を全部この焼き物に替えて、1カ月間営業してもらい、ニューヨークのお客さまに体感してもらったらどうかという提案したのです。
「そういうことができるのですか」と聞くので、いや、もう話はつけてきましたと。
「社長がもしそれをやろうと決断するなら、小皿、大皿、一輪挿しに至るまで全て焼き物でそろえなければなりません。
1個でも違うものが入っていたら、この企画は意味がない。
ワイングラスも作ってもらえますか」。
私がそう言うと、「やります」と。
そのプロモーションが1カ月どころかもう1年半も続いています。
ここまでくると、世界を周っている日本人の方がたまたまそのレストランに入ってびっくりされるわけです。
「この店はなぜ全てがこの焼き物なのか」ってね。
「ああ、これなつかしい。子どものころ使っていたお茶碗だ」とか、そういう話まで出てくる。
このプロモーションの目的は、焼き物を知らしめるということも大事なのですが、焼き物の町で焼き物に関わっている人たちの活性化が一番重要で、立ち位置は常にそこに戻っていくことが一番の大事だと僕は思っているんです。
聞き手
なるほど。ニューヨークで何かするとか上辺ではなく、ものそのものが持つ本質を感じてもらうということですね。
浅田
そうなんです。この町の人たちの生活の中に「ニューヨークがつながっている」というものの考え方が醸成されることが一番の目的だと思うんです。
聞き手
その社長さんは納得されましたか。
浅田
ええ、納得されました。始めたときには分からなかったかもしれませんが、1年半続けたことで理解されたようです。
聞き手
浅田さんが企業の人たちに伝えたいことは何ですか。
浅田
今年(2011年)の1月に、金沢の中小企業の社長さんの集まりで、デザイン力がいかに大切かという話をしてくれないかという打診がありました。
そこで、さきほども話しましたが、今の時代の人たちが何を望んでいるかを企業の人たちも考えて創らないと駄目だという話をさせていただきました。
形だけではない、クオリティだけでもない。
本質的な価値を持つ何かを想像すること。
そういう意味で言えば、スティーブ・ジョブズがアップルでやったことはすごいと思います。
あのレベルまでいくともう形とかではなくて、違う次元のものですね。
聞き手
その金沢の講演で一番伝えたかったことは何だったのですか。
浅田
1時間半くらいの講演でしたが、一番言いたかったことは、ものを使う人たち、ものを選ぶ人たちがものの本質をお互いに分かり合うということ。
その価値をお互いに共有しなければ駄目だということ。
ですから、作る方もデザインばかりに捉われるのではなく、例えば有名な建築家にステーショナリーのデザインをしてもらったとかそういうものではない、もっとその奥にある本物、本質の方がデザインよりも大切だということです。
聞き手
それはシンプルに言えば、一言で終わってしまいますが、それを1時間半の中でどうやって伝えたのですか。
浅田
ものの本質とは毎日の生活の中にあるものです。
僕はデザイン力とはものを省く力だと思っているんです。
つまり、削るのがデザインだと。足していくのがデザインだと考える人は多い。
グラフィックでいえば、きれいな線や模様でデコレートされているのがデザインされたものだと。
僕は逆に何もなくて、一番言いたいものが一つの言葉だけで表現されていると、もっとその言葉が強烈に伝わるのではないかと思う。
聞き手
そぎ落として残ったものが本物であり、本質であるということですね。
浅田
それは形だけでなく素材だとか、例えば紙自体にも目が行き届く。
触ったときの手触りからも伝わる。ですから、グラフィックデザイナーも形だけでなく、もっと深い部分からデザインしてほしい。
そういう話をいろいろな形でさせていただきました。

自分を取り戻す時間と空間
聞き手
余分なものを削ぎ落として、残ったシンプルなものこそが本質であり、最も訴える力があるということですね。浅田さんの中でそれを確信したのはいつごろですか。
浅田
確信は未だにありませんが、ものの見方には父が影響しているかも知れませんね。
僕がまだ小さな子どものころ、父はすでに仕事をリタイヤしており、庭づくりが趣味でした。
草木だけでなく珍しい石とかも父の庭を構成する重要な要素なわけです。
ときどき、父が幼い私に聞くんですね。
「この石の顔はどこだと思う?」。
すると、子どもの私は一生懸命、その石の「顔」を探すわけです。
それがくせになって、1本の木の顔、1本の木の背中を発見しようとする。
そのころのものとの接し方が、今のものの見方につながっているのではないかと思います。
聞き手
それを仕事の中で生かすうちにどんどん確信をもっていったのですね。
浅田
いい悪いかは別にして、僕自身の感性は僕のこれまでの人生の中で培われたものですから。
多摩美術大学を卒業して、29歳でニューヨークに渡ったのは、30歳を過ぎてまた一からやるのはしんどいなと思いまして、30歳までに行きたいと思ったからです。
40代のときには、学校も会社も関係ない一個人の「浅田克治」では何もできないと思って死に物狂いで働きましたね。
聞き手
それは自分探しのようなものですか。
浅田
そうですね。自分とは一体何かということに不安にもっていた。出身大学や勤めている会社が、個人を半分以上形成している。ところが、それを全部そぎ落としてしまうと一人の素の自身しか残らない。
聞き手
なるほど、それもさっきと同じ本質を見極める思考と同じなんですね(笑)。
浅田
同じ思考なんです(笑)。結局、僕は浅田克治でしかないんですよ。
聞き手
よく自分探しのために旅に出るとかありますけど、浅田さんは自分を確認するために一生懸命仕事をされたわけですよね。それはなぜですか。
浅田
僕はデザイナーでありアートディテクターですが、人生はそれだけではないと思っています。
でも、そのときは仕事を一生懸命やることによってそれが見えてくると思ったんです。
それと同時に、週末はずっと田舎にいました。
35歳くらいのときから、月曜から金曜まではマンハッタンで仕事して、金曜の夜から月曜の朝まではマンハッタンから車で2時間半の田舎で過ごしてきました。
聞き手
そこで何をするのですか。
浅田
何もしません。景色を眺めたり、釣りをしたり、ハイキングに行ったり。
聞き手
それは意図的だったのですか。
浅田
アメリカのビジネス社会の中にいると自分が磨り減っていくんです。
常に戦い続けなくてはならないし、自分を主張し続けなければならない。
そして、「私はこう思う」という自分自身を持っていなければ生き残っていけない世界です。
マンハッタンの中にいると一人で世界を相手にしている気になってしまいますが、それはとんでもないことで、本当の自分を見失ってしまいそうになる。
大きなうねりの中で流されてしまいそうになるんですね。
だから、自分にフォーカスするというか、自分を取り戻すための時間と場所が必要だったんです。
聞き手
それは非常に興味深い話ですね。
※掲載の記事は2015年7月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。