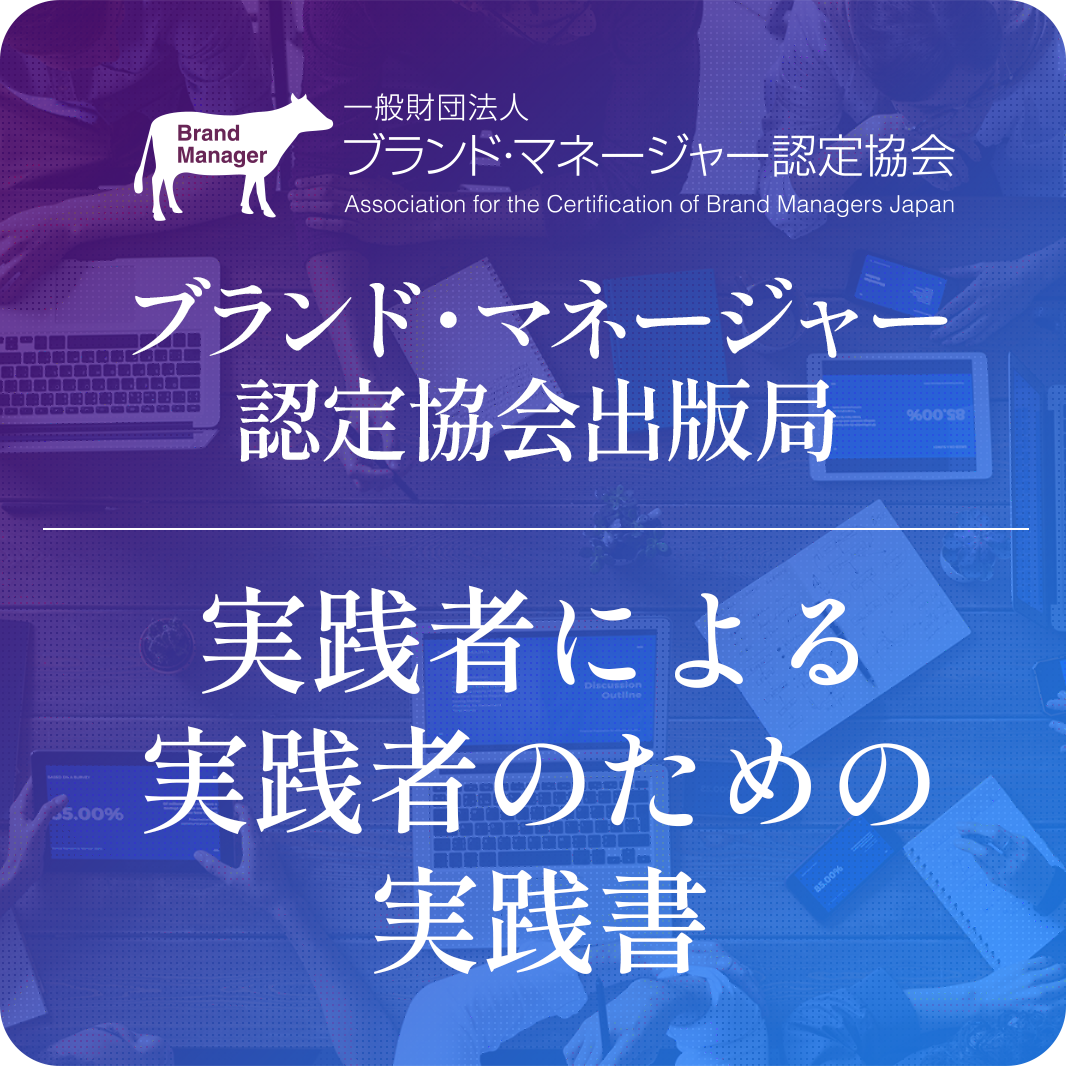ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >大石 賢司氏 Vol.1
価値観が全く違う新規ブランドのイメージづくりに大切なものとは – 前編
大石 賢司氏 Vol.1 SPRINGS C.S.F.、C.S.F.WOOD 代表取締役
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【大石氏のプロフィール】
SPRINGS C.S.F.、C.S.F.WOOD 代表取締役。
クリエイティブ・アートディレクター。
資生堂ブランドのひとつであるイプサを、
15年間にわたりアートディレクターとして、
イメージ作りから店頭のトータルツールの開発にまで携わり、
イプサのブランドイメージを確立。
ファーム(農場)という組織づくり
聞き手
大石さんが独立されたのはおいくつのときですか。
大石
26歳のときですね。
聞き手
起業された理由は?
大石
特に大志があったわけではないんです。大学卒業後、就職して企業のデザインチームに入って3年経験しまして、その後、大学の先生のデザイン事務所に1年ほど出入りして、次は代理店に就職しようかなと思っていたんです。ただ、当時はあまり就職環境がよくなくて、1年間就職浪人をしながら友人の仕事を手伝ったりていました。そのうち、その友人から一緒に会社をやらないかと誘われて、その流れの中で独立した格好になったわけです。
聞き手
仕事がなくて困ったことはなかったんですか。
大石
困ることはなかったですね。
聞き手
じゃあ、どんどん仕事が入ってきた?
大石
どんどんというか、当時はコンペが多かったんですけど、割と採用していただいていましたね。
聞き手
会社を3つ設立されていますよね。これはどういう経緯で?
大石
一つは「クリーク・サイド・ファーム」という友人との共同経営のような会社です。デザイナーってけっこう独立して辞めていくんですが、辞めていくときに自分のクライアントを持って出ていくんですね。そうすると、今まで一緒に仕事してきた関係が断ち切れてしまう。それってもったいないなって思ったんです。もとの会社との関係を大事にしながら、それと自分がやらなければいけないこととをうまく一体化するような事務所の作り方はないかと考えていたんです。例えば、ファーム(農場)を経営管理する。その農場には、牛を飼う人、ミルクをつくる人、チーズをつくる人、畑で農作物をつくる人、森を開墾する人などいろいろな技術を持った人が一緒に働いている。そういうデザインのいろいろな才能を持つ人を一つのファームのように育て、そこから育った人にその道の専門家として活躍してもらう。そんな個人と組織が一体化したようなデザイン事務所ができないかと。それで、クリーク・サイド・ファームという会社を設立したんです。そういう構想のもとに、クリーク・サイド・ファームに所属し、次にクリーク・サイド・ファーム・略してC・S・F「ウッド」という事務所をつくりました。ウッドはファームの中の森(Wood)という意味づけなんです。そして今度は、その森の中に源泉をつくらなくちゃいけないと思って、「スプリングス」・C・S・Fという事務所をつくったんです。デザインでもマーケティング寄りの製品自体を生み出す会社とそれを表現する会社、そしてもともとあった若い人を育てる会社とが一体化した組織を作れないかと。でも、なかなかうまくいかないですね(笑)。
聞き手
経営はどういう状態なのですか。
大石
今、クリーク・サイド・ファームは休眠状態ですが、ウッドとスプリングスは私自身が経営しています。今、一緒に働いている人たちとも、それぞれが独立して事務所を持っても、C・S・Fの名前をつけてつかず離れずで関係していければいいねと話し合っています。
聞き手
緩やかな関係ですよね。私もこのブランド・マネージャー認定協会はそういうイメージを持っていたのですごく共感します。そういう関係って、今の時代だからこそうまくいくのかもしれませんね。

資生堂「イプサ」が飛躍の分岐点
聞き手
これまで化粧品関係の仕事を多く手掛けられていますね。
大石
実はウッドという会社を立ち上げる1年前、クリーク・サイド・ファームの仕事の中で資生堂に関係するメンバーと出会う機会があったんです。資生堂が「イプサ」という新しいブランドを立ち上げる時機です。「イプサ」は社外にはまだ極秘のブランドで、発表する前のコアな部分を形づくろうという段階でした。そこでいろいろな人に声を掛けてアートディレクターを探していたようです。それにちょうど運良く出会うことができた。その当時、私はまったく無名なデザイナーでしたが、なぜかテストのような形で、いろいろとチャレンジさせていただく機会をいただきました。私はちょうどその前に休業していた時期がありまして、自分のデザインの方向性に色々と疑問を抱いていた時期です。カナダやインドに行ったりしていたんです。西欧からきたブランドの概念や価値観とか、デザインとは何かとか、いろいろ突き詰めて考えた時期でした。そんな中で自分たちの体内に流れているのはどうしてもアジアだという結論に至ったわけです。アジアの中に自分たちのアイデンティティーがあって、そのアイデンティティーをもう一度掘り起こすべきじゃないかと。もちろん、西欧的なデザインを否定するわけではないのですが、もう一度見直してミックスし新しい自分のデザインというものを見い出したいと。資生堂のクリエイティブディレクターとそのような話をよくしました。今考えると、私がイプサのアートディレクターにその後選ばれたのは、仕事の実力ではなく、そんな考え方や姿勢にあったような気がします。
聞き手
その休業中に世界を見て、アジアの中の日本を客観視されたわけですね。ちょうどその当時は、外資の化粧品ブランドが日本に上陸してきたころですね。だから、余計に大石さんの考えと資生堂のCDの考えが一致したのでしょうね。じゃあ、「イプサ」ブランドがきっかけで化粧品業界の仕事が続くわけですね。
大石
そうですね。「イプサ」は12年ほど担当させていただきました。12年の間、「イプサ」が成長していくのと並行して自分も成長させていただきましたね。30代から40代にかけてはほかの仕事をやる余裕はなくて、それだけに集中していました。
聞き手
1987年に「イプサ」のアートディレクターに就任していますが、ブランドが立ち上がったのも同じころですか。
大石
ブランド自体は就任する1年前に立ち上がっていました。
聞き手
そのとき、資生堂としての「イプサ」ブランドの位置付けはどういうものだったのでしょうか。
大石
百貨店の化粧品売場の中央に資生堂のブランドエリアがあります。その中にハイステージなものからナチュラルなものまでいろいろなブランドがある。そこでもう一つ、そこの枠にはまらないブランドとして新しい概念をつくりたいと考えていたようです。化粧品のニーズはお客さまそれぞれで違う。そうであるならば、その違うものをきちんと測定し、お客さまと会話する中で化粧法を見つけていくようなブランドをつくろうということが根本だったようです。
聞き手
お客さまとコミュニケーションを図りながらカウンセリングをし、化粧法を構築していくというやり方ですね。
大石
そうです。化粧品にレシピという考え方を取り入れたユニークなブランドでした。

自由にできることのこわさと不安
聞き手
その競合対策はどのように表現していったのですか。
大石
私自身がアイデアを再考したときに、西欧に対して「無国籍」という概念が出てきた。メイド・イン・ジャパンであることは確かだけれども、西欧のエッセンスも取り入れながら、アジアの生命力を表現したかった。アジアの感覚って、森の中に生命力を見いだしたりするじゃないですか。例えば、木の中に水が存在し、その水を循環させて全体を潤している。今は化粧品としては当たり前のように言われていることですが、その当時はそういう考え方を化粧品の中に持ち込む、あるいはそういう感覚で化粧品の広告やコミュニケーションをつくっていくことはほとんど考えられていなかった。まずそこから始めてみようと。化粧品とは最後につくられた成果であって、考え方の中でお客さまと一緒になって、自然観とか、循環するとか、共存するとかという概念を共有するブランドをつくっていきたい。そういう共通認識がアートチームの中で形成されていったわけです。
聞き手
チームでそれを表現するに当たって、難しい局面もあったと思いますが、大石さんから提案したものが場合によっては反対されるとか、その意識合わせがずれることはありませんでしたか。
大石
いえ、なかったですね。立ち上がって5年間ぐらいは本当に好きにやらせていただきました。「あなたのやりたいようにやってください。5年間は変えませんから」と。
聞き手
そう言われると、逆にこわくありませんでしたか(笑)。
大石
ものすごくこわかったです(笑)。誰かが否定してくれたり、時間がないとか言ってくれるとほっとするじゃないですか。予算がないからここで止めてくれとかと言ってもらう方がどこか安心できるものですよね。でも、ある程度自由にやらせてもらいながら、障害になることはすべてアートチームがカバーしてくれました。
聞き手
そうは言っても、年間の販売目標はあったわけですよね。それに対して、大石さんもコミットされていたのですか。
大石
ええ。
聞き手
ということは、目標はクリアしていたわけですね。
大石
そうです。
聞き手
では、その目標を達成するためにプレッシャーはありませんでしたか。
大石
ものすごく不安で(笑)、自分が表現したことが本当に正しいのだろうかとか、「イプサ」というブランドにとって本当にこの道でいいのだろうかとか、四六時中、悩んでいました。でも、クリエイティブディレクターは、「あなたは自信を持ってやっていいんです。自分の中から湧き出してくるものを素直に出してください」と言ってくれまして、その言葉にとても救われました。自分を信じていいんだと。
聞き手
それだけ大石さんの才能が輝いていたということでしょうね。しかし、資生堂の度量の大きさを感じますね。
※掲載の記事は2015年4月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。