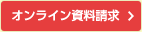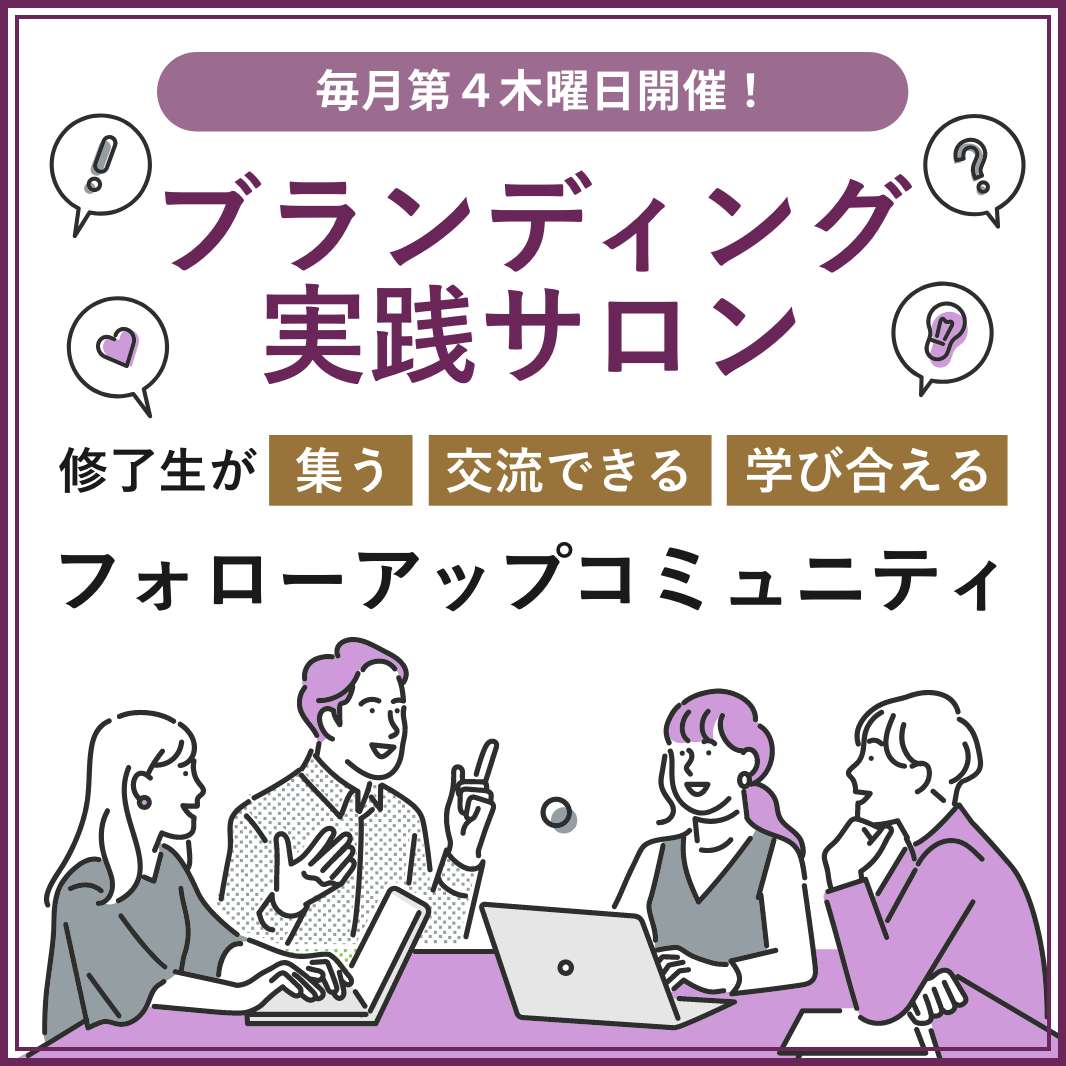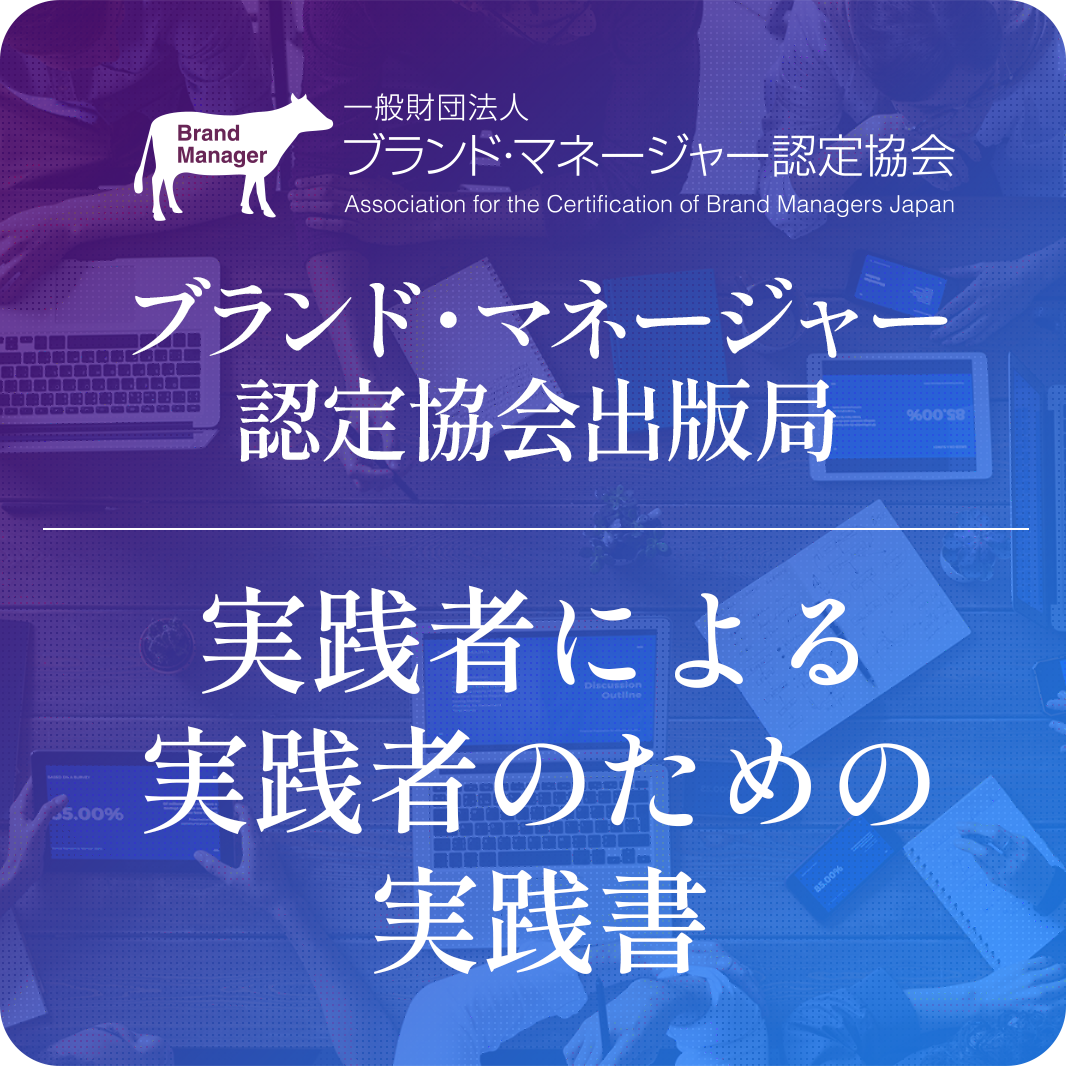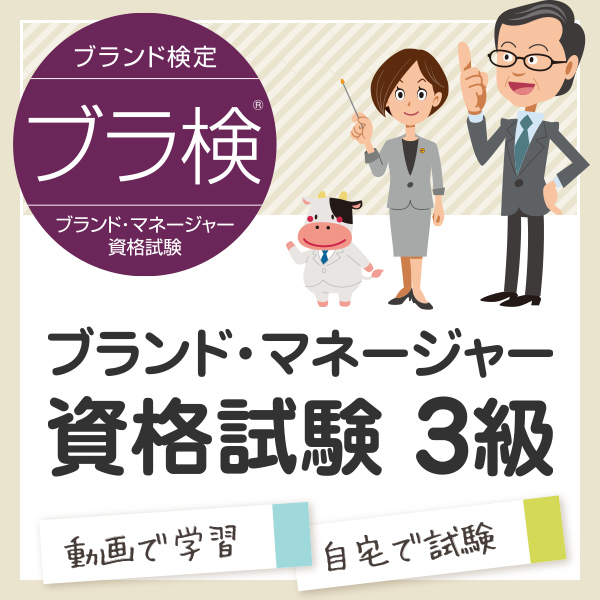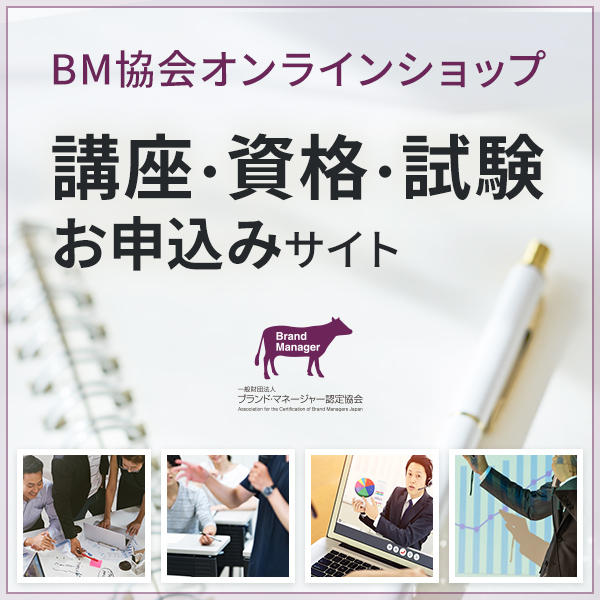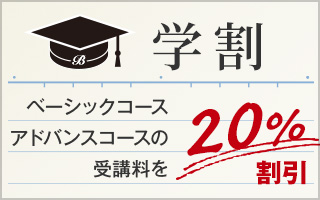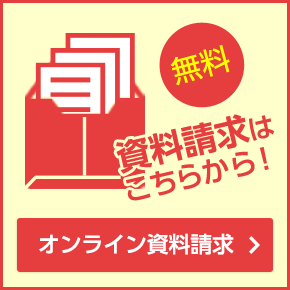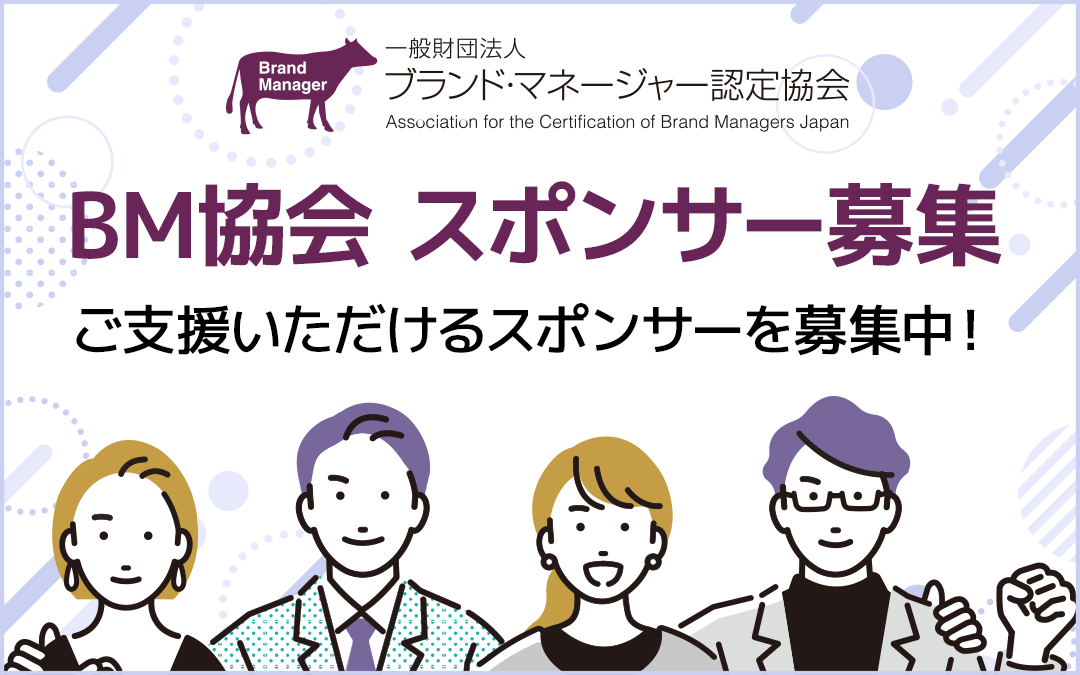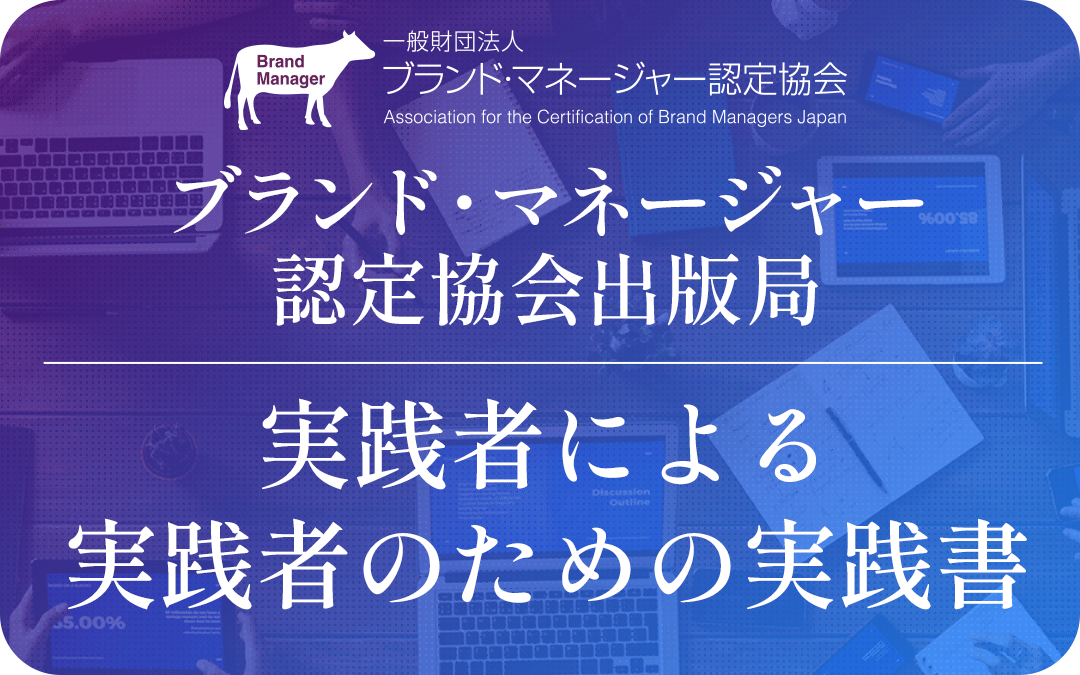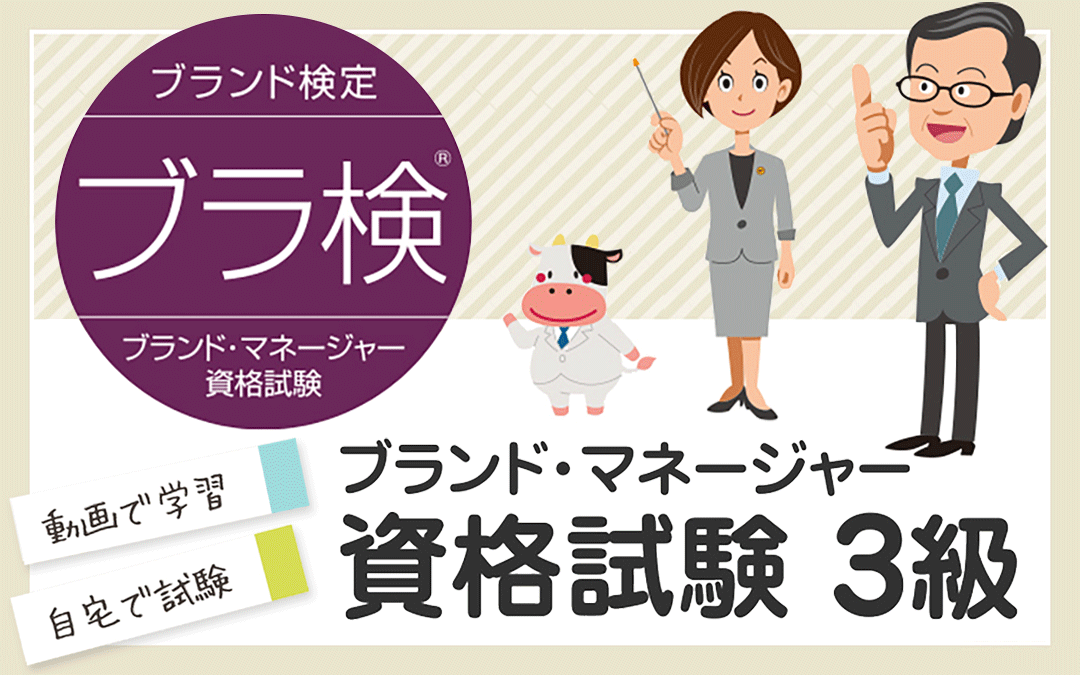ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー > 日本理化学工業株式会社 Vol.1
消費者を幸せにするブランドづくりで働く社員も幸せに – 前編
日本理化学工業株式会社 Vol.1 同社代表取締役社長 大山 隆久氏
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【日本理化学工業株式会社のプロフィール】
日本理化学工業株式会社は昭和12(1937)年創業のチョーク製造会社。
粉の出にくい「ダストレスチョーク」でチョークのトップシェアを誇る一方、昭和35(1960)年から知的障害者の雇用を開始。現在、社員83名のうち知的障害者が61名(重度28名)と、障害者雇用率は70%に達する。
平成17(2005)年には企業フィランソロピー大賞特別賞〔社会共生賞〕を受賞。
平成21(2009)年10月には鳩山由紀夫首相が川崎工場に視察に訪れた。
テレビや書籍などでも数多く紹介される。
大山泰弘会長は障害者雇用に取り組む中小企業の経営者にとってカリスマ的存在。
平成20(2008)年には長男の大山隆久さんが後継者として社長に就任した。
消費者に「届く」商品作りでブランドを確立
聞き手
日本理化学工業株式会社は昭和12年創業とのことですが?
大山
それ以前から卸の仕事をしていた祖父の会社の近くに大学病院があり、そちらの医師から「アメリカに体に害のないチョークというのがあるから、それを輸入してくれないか?」と依頼を受けたことをきっかけにチョーク製造を始めました。当時、学校の先生に肺の病気が多く、体に安全なものが求められていたのです。その頃は柔らかく粉が飛散しやすい石膏チョークが主流で、そのため教師に肺の病気が多いのではないかと推測されていたようです。因果関係は現在も証明されておらず、今でも石膏チョークの使用は継続されているのですが、当時のそうした要望から弊社のチョーク開発がスタートしたのは間違いありません。製品を入手した祖父が成分や製法を細かく研究、国内で製造可能なことを確認し、昭和12年からチョーク作りをスタートさせたというのが創業の経緯です。
聞き手
アメリカで既に販売されていた商品を基に製造開発されたのですか?
大山
ベースがないところからの商品開発は難しいですから、既成品を輸入しながらいろいろな情報も仕入れて開発したようです。弊社は80年近く前に日本で初めて飛散の少ない炭酸カルシウム製チョークを製造しましたが、それでも「チョークメーカー」としては新参で、国内最後発といっても過言ではないほどです。創業80年を迎えようとしている弊社がいまだ新参者であるほど、チョークという商品は古い歴史を持った商品なのです。そのような古いマーケットのなかで、いかに他メーカーから抜きん出るかというところが重要になりました。

聞き手
そのような古い市場に参入しながら、他社との差別化に成功した理由は?
大山
現在、弊社の主力商品でもある「ダストレスチョーク」の開発が鍵となります。炭酸カルシウム製のチョークなどというものは日本国内に存在していませんでしたから、まったくゼロからのスタートでした。しかし現在のチョーク市場で半分近いシェアを獲得するまでに至ったのは、粉末が飛散しづらく、摩耗度が低いため長く使えるという商品のメリットが、消費者のニーズにマッチしていたという事実によるところが大きかったのだと思います。もちろん、「ダストレスチョーク」として商標権を取得したことも大きな意味を持っていますが、消費者の心に響く商品をお届けできたというところがやはり勝機を掴むことができた最大のポイントだと思います。
聞き手
「ダストレスチョーク」を広めるために、どのような戦略をとられましたか?
大山
戦略というほどのものではありませんが、ひとつには「体に安全なチョーク」が求められているという消費ニーズを汲み取り、それに応えたことですね。これにより一歩一歩着実に販路を拡大することができました。そして、さらに大きな転機となったのは、昭和26年と28年に当時の文部省の斡旋品として国のお墨付きをいただいたことです。これをきっかけとして、全国の学校にどんどん普及していったのです。とはいえ、チョークというのもどんどん小さくなっていくマーケットです。特に30年くらい前から少子化が始まり学校利用も縮小の一途を辿っていますし、ホワイトボードや電子ボードの誕生や、プロジェクターの利用により、チョークを使う場面は減ってきています。しかし、会社ですから、とにかく継続していかなければなりません。そのなかで時代に合わせて、チョークを花壇の肥料としてリサイクル利用することを提案したり、さらには新商品を開発したりと、一生懸命「次の柱」を探っている形です。
潜在的なニーズを掘り起こし、ターゲットの心に「響く」商品作りを
聞き手
「次の柱」とは、具体的にどのようなものになってきますか?
大山
弊社の主力である「ダストレスチョーク」を中心に、現在は窓ガラスやホワイトボードに描けて水でふき取ることで消せる筆記具「キットパス」や、風で飛散しにくく事故の心配もない「ダストレスラインパウダー」などの商品を追加しています。これらはチョーク製造・販売を続けるなかで感じた消費者ニーズに応える商品であると自負しています。また、昭和50年に川崎市に全国で初めてとなる心身障害者多数雇用モデル工場第1号を開設したのですが、その際には「ジョイント事業部」という新たな事業部も立ち上げました。弊社は障害者の積極雇用を続けてきたのですが、常々「簡単に作れるチョークだから障害者雇用が可能なんだ」という声にも晒されてきました。それらに反論したいという思いが新事業部立ち上げに繋がったのです。「障害を持った人でも、チョークだけでなくもっと高度な仕事ができるんだ!」という意気込みを形にしつつ、世の中と障害者をジョイントさせるという意味で「ジョイント事業部」としました。水道まわりの部品などのプラスチック成型という、とても細かな作業を要する事業ですが、多くの人脈に支えられて今日まで細々と継続しています。

聞き手
新商品開発や新事業部立ち上げに繋がるチャレンジ精神は、御社の社風にあるのでしょうか?
大山
やはり小さい会社なので、とにかく切羽詰まって考えざるを得ない、行動を起こさざるを得ないという状況に陥りやすいというのはあります。チョークが下火だから、「今のうちに次の種まきをしよう」と。新商品にしてもいろいろなものを作って市場に出してみないと成果には繋がらないわけですから、結果を出すためには「やるしかない」。さらに結果を出しても、それで安泰というわけでは決してなく、次は海外などへ販路をさらに広げていく必要も出てくる。最終的に新しい挑戦もきちんと生業になるようにする必要があるし、ひと言で言うと「切羽詰まっているから、いろいろなことをやらざるを得ない」というのが現実です。
聞き手
新商品の開発時に大切にされていることは?
大山
例えば「キットパス」という商品を例に挙げると、「絵を描く」ための商品です。ともすると子ども向けのものと片付けてしまいがちですが、「絵を描く」楽しみは、何も子どもに限定されたものではないはずなのです。商品が本来持っているターゲットとは異なる層にも、共通のニーズがあるのではないかと想像することから、新しい商品が生まれることはよくあります。そうした発想から、昨年9月にはビジネスマン向けの「キットパス」を市場に出しました。お風呂の壁に描ける筆記具なのですが、お風呂というのは頭を整理するのにとても良い時間だと思うのです。リラックスしているからアイディアが出やすいというのもありますし、思考がまとまりやすかったり、効率よく記憶できたりというのもあるようです。そこで忙しいビジネスマンのみなさん向けに「入浴をクリエイティブな時間にしていただけたら」との思いから、大人向けのパッケージで「キットパス」をお届けしてみました。(http://www.rikagaku.co.jp/items/ofurootona.php)残念ながら結果は思わしくなく、商品としてはいまだ消費者の心に届いているとは言えません。しかし、そうした失敗を繰り返しながらマーケットを切り分け、それぞれの層に「響く」商品作りを心がけています。
聞き手
組織作りや社会貢献、販路拡大など、社長の役割は多岐に渡りますが、ご自身にとって優先順位は?
大山
現時点では、ある程度いろいろなことがうまくまわりだしているという手応えがあり、こうなると一番重視したいのは「人」です。なにせ社員全員が成長していかなければ、会社は成長しないわけですから。挨拶や物を大切にするなど、「人としてここだけは欠かせない」というところが強固になればなるほど、基盤がしっかりとできあがり、そのうえに成長を積み重ねても揺らぐことのない盤石さを手に入れることができます。しかし「なんとなく良い流れだから」と、そういった「人として欠かせない」部分を見過ごして利益ばかりを追求していては、のちのち土台から崩れてしまう恐れがあります。会社というものは人で成り立っている組織ですから、人が成長していくということがなにより重要。「物心両面の働く幸せの実現」というのが弊社の企業理念というか、ただ一つの目的です。

※掲載の記事は2017年5月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。