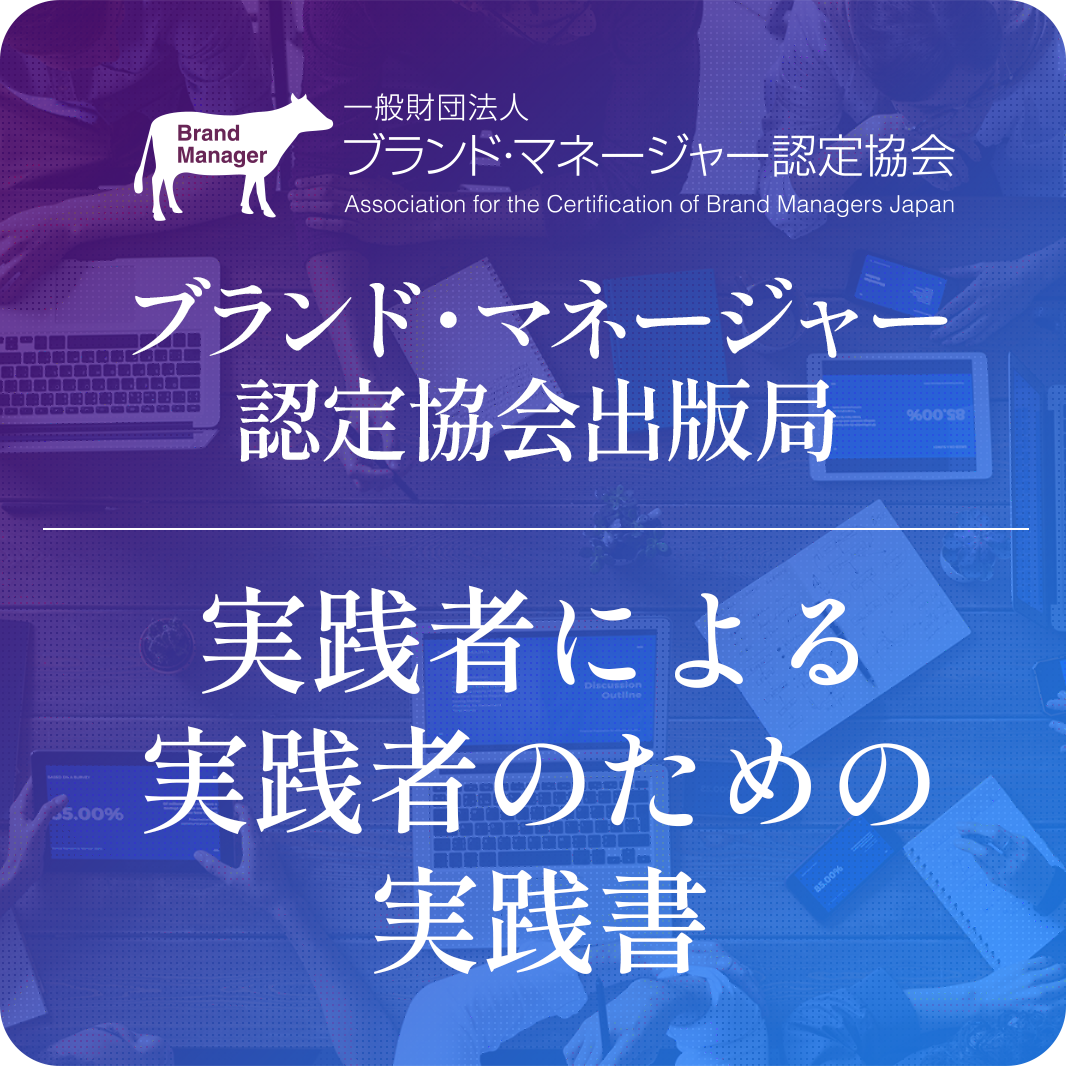ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >敷島製パン株式会社(Pasco) Vol.1
「超熟」ブランドの誕生・育成から「社会的価値」の創造へ – 前編
敷島製パン株式会社(Pasco) Vol.1
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【敷島製パン株式会社のプロフィール】
1920年6月創業。
パン、和洋菓子の製造販売を行う、老舗製パン企業。
国内に15工場、事業所は国内に40か所。
売上高は170,173百万円(2014年8月期)、国内製パン業界2位のシェアを誇る。
また冷食事業、海外事業も展開している。
製パン事業ではPascoブランドで商品を展開。
中でも主力商品「超熟」は、食パン市場でNo.1シェアを誇る人気商品である。
「金儲けは結果であり、目的ではない。食糧難の解決が開業の第一の意義であり、事業は社会に貢献するところがあればこそ発展する」
という創業者・盛田善平の理念を今も守り続けている。
「敷島製パン」と「Pasco」の関係
聞き手
本日はお忙しいところお時間をいただき、誠にありがとうございます。敷島製パン株式会社総務部広報室室長の加藤博信さんと、同社マーケティング部部長の石橋徹さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず「Pasco」という企業ブランドについて、それから「超熟」というファミリーブランドについてお話いただけますか?
加藤
「敷島製パン」よりも「Pasco」のブランド名をご存知の方が多いかもしれませんね。敷島製パン株式会社は1920年に創業し、「シキシマ」のブランド名で中部地区・関西地区を中心にパンや和洋菓子の製造・販売をしていました。1969年に関東地区に進出した際に「Pasco」というブランド名を使用し始めましたが、この「Pasco」という言葉は、パン(pa)敷島(s)カンパニー(co)の頭文字からとった造語です。当時、大手競合に対抗するために、独自性のあるイングリッシュマフィンやライ麦入りパンといったバラエティブレッドの展開でワンランク上のパンを製造するチャレンジャーメーカーとして、Pascoの名と共に差別化を図ろうとしたのです。

聞き手
当時から、差別化やブランド化を重視する会社だったのですね。先見の明があったということでしょうか?
加藤
当社は大正時代からすでに研究所的な組織を持つような会社でしたから、新しい商品を作っていくという考えが根本にあります。常にチャレンジ精神を忘れないということを大切にしているのです。
聞き手
なるほど。Pascoブランドではその姿勢を特に強調して打ち出したわけですね。現在はPascoブランドに統合なさっていますが、「シキシマ」と「Pasco」の2ブランドはどの時点で統合されたのでしょうか?
加藤
2003年のことです。現社長(盛田淳夫)の就任後に検討され統合しました。当時、関東地区ではPasco、中部・関西地区では地域によってシキシマとPascoの両ブランドが流通していました。そのため2つのブランドが別会社のブランドであると認識されていたため、ブランド・イメージにばらつきがあったことが統合の理由の1つです。唯一、1998年に発売された「超熟」だけは、ブランド統合の数年前からPascoに統一していました。ある意味、ブランド統合の準備をしていたようなものですね。
新商品「超熟」が生まれるまで
聞き手
では、その「超熟」が誕生した経緯をお願いします。今やPascoさんにとって主力商品であり、以前は小林聡美さん、現在は深津絵里さんが出演されるテレビCMの柔らかな雰囲気も人気を後押ししていますね。
加藤
ありがとうございます。先ほども申し上げましたが、「超熟」は1998年に誕生したブランドです。当時、食パンの競争環境が変化してきていました。業界第3位のフジパンさんがもっちりとした食感の「本仕込」という商品を出して、売り上げとシェアを伸ばしてきていたのです。業界第1位のヤマザキさんも、「新食感宣言」という商品で追随しました。これは、消費者のパンに対するニーズが、「風味」から「食感」に変わってきていたことを示していました。Pascoでも、この消費者のニーズに応えるため、新商品を開発する必要がありました。目指したのは「炊きたてのご飯のように、毎日食べても飽きないおいしさ」です。それを実現するには「材料の配合を変える」か「製法を変える」かの、2つの選択肢がありました。「材料の配合を変える」のは比較的簡単に対応できることでしたが、当社では、設備投資のリスクをとってでも、他社に模倣されにくい「製法を変える」という選択肢を選びました。そして、当時量産が難しいと言われていた「湯種製法」という手法を取り入れて誕生したのが「超熟」です。

聞き手
新しい製法を取り入れる上で、大変なご苦労をなさったのではないでしょうか?
加藤
「湯種製法」をヒントに自社開発した「超熟製法」は製造過程で様々な条件を満たさなければ品質を保てないため、量産化する上でそこをどうクリアするのかが最も大変でした。小麦粉を熱湯でα化(※)し、低温で長時間じっくり熟成させるため手間暇がかかるのです。
さらに、小麦の味の良さを分かっていただくため、配合する材料は抜けるところまで抜く「引き算」の発想で作りました。これはお客様に安心して、安全なものを召し上がっていただきたいという理由もあってのことでしたが、製造の上ではさらに難易度が上がることになりました……。こういった一連の製法は特許も取得しています。
※α化とは小麦粉のでんぷんが水分をたっぷりと吸収してふくらみ、熱エネルギーによってでんぷんの構造が変化し、粘りが出てモチモチとしてくる状態のこと。


聞き手
「超熟」にかける想いと覚悟が強くなければ成しえないことですね。開発中から、「超熟」が成功すると確信なさっていたのでしょうか?
加藤
正直、最初は不安もありました。工場で試作した当初、新しい製法に対して従業員から大変な反発がありましたし。ただ、開発を進めていくうちに不思議とそれが減っていったのです。どうやら、開発中の試作品を従業員が持って帰り、家族に試食させたところ明らかに反応が違ったそうで、今まで1枚も食パンを食べなかった子どもが朝2枚も食べたというようなことも聞きました。その話を聞いたとき、「超熟」は消費者のニーズに応えられると確信しました。
「超熟」というブランドの育成
聞き手
その「超熟」も誕生から15年以上が経ち、今や他より価格が高くても「超熟」を積極的に選ぶファンも多いと聞きます。コモディティ化しやすい業界でありながら、なぜロングセラーを続けているのでしょうか?今度は石橋さんからその辺りのヒントを伺えますか?
石橋
その時代時代のお客様に合わせて、常に新しい「価値」を提供できてきたからではないかと思います。「価値」といっても色々ありますが、まずは「機能的な価値」ですね。どこのパンも大差がないという時代から、味や食感にお客様が注目するような成熟した市場環境になりました。そこに我々はまったく新しいもの、日本人が好きな炊きたてのご飯のイメージ、耳まで柔らかく、しっとりもっちりした美味しいパンという、基本的な商品の「機能」を作り上げて、それが受け入れられたことが大きかったと思っています。まずはその「機能的な価値」がしっかりしていることが最低条件です。しかし、それだけだったら、それ以前にも美味しいパンはいくらでもありました。そこで重要となってくるのが「情緒的な価値」であると感じ、さらなる取り組みを進めていきました。
聞き手
まさにブランディングのど真ん中ですね。当協会の講座でも重要なポイントとしてお伝えしている部分です。当時からそういったブランディングを学ばれていたのですか?
石橋
実は、当時はそういったことに手探りで取り組んでいました。「情緒的な価値」とは何だろうか……と考えて出てきたのが、「食べて美味しい」だけではなくて、「食べて楽しい食卓」や「食べる喜び」をお届けしていくということだったのです。消費者の多様な食生活を想定し、それを提案していくマーケティングに至ったわけです。CMでもコミュニケーション戦略でも、“食生活の中の超熟”を提案し続けていきました。当初のシンボルキャラクターであった小林聡美さんも、今は深津絵里さんに代替わりしましたが、ずっと継続してお伝えしていきたいのは、「超熟」が持つ素朴でシンプルな食生活の世界観です。
「超熟」というブランドを守る
聞き手
ここまで「超熟」の誕生からの歩みを伺ってきましたが、「超熟」の中ではそれほど多くの商品ラインナップはないように感じます。
ラインエクステンションと言われる、「超熟」ブランドの派生商品を増やしてほしいというような声はなかったのでしょうか?

石橋
もちろんありました。特に社内からの声は強かったですね(笑)しかし、「超熟」は「食事パンである」という元々のコンセプトがしっかり作ってありましたので、そのコンセプトからブレないように意識し、ラインナップを絞ってきました。
聞き手
菓子パンのようなはっきりした味の付いたものは、「超熟」ブランドに合わないということですね。ブランディングにおいて絞り込みは、特徴を際立たせるためにも有効です。
石橋
はい。ですからラインナップに加えるものは、「超熟」シリーズ全体に新たな価値を提供できるものに限定しようと社内で意思を統一しました。たとえば「超熟ロール」という商品ですが、当初は「超熟バターロール」を販売したいという話が出ていました。しかし「超熟」は、余計なものを入れないシンプルな美味しさをコンセプトにしていましたので、バターを加わえた風味はそぐわないと判断しました。「超熟」でロールパンを出すなら、「超熟」らしいロールパンを出したい……ということで考え出したのが、「超熟ロール」です。シンプルな味わいの「超熟」の生地を、細長くホットドック用パンよりやや短くして、そのまま食べても美味しく、なにか挟んでも美味しいという価値を提供しました。

聞き手
ブランドの軸がブレてしまうことでブランド全体が崩れてしまうのは、往々にして起こりうる悲劇です。それを回避してこれたのは、「超熟」ブランドの取り扱いを決める規定のようなものがあったからでしょうか?
加藤
発売から2年ほどしたころ、社長がブランディングに取り組むことを宣言し、専門家の方と進めることになりました。その際に規定が作られました。
聞き手
ではブランディングに取り組まれたのは2000年ごろということですね。Pascoブランド誕生のいきさつでも感じたことですが、社長の先を見た経営判断には敬服します。
※掲載の記事は2017年2月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。