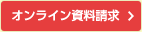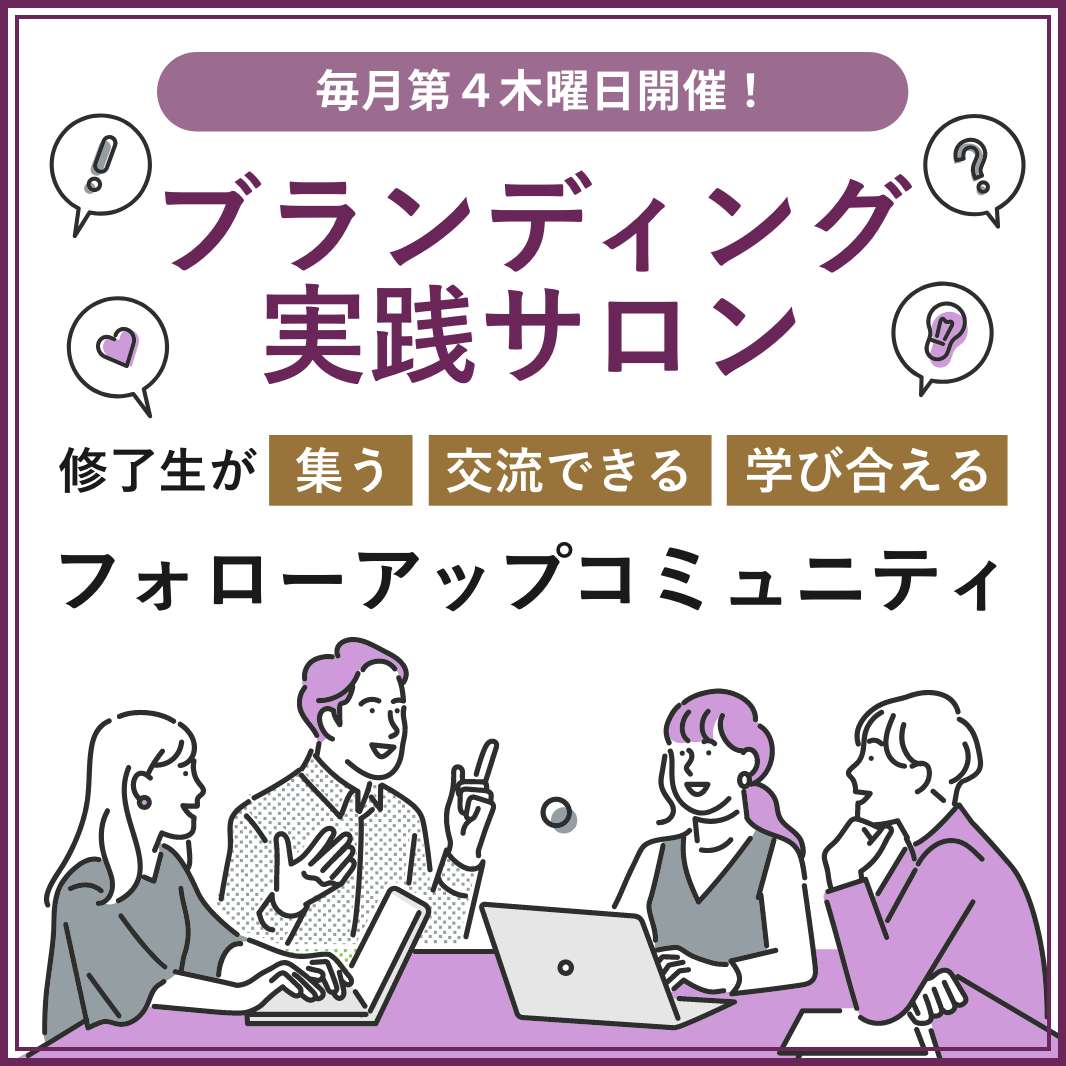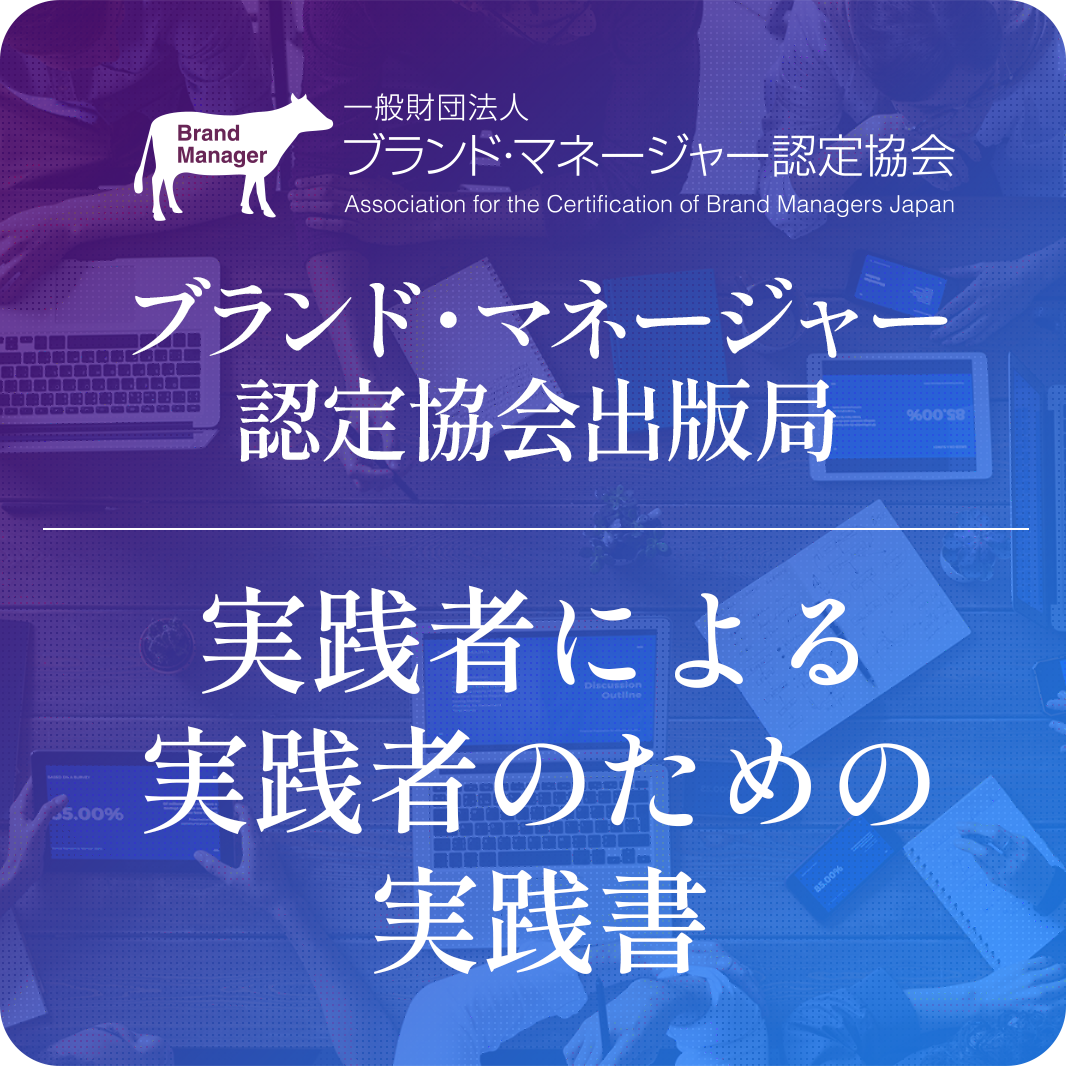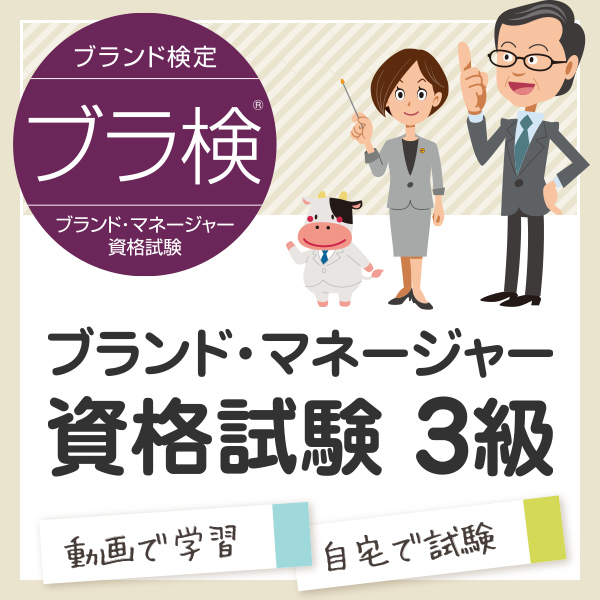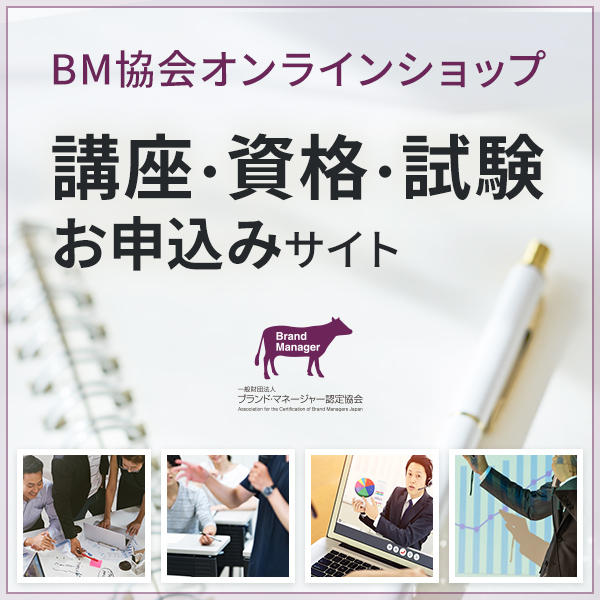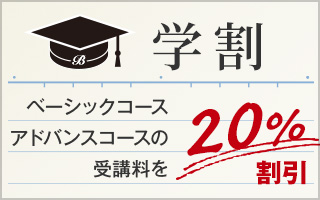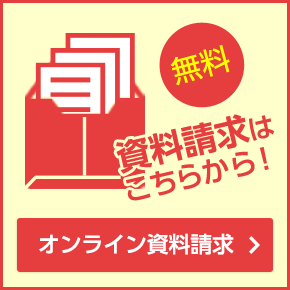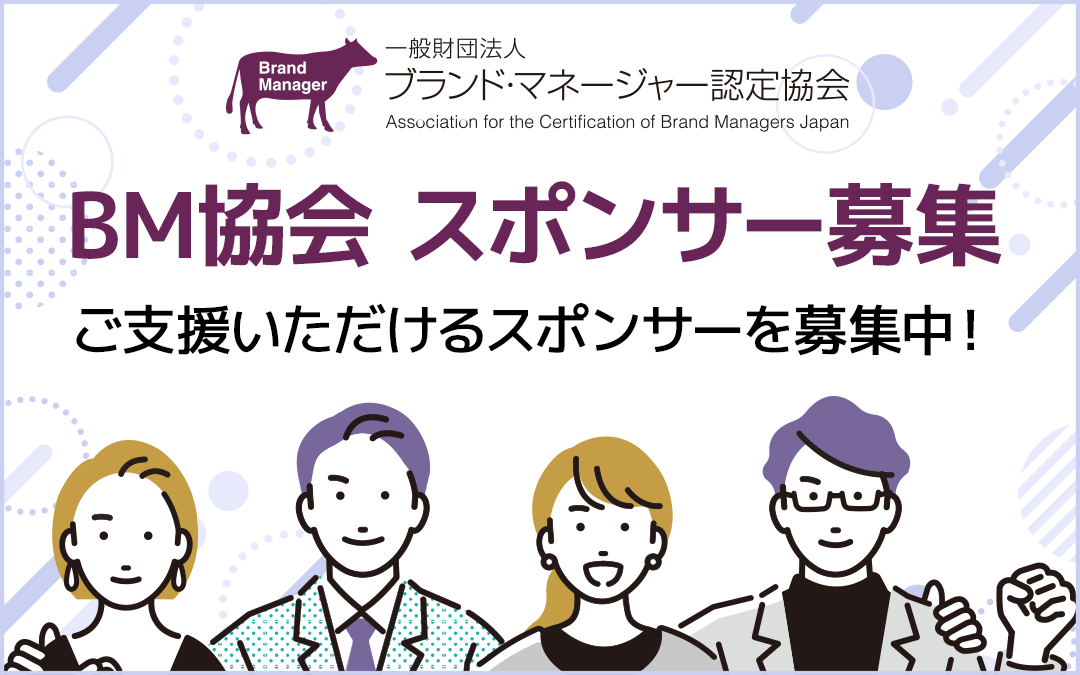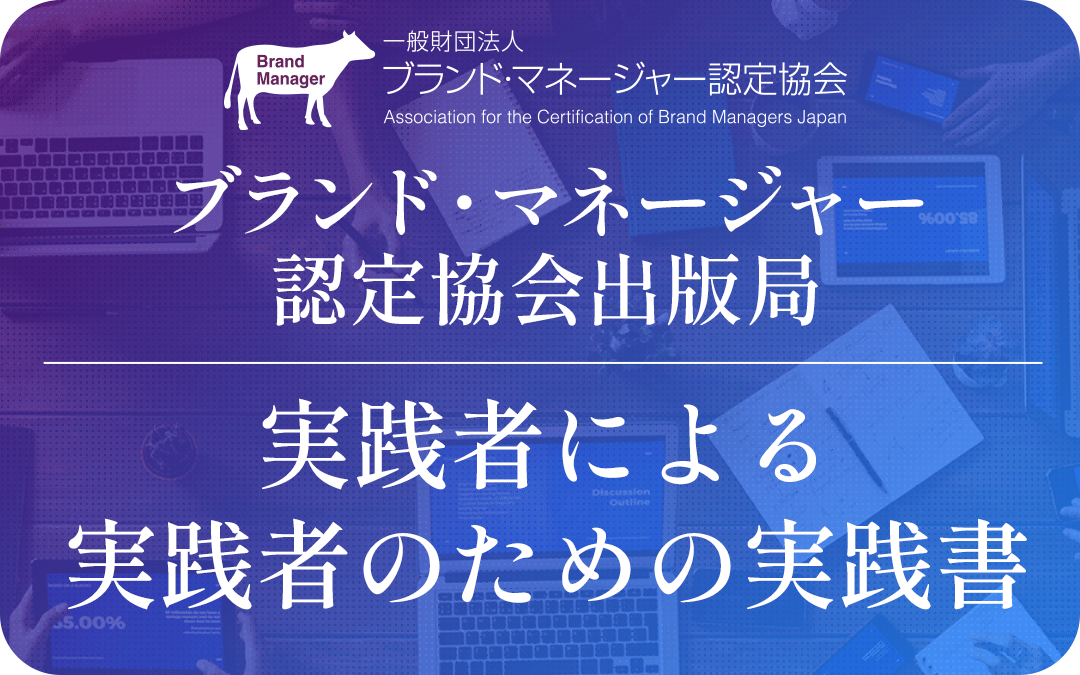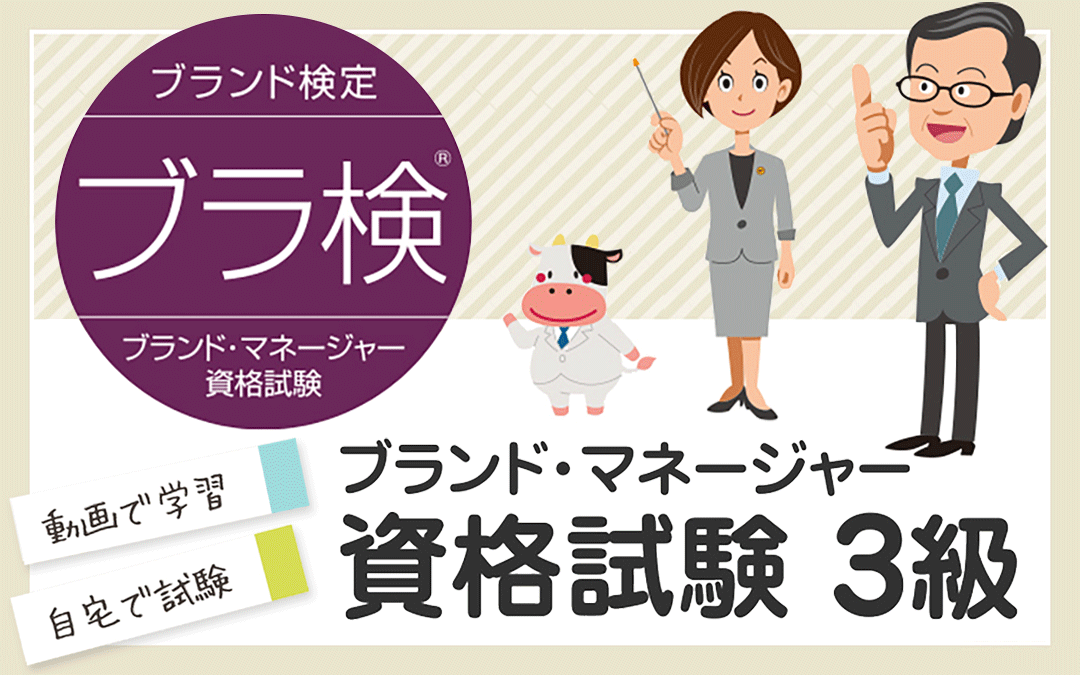ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >梶原 奈美子氏 Vol.2
市場規模を大きく広げた大ヒット商品を生み出した戦略とその背景 – 後編
梶原 奈美子氏 Vol.2 キリンビール株式会社 マーケティング部
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【梶原氏のプロフィール】
2004年日本リーバ株式会社(現:ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社。
ヘアケア商品のマーケティングを担当。
05年、タイの現地法人に出向しアジア全般にむけたマーケティングを経験。
06年キリンビールに入社。商品開発研究所に配属後、
缶チューハイ・ビール類の新商品開発を従事し、
09年に発売したノンアルコール・ビールテイスト飲料
「キリンフリー」が大ヒットとなった。
現在は同社マーケティング部で「キリンフリー」の
ブランドマネジメントを担当。
完成度80%のプレゼンシートで「壁打ち」に臨む
聞き手
「キリンフリー」の開発ストーリーが載っている『最初に飛び込むペンギンになれ!』(日経BP社刊)の中で出てくる「壁打ち」という言葉についてご説明いただけますか。
梶原
「壁打ち」という言葉自体は、キリンフリーの開発当時のマーケティング部長だった佐藤章が言っていた言葉なのですが、私もこの会社に入って結構いいなと思ったことの一つです。
例えば、外資系だと一人の担当者が最高の状態まで仕上げて、それを通していくというやり方が多いんですが、特に商品開発においては多面的な意見というのが大切なのです。
というのは、やはり、お客さまはいろいろな視点からいろいろなニーズが持っていて、その最大公約数を発見していくのがすごく大切だと思うんですね。
そのためにいろいろな仮説を立てて考えていくのですが、自分で「イケる!」と思っても、本当にそれがいろいろな側面からOKなのかどうか分かりません。
それを仕事の責任だからといって無理やり通しても、本当にそれでいいのかなと思っていたんです。
それは前の会社にいたころからずっと思っていたことなのですが、この会社に入ったときに、どこからともなく人が集まってブレストを始めると、一つのアイデアに対してぜんぜん関係ないこととかさまざまな意見が出てくるんですね。
その間にそのアイデア自体もいろいろな性格をもって膨らんでいく。
一人が自分の考えやアイデアにあまり固執するのではなく、自分が思っていることを相手にも共有してもらうことで、チーム全体でいいアイデアビルディングができるんです。
聞き手
ブレストとちょっと違うのはアイデアを重ねていくようなイメージでしょうか。
梶原
そうですね。壁打ちというのは、あるところまでは片方が考えて、それを向こうに投げて、また返ってくるような感じですね。
特に広告のオリエンテーションのときは、完璧にオリエンシートを仕上げ過ぎて、「もうこれだ!」と思って臨んだら、ちょっと違った視点から意見をもらっても受け入れられないことが多いんです。
でも、8割ぐらいまでオリエンシートを仕上げて壁打ちに臨むと、もっと発展的な話し合いができるんです。
聞き手
なるほど。プレゼンをやっていくプロセスみたいな感じですね。

梶原
そうですね。プレ・プレゼンみたいな。
壁打ちしましょうよと言うときには、私たちは8割ぐらいできたオリエンシートを、向こうは最近できた広告の現状とか、次はこんな広告がいいんじゃないかといったアイデアとかを出し合います。
ときには、クリエイターさん本人を連れてきてもらって、より突っ込んだ話になることもあります。そこで結構ズレたりするとまた議論があったりして、
「じゃあ、どういうクリエイティブがいいのか」、
「私はこう思います」、「こっちはこういうのがいいんじゃないか」
というふうに双方から意見を出し合って話し合えば、お互いにまた違ったアイデアが出てきます。
逆に、それをオリエンに戻して、オリエンシートを完成させることもあります。
聞き手
全部作ってきちゃったら、否定できなくなってしまいますものね。そこの途中のプロセスが結構大事かもしれませんね。
梶原
そうなんです。そこのふわっとしたところが大事ですよね。
「世界初、アルコール0.00%」のコピーが生まれた秘密
聞き手
ところで、クリエイティブに関することなのですが、キリンフリーが「世界初、アルコール0.00%」というコピーに至ったプロセスをお話いただけますか。
梶原
開発当初の頃に、「アルコールゼロが売りだよね」という話になったときに、じゃあ、どう表現すればいいのかということになり、「アルコール0%」と「0.0%」と「0.00%」でグループインタビュー(グルイン)を行ったんです。
で、一番最初に行った2007年の冬のグルインでは、「アルコール0%でいい」と意見が大勢だったのです。
それが、08年の秋に、異動してきた上司に「この商品のキモのコンセプトは何か」と聞かれたときに、「完全アルコール0%です」と答えると、「それだと弱い!」と一言で切り捨てられてしまったんです。
「0%」で言いたいことは、かなりはっきりしていると自分では思っていましたから、とても意外だったんです。
実は、私がこの開発に集中している間に、「糖質ゼロ」ブームというのがあったのです。
それでもう一度、グルインにかけてみると、皆さん「0.00」の方がいいと言うんですね。
聞き手
それは、最初のグループインタビューでの突っ込み方が足りなかったのでしょうか。
梶原
いえ、07年のグルイン当時は、市場環境に「糖質ゼロ」とか「カロリーゼロ」とかのゼロブームがまだ来ていなかったんです。
だから、「アルコールゼロ」という数字にまだ新鮮味があったんですね。
その後、市場が「カロリーゼロ」という別のゼロで盛り上がってきた。
で、「同じゼロだと何のゼロか分からないし、第一紛らわしい」と。ゼロ自体がもう新しいものではなくなっていたんです。
聞き手
ゼロという表現のステージが変わっていたのですね。
梶原
そうなんです。もうすでにほかが変わっていたので、それに合わせて自分たちも変わらなければならなかったのです。
聞き手
なるほど。それが「アルコール0.00%」を生んだわけですね。今年に入ってからは、何か新しい動きはありますか。
梶原
リニューアルをしたというのがすごく大きなところで、パッケージ自体も缶は白をベースにした緑のロゴが爽やかものに変更し、中味もノンアルコールを飲まれるお客様が健康志向であることを意識しています。
.jpg)
梶原
また、お客さまの反応を見ていると、キリンフリーは味というところを大事にしてほしいという声が多かったんです。
そうしたら、やはり自然なビールのおいしさみたいなところをより大切にしていこうということで、「自然素材のおいしさへ」、「人工甘味料・合成香料・酸化防止剤無添加」でいこうと。
それが今回の新しい打ち出し方ですね。
テレビCMのタレントさんも新しい人を2人起用しています。
聞き手
健康志向のニーズを拾っていこうということですね。
梶原
そうですね。開発当初は、イメージするターゲットが30代男性のビールユーザーというところにあったのですが、実際に消費しているのは若年層や女性だった。
ですから、今実際に利用されている人たちに需要されるようなポジショニングに変えていったところです。
聞き手
それは想定していなかったことなのですか。
梶原
トライヤルはイメージターゲットどおりだったのですが、実際にリピートしてくれたのは20代の若年層と女性でした。ボリュームゾーンがかなり移行したという感じですね。
聞き手
まさにヒット&エラーの中で見えてきたものなのですね。
ところで、梶原さんがこれまでの経験を通じて、商品開発でもブランディングでもマーケティングでもいいのですが、失敗するケースと成功するケースの分かれ目はどこにあると捉えていますか。
梶原
一つは商品として正しいというか、ある程度、商品の出来が良くないと売れません。それは絶対条件です。
もう一つは空気感ですが、社内の盛り上がりという部分がちゃんと喚起できていたかということですね。
あとは、新しいタイプの商品に関してはPRの力って最近はすごく重要だなと思っています。
今は話題にできたかどうかが、広告の出来がいいかどうかよりも大事になっていると思います。
新しい人は今の生活者感覚を大切にして
聞き手
梶原さんは今のお仕事は好きですか。
梶原
ええ、好きですね(笑)。
聞き手
どんなところが好きですか。
梶原
お客さまの生活が変わるところですね。
聞き手
それは生活者にいい影響を与えているということでしょうね。
梶原
そうですね。やはり、キリンフリーを出したことでいろいろな人のビールとの付き合い方が変化していて、そういうのをグループインタビューで聞くたびにすごくうれしくなるんですよ(笑)。
聞き手
今後、マーケティングの先輩として後輩たちにどのようなことを伝えたいですか。
梶原
今、世の中がすごく変わってきているなと感じていて、やはり旧来的なマーケティングの手法だけだと太刀打ちできないなと思います。
ある程度商品が完成されていたら、広告がうまくいけば売れた時代もあったと思いますが、今、旧来的な手法でそれをやろうとするとものすごくお金をかけて、GRP(延べ視聴率)をすごく増やさなければ無利でしょうね。
逆に、お金が少ないときには知恵を絞って、PRや社内をうまく使うとか、ちょっと昔のモデル以上のプラスオンみたいなことを自分たちで考えていかなければならない時代だと感じています。
これからマーケティングの仕事をしようと考えている若い人たちには、今の生活者感覚みたいなものを大切にしてほしいと思います。
会社に入ってしまうと、
「結局、マーケティングなんてタレントなんだよ!」
とか(笑)上司に言われてしまう。
確かにそれもかつては大きな要素だったとは思いますけど、今はそれだけだとダメですね。
今は、PRとかをどう使っていくか等、今の時代のマーケティングを自分なりに考えられるマーケッターが活躍されているように思います。
聞き手
最後に梶原さんの今後の夢や目標を教えていただけますか。

梶原
すごくざっくりしているのですが、時代が変わってきているなというのを感じています。
やはり会社も変っていかなくてはいけないですし、それに対して個人でもっといろいろできることがあるんじゃないかと思います。
私は、今までは商品を通じてじゃないと世の中に発信できなかったことがすごくたくさんありました。
例えば、私はあんまりたくさんお酒を飲めないんですけど、そういうときに「キリンフリーってごくいいよね」っていう自分の思いを商品に乗せて発信していたりしたんです。
でも、それって、ある意味データでは出てこないニーズですよね。
これまでのマーケティングは、お客さまの重要なニーズをより満たすことを重視してきました。
例えば、ビールにおいて「キレ」がお客様の重要なニーズとした場合、 各社が「最もキレのある」商品を追求してきたわけです。
しかし、現在はもうこうした「物性のわずかな差別化」を競争していく世の中ではなくなりました。
明確な「価値」や「提案性」のある商品が売れる時代です。
最近は、これまで通りのグループインタビューや市場調査だけではなく、時代の一歩先を読み、お客様の求めるものについて考察を深め、新しい価値を提供できる力が求められていると感じています。
そういう意味で、ブランド・マネージャーや商品をやっている人の「個」の時代が来そうな感じがしています。
また、時代の変化を捉えていくためには、旧来的な価値ではない「新しい芽」を大切にしていかなければいけないと思います。
例えば、お客さまがビール離れしている。
じゃあ、なぜなんだと。
旧来的なビールの価値を魅力的に伝えていくことももちろんそうなのですが、そうではないまったく逆の発想を提案してみたりとか。
そういうのは調査では出てこない個人の蓄積みたいなものがすごく力を発揮するんですね。
そういうことをこれからの仕事に生かしていきたいですね。
聞き手
ああ、なるほど。単純にその商品を媒介して何かを伝えるだけではないということですね。
梶原
個人的な思いとしては、新しい芽を育てる活動って企業活動の中だけではまかないきれないものがあると思うんですよ。
研修や、マーケティング手法では、変化の激しいこの時代にお客様に魅力的な提案ができる力がつかない、そういう時代になってきているなと感じます。
私は、仕事を通じて知り合った人たちから、半個人的な繋がりに発展して、色々な意見交換や勉強をさせてもらっています。
そこで、個人と個人の思いが繋がって、最終的に仕事につながっていったという話をよく聞くんですね。
今後はフレームの中で仕事をするのではなく、個人の仕事力というのがますます大切になってきそうですね。
結局、仕事とは自分の持てるものを社会に還元しよりよくしていくことだと思うのですが、これからは、個人が社会に貢献できる仕事力を高めていくことで、結果的に会社にも貢献できるし、よりよい仕事ができるという時代になると思っています。
聞き手
働き方の環境もどんどん変わってくるでしょうし、今、社会起業家という若い世代の人たちがいっぱい出てきていますよね。
社会貢献とか世の中のためにとかの意識がすごく強くなってきていて、今までの時代と明らかに違ってきているなと感じます。
その意味でも梶原さんには今後のご活躍を期待しています。今日はありがとうございました。
※掲載の記事は2015年8月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。