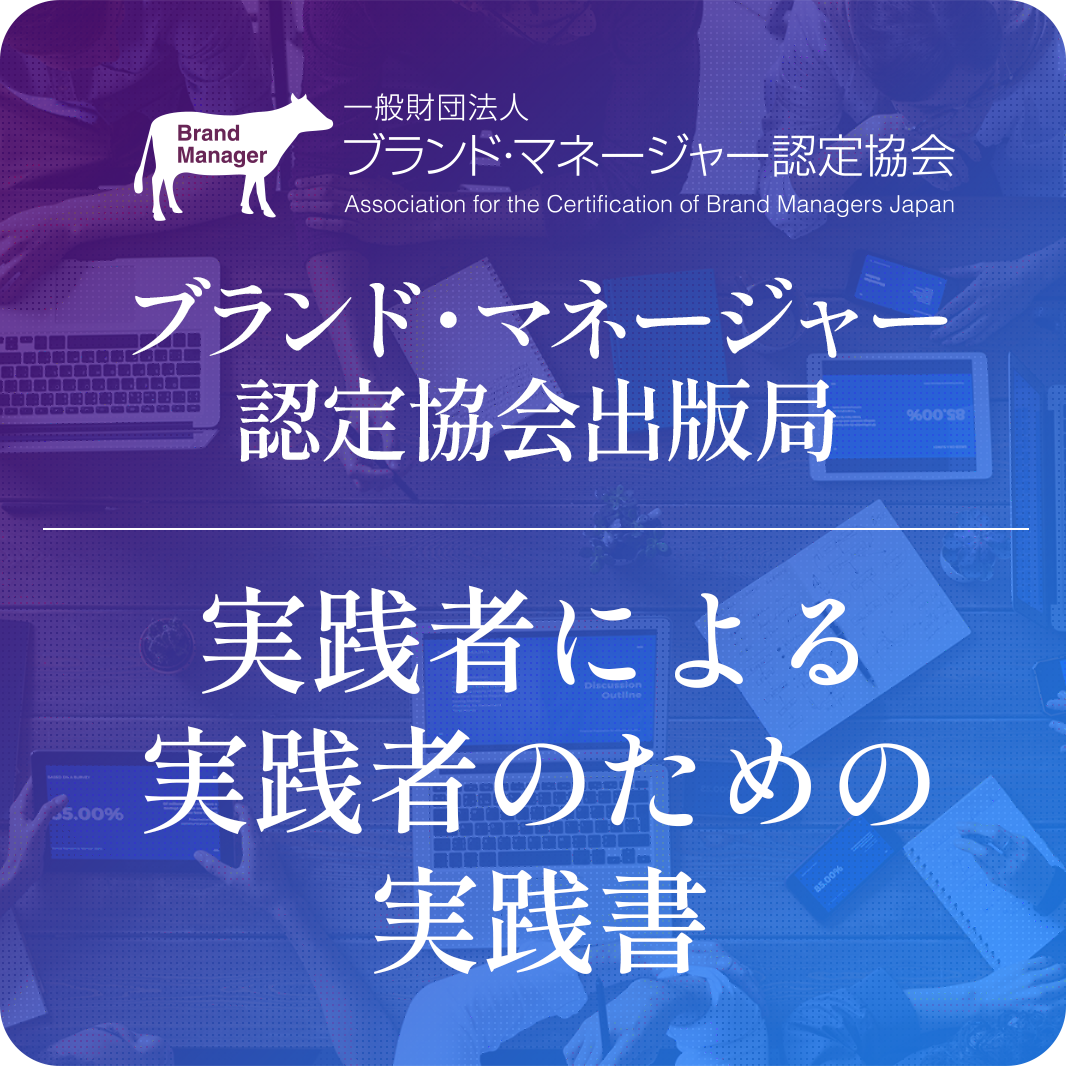ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >高野 登氏 Vol.2
~存在そのものがブランド~リッツカールトン流ブランディングとは 後編
高野 登氏 Vol.2 人とホスピタリティ研究所主宰
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【高野登氏のプロフィール】
1953年長野県生まれ。
元 ザ・リッツカールトンホテル日本支社支社長。
プリンス・ホテルスクール(現日本ホテルスクール)
第一期卒業後、ニューヨークに渡り、
ホテルキタノ、 NYスタットラーヒルトン、
NYプラザホテル、SFフェアモントホテルを経て、
1990年ザ・リッツカールトン・サンフランシスコ入社。
1992年に日本支社立ち上げのために来日。
その後ホノルルオフィス開設のため
ハワイへ転勤後、1994年に日本支社に転勤。
1997年にザ・リッツカールトンカンパニー大阪開業。
2007年3月にザ・リッツカールトンカンパニー東京を開業。
2009年、ザ・リッツカールトンカンパニーを退社。
2010年、人とホスピタリティ研究所を設立。
著書に『リッツカールトンが大切にするサービスを超える瞬間』
『絆が生まれる瞬間 ホスピタリティの舞台づくり』(どちらもかんき出版刊)。
ホスピタリティとブランド戦略は別もの
聞き手
ホスピタリティと企業のブランド戦略はどう関連付けていますか。
高野
それは別ものです。
ブランドはイメージのものですから、ホスピタリティとごっちゃにしてしまうとわけが分からなくなります。
聞き手
サービス業では、一貫性をもってブランドづくりのためのおもてなしをしようという話をよく聞きますが。
高野
ブランドづくりのためにおもてなしはできないと思います。
ブランディングは科学的に突き詰めていくものです。
感情論ではブランドは絶対にできません。
聞き手
例えば、「第二のわが家」というコンセプトがあって、それに対するおもてなしやホスピタリティを統一しようという意識は?
高野
ブランディングとは子どもを生み出すようなものです。
それをどうやって毎日育てていくかという一貫性がないとダメだということですね。
しかし、それは現場の話であって、ブランドづくりとは別ものです。
ブランディングはもう少し次元の高いところで、50年後にどういうブランドにしたいのかといったビジョンのもとに遂行するものです。
最初にボタンを掛け違えると後で大変なことになってしまいますからね。
毎日どういうふうにお客さまをお迎えするか、どんなおもてなしするかというのは、現場の日常なわけです。
それはきちんと切り離して、なおかつブランドのイメージからはずれないような手法を作っていかなければなりません。

聞き手
ブランディングで一番意識されていたことは何ですか。
高野
リッツカールトンのブランドからはずれないということですね。
リッツカールトンが創業のときから持っていたブランドづくりのイメージからブレない。これが一番重要なことでした。
聞き手
高野さんにとって、「らしさ」とブランドはどう関連付けられますか。
高野
ブランドが「らしさ」をつくっていくということです。
「らしさ」とはみんなの共通認識の中で立ち上がっていくものです。
例えば、リッツカールトンらしさ、ヒルトンらしさ。
それが会社であれば、その核になるのはその会社の理念でありビジョンです。
そうした具現化されたものが「らしさ」を表現しています。
聞き手
もう少し具体的に言うと。
高野
人を見れば分かると思うのですが、「○○さんらしいよね、この行動は」と言うとき、その人の人格や生き方が共通認識としてあるからそう言えると思うんです。
会社でいえば、企業風土や企業文化ですね。
それはどこに立脚しているかというと、「うちの会社はこうあらねばならない」という一番真ん中にある理念です。
そのイメージを全て表すのがブランドだということです。
創業の思いをリーダーが語り続けること
聞き手
高野さんは今、企業研修などで活躍されていますが、その中で共通項として伝えたいものは何ですか。
高野
研修のテーマは組織づくりだったり、従業員育成だったり、企業によってニーズが違いますから、そのニーズに応えることに努めています。
ただ、一貫して伝えているのはリーダーの姿勢です。
リーダーがどういう姿勢で仕事をするのか。
顧客づくりでも人材育成でも、リーダーが何をしたいのかが見えていないと、従業員が追いかけるものがありません。
ですから、リーダーがそれを明確に持っているかどうか、それを社員にどう伝えるかという仕組みができているか。
その2点だけは最初の段階で確認させてもらいます。
聞き手
それがなかったらお手伝いしようがありませんものね。
高野
それがなければ、研修やトレーニングに入っても「のれんに腕押し」で意味がありません。
まず、「思いありき」ですね。
思いがあり、言葉があり、言葉が行動を生み、それが習慣化されて企業風土が形成されます。
最初の「思いありき」というのは、そもそもこの会社を何のために始めたのかという「創業の思い」ですね。
思いとは理念やビジョン、つまり会社が存在する目的です。
それを言語化した言葉が、会社の中の行動パターンをつくっていきます。
その行動パターンが続いていく中で、従業員の仕事の習慣が出来上がっていきます。
その習慣が企業風土をつくるのです。
それがリッツカールトンのやり方でした。

聞き手
その思いが従業員に伝わっていない会社は多いと思いますが。
高野
それはいくらでも修正のしようがあります。
どこが問題かということだけチェックすればいいのです。
聞き手
思いから言葉、言葉から行動、行動から習慣、習慣から企業風土をつくり上げていくのが企業活動の究極の姿だと思いますが、いろいろな企業を見られてきて、どの部分が一番難しいとお考えですか。
高野
一つはリーダーの姿勢。
リーダーが思いを伝え続けるというエネルギーをどこかで制御している。
そういう会社が多いと感じますね。
会社が大きくなっていくと思いを伝える仕組みが必要になってきます。
しかし、その仕組みの中で、思いを語るのはリーダーしかできない部分であって、これは会社の規模が大きいからといったエクスキューズができない部分なんです。
ですから、リーダーはそれを語り続けなければならないのです。
もう一つは人材育成の問題です。
人材育成には、オリエンテーションと研修と教育という3つの側面がありますが、それが一緒くたになっている企業が多いですね。
基本的に夢とビジョンを語り続けるオリエンテーションに、研修とか教育を持ち込んではいけません。
研修とは知識やスキルをきちんと伸ばしていくという役割がありますから、そこにオリエンテーションを持ち込むものでもありません。
スキルを学んでいるときに、「私たちはこうありたいのです」なんて夢を語っても場違いなだけですからね。
教育は人間的成長を支えるものです。
仕事をしていく上でプロとしてどのレベルまでその人に育ってほしいかを見極めて、そのために時間を割くのが教育です。
ですから、オリエンテーションと研修と教育はきちんと分ける必要があります。
これがゴチャゴチャになっていると言葉が生まれてきません。
だから、行動に素直に移れない。
毎日の行動の中で言葉が生まれるように仕組み化していくことが必要だと思います。
企業規模が大きくなっていく中で一番の問題は、前述しましたが熱い思いが見えづらくなっていくことです。
会社が小さな頃はみんなで車座になって夢を語り合っていたのが、成長するにつれてその思いを語らなくなってしまうという企業の話は山ほど聞きます。
聞き手
それは思いが薄くなっていくということでしょうか。
高野
というより、規模が大きくなるにつれてリーダーが発信しなくなっていくんです。
今のリッツカールトンは全世界で4万人の社員がいますが、会社の価値観をみんなが共有しています。
それはトップが思いを絶えず語り続け、発信するエネルギーを惜しんでいないからです。
言葉できちんと伝え、思いを共有する仕組みができているからです。
西洋文化で特徴的なのは言葉で伝えようとすることですね。
日本は共通言語としての日本語があるからか、「以心伝心」や「あうん」の呼吸のように、言わなくても分かるだろう的なコミュニケーションの企業がまだまだ多いですよね。
「それくらいは君の思いで受け止めろ」みたいな。
でも、何十カ国で展開するグローバル企業だと、国によって思いの受け止め方もバラバラです。
ですから、きちんと理解できる言葉で相手に届くまで語り続けなければならないのです。
西洋のトップは語る時間を惜しみません。
聞き手
しつこいぐらいに言い続けることが重要なのですね。

高野
それこそリッツカールトンのトップは本当にしつこいですよ(笑)。
思いを理解させるだけでなく、従業員がそれを本心で思えるようになるまで徹底してやりますから。
聞き手
「ブランドをつくる」という部分で、リッツカールトンの従業員が取り組んでいる仕組みというものはあるのですか。
高野
毎日の行動そのものがブランドづくりなのです。
どういう言葉を使うか、どういうあいさつをするか、どういう行動をとるかなど、ホテルの中の営業活動そのものがブランディングなのです。
ですから、今日はブランドをつくるためにこれをやるというものはありません。
ただ、ブランドの一員として、例えば、「ペットボトルから直接飲料を飲まないようにしよう」といったそれぞれのカンパニーの約束事は存在します。
聞き手
そうした行動規範は社員が自発的に作ったものなのですか。
高野
本社が作った「クレドカード」が行動の規準になっています。
「クレドカード」に私たちは最終的に何をしたいのかという「目的」がきちっと書かれているから、たたずまいから、ふるまい、歩き方、髪型、しぐさ、表情に至るまで、毎日の仕事の中にそれを軸にした行動が生まれてくるのです。
ただ、ブランドの軸をきちんと持ちながらも、それを一方的に押し付けるのではなく、その国の文化を尊重する謙虚な姿勢は持ち続けていかねばなりません。
聞き手
今日は大変貴重なお話をありがとうございました。
※掲載の記事は2015年10月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。