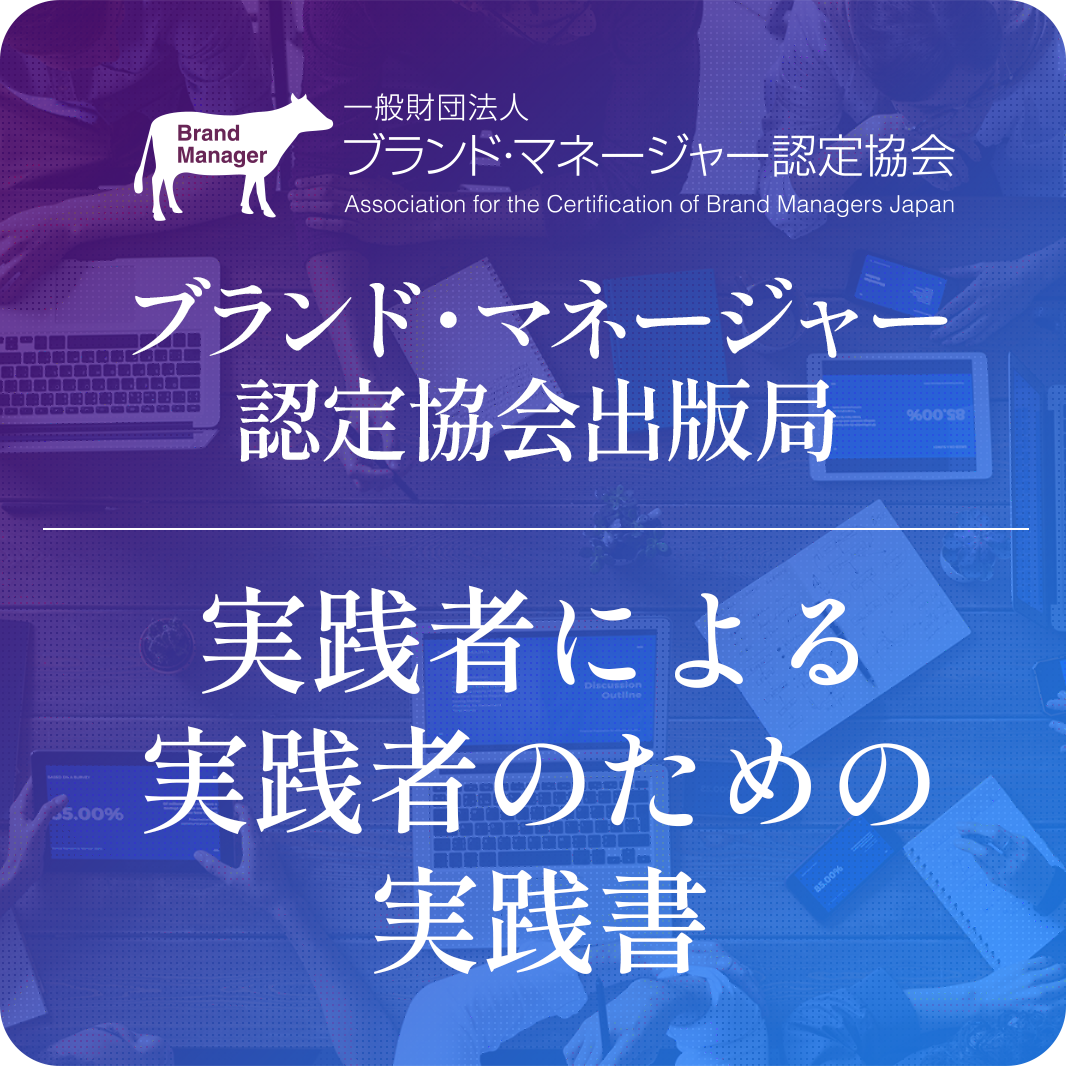ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >浅田 克治氏 Vol.2
本質を見極める思考からつくりだされるクリエイティブワーク – 後編
浅田 克治氏 Vol.2 ASADA DESIGN アートディレクター
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【浅田氏のプロフィール】
ニューヨーク在住の世界的なアートディレクター。
多摩美術大学グラフィックデザイン科卒。
ボツフォードケッチャムインターナショナル東京支社および
ニューヨーク支社を経て1981年独立。
同年8月、ニューヨークに「ASADA DESIGN」を設立。
ティファニー、日本航空、ニューヨーク現代美術館(MoMA)、
ナカミチ、TDK、Japan Image Communications (JIC)、旭硝子、
オリンパス、MRC (ハイエンドオーディオ機器)、 Krell (ハイエンドオーディオ機器)、
Emerson Spa & Resort、Index Holdings,Inc.、 William Lipton Ltd.(アートギャラリー)、
非営利団体フレンズウィズアウトボーダー、ピクトリコ(三菱製紙)、
千山窯(砥部焼)等、多数の商品のアートディレクションから
デザインコンサルタントを勤める。
自分を取り戻す作業が不可欠
聞き手
アメリカで長くアートディレクションの仕事をされてきて感じることは何ですか。
浅田
アメリカのビジネス社会の中にいると自分が磨り減っていくんです。常に戦い続けなくてはならないし、自分を主張し続けなければならない。そして、「私はこう思う」という自分自身を持っていなければ生き残っていけない世界です。
聞き手
自分を保つために週末の田舎の時間が大事だったわけですね。
浅田
マンハッタンの中にいると自分を失くしてしまうくらいエナジーがすごいんですよ。ですから田舎で過ごす時間はものすごく大事でした。
聞き手
自分を失くすとは、マンハッタンという都市に巻き込まれる感じですか?
浅田
目に見えないエナジーがすごいんです。自分の意思とは関係なく持っていかれる感じ。ですから、自分にフォーカスするというか、自分を取り戻す作業が必要なんです。それがないと染まってしまう。
聞き手
自分にゆとりを取り戻す?
浅田
言葉はいろいろあると思いますが、ありのままの自分でいたいという意思がないと環境に染まってしまう。そのエナジーがものすごく魅力がある。
あそこで何かをクリエイトすると、世界にそのクリエイションが発信されるわけですよ。
だから、そのパワーに乗っかってしまうと、自分もそうなのかと勘違いしてしまう。
それをアジャスト(調整)するためには自分だけの空間をしっかり確保していないと持たないんですね。
聞き手
ある意味、東京もそうですよね。

浅田
東京はもっと怖いかもしれない(笑)。
徐々にですが、それまで週末だけに通っていたキャッツキルに7年ほども前から金曜日も月曜日も過ごす様になり、ついに5年ほど前にマンハッタンからアサダデザイン事務所をキャッツキル(マンハッタンから車で2時間半北に在る穏やかな山地)に移し、いまは逆に週1?2回打ち合わせにマンハッタンに行き、後は山里で仕事をしています。
そこへデザインスタジオを移すと同時に始めたのがブログ。これが一番生身の僕自身じゃないかなと思ってる。
写真を撮ってブログにアップする。
写真日記みたいなものなのですが、僕の家族や友人たちやクライアントに、僕が今どういう生活をしていて、どういうものの見方をして、何を感じて生きているのかを発信する。
写真といっても僕の家の周りや身の回りを撮っているだけです。
蒔ストーブに火を入れて、「寒くなってきました」なんてことを書き込む。
どうということではないんですが、そこに自分がある。そのメッセージがないと何も創れない気がします。
聞き手
本来の自分を解放する感覚ですか。
浅田
自分が信じているものとか自分の脳の中を相手にぶつけて初めてエナジーが生まれ、コミュニケーションが成立します。
自分がないのに先のものばかり追いかけてもコミュニケーションは生まれません。
聞き手
そこできちっと今の自分を取り戻す作業をするということですね。
浅田
そう。それをやらないと伝える仕事はできません。逆に言えば、それをやっているから生きていられるのです。
ティファニーも街のパン屋の仕事も同等
聞き手
これまでさまざまな仕事に携わっておられますが、ティファニーとはどのような経緯で取り組むようになったのですか。
浅田
テイファニーのデザイン室(ジュエリーデザイン)には多くのデザイナーがいますが、外部のデザイナーで、一人がパロマ ピカソというピカソの娘さんで、もう一人はエルサ・プレッティというスペイン在住のデザイナーです。
で、アサダデザインを設立した頃から、この二人のデザイナーの広告のアートデレクションの話しが来まして、そのころ他のテイファニーの広告は大きなアメリカの広告代理店が作っていたのですが、パロマとエルサの広告はティファニーの宣伝部と直接、僕がやる様になったのです。
聞き手
最初のきっかけはどういうものだったのですか。
浅田
きっかけはティファニーの宣伝部へのプレゼンテーションですが、僕を採用してくれた宣伝部は、今度は上層部にプレゼンするわけです。
僕というテーストの背景には「日本」という文化があって、ティファニーはそれを気に入ってくれたようです。
聞き手
なるほど。
浅田
それは僕の中から自然と出てくるものなのです。
クリエイティブに使う素材はミーティングの段階で僕が選べるのですが、例えば、エルサが作ったクリスタルのボールがある。
ジュエリーだけでなく、彼女がデザインしているもので食器やナイフ、フォークなどがあって。
僕はクリスタルのボールがいいなと思ったんです。
そのボールの形というのは、どこか温かいし、まるで鳥が自分の巣をつくるような形だと感じたんです。
でも、最初、宣伝部は僕が何を言っているのか分からなかったようです(笑)。
聞き手
感性的な表現ですからね(笑)。
浅田
「僕はそういうふうにアド(アドバタイジング)を作りたい」とアピールして、最終的には、鳥の羽を1枚上から散らしてボールの中には卵がある・・・というイメージを提案しました。
すると、エルサたちが面白いと言ってくれたのです。それがティファニーでやった最初のアドでした。
聞き手
そのアイデアはそのまますんなりと通ったのですか。
浅田
その場では採用されましたが、今度は彼女たちが社内にプレゼンしなければならないわけです。
そこにはもう僕は入っていけない。
結局、エルサだけでなくパロマも手掛けるようになりました。
同じティファニーでも、パロマとエルサの雰囲気は全く違うものでした。
でも、僕にとっては二人のデザイナーの作品の違いはあっても、それぞれの個性と僕の感覚の共通点を探しながら仕事をしました。
それは、他のクライアントの仕事も同じ事が言えると思います。
クライアントには職種もいろいろあり、会社の規模の差もありますが、アサダデザインにとっては、デザイン事務所の隣のパン屋さんの仕事も大企業の仕事も同等です。
仕事に大小はあっても、作る一つ一つのものは、クライアントと僕との合作なんですよね。

在るがままの自分をキープしておく
聞き手
そこで浅田さんが自分を抑えるということはなかったのですか。
浅田
僕の役割はアートデレクションでしたから、クライアントの思いと僕の考え(アートデレクション)が一緒になって始めて仕事になるんですが、多くのクライアントからは、僕にすきなようにやらせてくれました。
それはクライアントが僕がどう思うか、どう作るかを、見たかったのでしょう。
で、それが長年のあいだに僕が持っている感性から生まれたエナジーみたいなものが形になったのでしょう。
聞き手
その作業は、後輩のクリエイターたちに伝えるとすればどういう言葉になりますか。
浅田
自分の中にあるものを掘り出す作業ですね。
聞き手
掘り出すために日頃から心掛けるべきことってありますよね。
浅田
それはやはり、在るがままの自分をキープしておくことでしょうね。新しい別の自分をつくるのではなくて、ずっと在る自分でいることが一番大切です。
そうしないとどこかに持っていかれてしまう。
当然ながら人は変わっていきますが、そのときそのときの自分に忠実に向き合うことです。
子どものころの話ではありませんが(前編参照)、丸い石の中にも宇宙があって、僕はその宇宙の中で、これが僕なんだという形や色、質感をいつも探しているのかもしれないですね。
聞き手
だから、チャンス(機会)があったときに自信を持って臨めるのでしょうね。
浅田
結局、僕一人しかいませんから、自分が責任を負わなければならないんです。
聞き手
ティファニーのクリエイティブで気をつけていたことは何ですか。
浅田
もちろん、ビジネスではあるのですが、ティファニーのロゴが入るアドの中に、あるいはパンフレットの中に、僕をどういうふうにして入れるかということの方が、ティファニーだからどうというよりももっと大切でした。
聞き手
なるほど。それが結果的にティファニーになるんですね。
浅田
そう。僕自身がティファニーの一部になり、僕の感性がティファニーのイメージになっていく。それは宇宙にあるようなもので、目で見えるものではないんです。
モノの本質を知ることから始まる
浅田
キャッツキルだけではまだニューヨークのにおいがするので、僕はワイオミングにもバケーションに行くんです。
で、1~2週間山の中にいて、牛や馬と生活をするわけです。
そこでは、全ての牛にブランドとしての焼印が押してある。
それは識別のためです。
「ブランド」の起源はそこから始まっていますよね。
しかし、今のブランドはロゴでもなく、色でもなく、ぜんぜん違う「生きもの」です。
それを知らないといいも悪いも全部持っていかれてしまう。
聞き手
ブランディングで大切なこととは何でしょうか。

浅田
どんなブランドでもまずモノを知らないと駄目です。
ブランドというよりモノとしての製品、道具としての製品を知らないと楽しみも何も生まれてこない。
それをもっとエンジョイすべきじゃないかなと思います。
例えば、Tシャツ1枚にしても、コットン100%、ウール100%、麻100%、絹100%といろいろな素材のものがあります。
少なくとも、100%というのは、どういう感触なのかを肌で感じたことがあるかどうかが重要です。
聞き手
ブランドが本質から離れて記号だけになってしまってはいけないということですね。
浅田
まず、Tシャツを着るシーンを考えた場合、どれが一番自分に合うかというのは、それを着るときの季節にもよるし、環境にもよる。
例えば、麻のシーツで寝たいというのは、麻のシーツとはどういうものか実際に裸で寝てその感触に触れないと分からないじゃないですか。
聞き手
体験しないと分かりませんよね。
浅田
それが最初に言った「ものの本質を知る」ということなのです。
そうするとブランドって一体何だということになる。
そんなものいらないんじゃないかということになる。
そういうところから入っていって、「ああ、やっぱりこの会社の製品はいいよね」と。
逆に言えば、「この製品を作る会社が出すものはいいよね」となる。
聞き手
それが結果的にブランドになるということですね。
日本の文化を表現したJALの仕事
聞き手
JAL(日本航空)の仕事にも深く携わっていますね。
浅田
僕が大学(多摩美美術大学グラフクイック科)を卒業する何年か前に、JALが初めてサンフランシスコに飛んだんです。
つまり、初めて日本からアメリカへ飛ぶルートができて、JALのアメリカ側のアドを作ったのがボツフォード・ケッチャムインターナショナルという会社でした。
僕はその会社の東京オフィスに入社したんです。
当時は、アメリカ人のアートディレクター、アメリカで教育を受けた日本人のアシスタント、アメリカ人のコピライター、アカウントマネジャー、プロダクションマネジャーという15人ぐらいの社員で、アメリカ人がほとんどの会社でした。
聞き手
JALというイメージもまだ何もないころですよね。
浅田
サービスとはどういうことかとか、そういうところから携わりました。
聞き手
JALの仕事はどこまでやられたのですか。
浅田
ボーイング747(米ボーイング社が開発した大型旅客機)をJALが購入した頃は、まだ日本にいて、747のカタログや、アジアで使われる英語版の広告を日本で作っていましたが、JALのアメリカ支社がニュヨークに移り、ニュヨーク線も開通し、広告代理店もニュヨークに移り、その頃私もニュヨークに転勤になりました。
ちょうど10年間お世話になりました。
ニュヨークに転勤してすぐの頃は、日本の文化、風習を伝えながら、アメリカ人が考えている歴史的な日本でなく、(1960?1970年代の日本)、特に東京を理解してもらうのには、結構苦労しましたね。
最後の頃は、アメリカだけでなく、ヨーロッパ、アジアで作られる英語版のキャンペーンのアートデレクションをしていました。
その度に、一ヶ月も東京に滞在した事も在りました。
JAL以外のクライアントの仕事では、日本人で在る自分はそんなに意識しなかったですね。
アメリカ人のアートデレクターとは、良い悪いは別として、けっこうユニークなアートデレクターだった様に思いますね。
聞き手
当時は夢があった時代で、スチュワーデスも非常に人気の高い職業でしたね。そういう時代にどのような苦労がありましたか。それともすんなりとブランディングができていったのでしょうか。
浅田
日本にいてアメリカに日本を紹介するのではなくて、アメリカにいて日本や日本文化を紹介するということは簡単なものではありませんでした。
お茶の文化ひとつをとっても、お点前だけではありませんから、どう伝えればいいかとても難しい。
ただ、日本航空というエアラインの中にアメリカンとははっきり違う世界がある。
それがJALなんだということを表現する仕事でした。
聞き手
日本人の浅田さんはアメリカのエージェンシーの中でどういう立場だったのですか。
浅田
JALの宣伝部の人たちとアメリカのエージェンシーの人たちの間に立ってコミュニケーションする立場でした。
「それは本当の日本じゃないよ」とかね。
例えば、コピーライターはカメラマンに、赤ちゃんを背中におぶってねんねこ(幼児を背負った上から羽織る広袖の綿入れはんてん)を着た女性の写真を要求するわけです。
でも、日本にはそういう光景はもう存在していない(笑)。
聞き手
なるほど(笑)。アメリカ側は勝手に日本をイメージしているわけですね。
浅田
アメリカ人は赤ちゃんを背負うことで両手が空いていろんな作業ができると機能的に捉えているわけです。
でもそれは現実の日本とは違う。
だから、そういうのを僕は僕自身のナチュラルな感性の中でジャッジしていたんです。
伝わる、伝わらない以前に、文化を紹介するというのはそんなに簡単なことではないですね。
聞き手
だから、海外に日本の焼き物を紹介する(前編参照)にしても、ただ展示会で並べても駄目だということなんですね。今日はとても楽しいお話をありがとうございました。
※掲載の記事は2015年7月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。