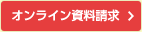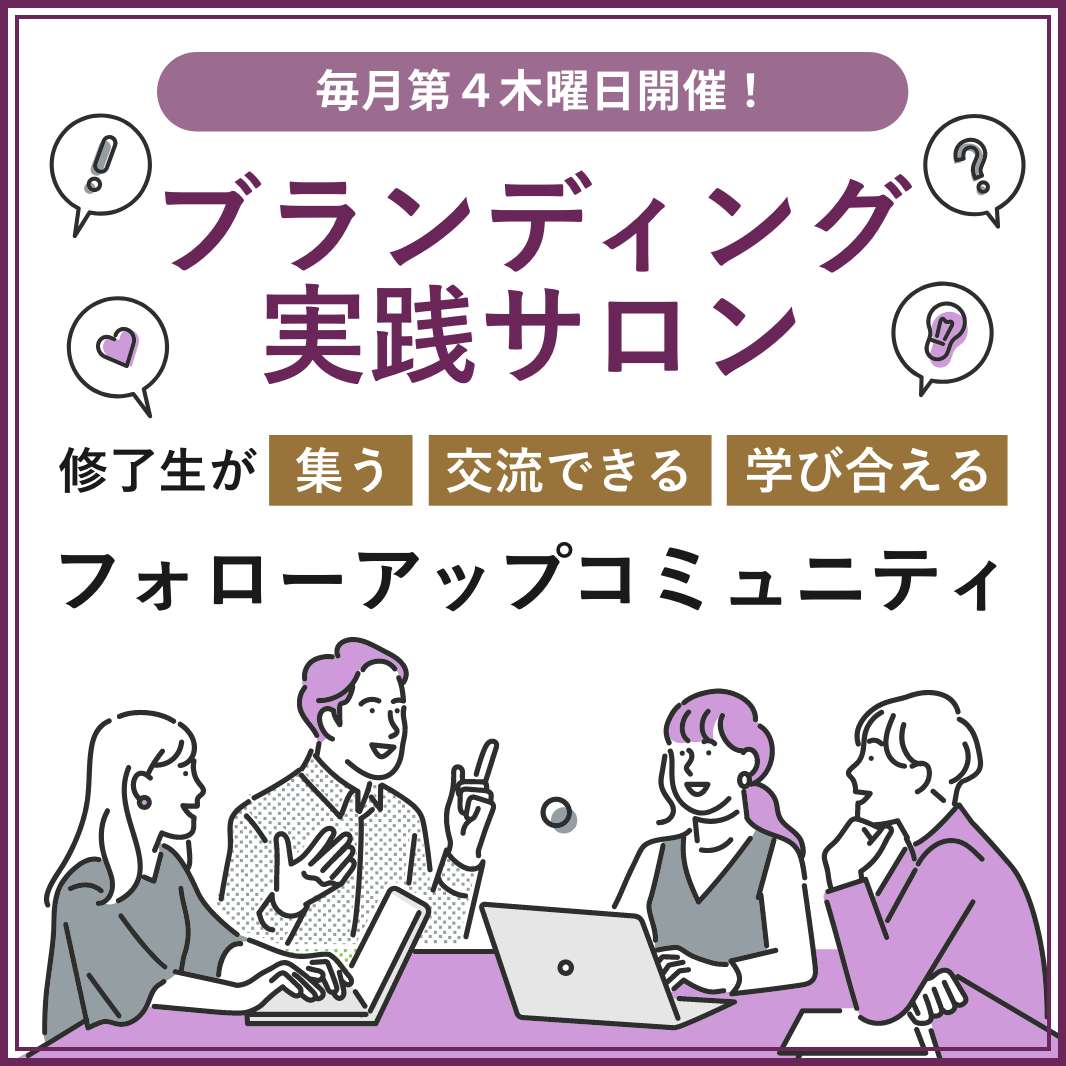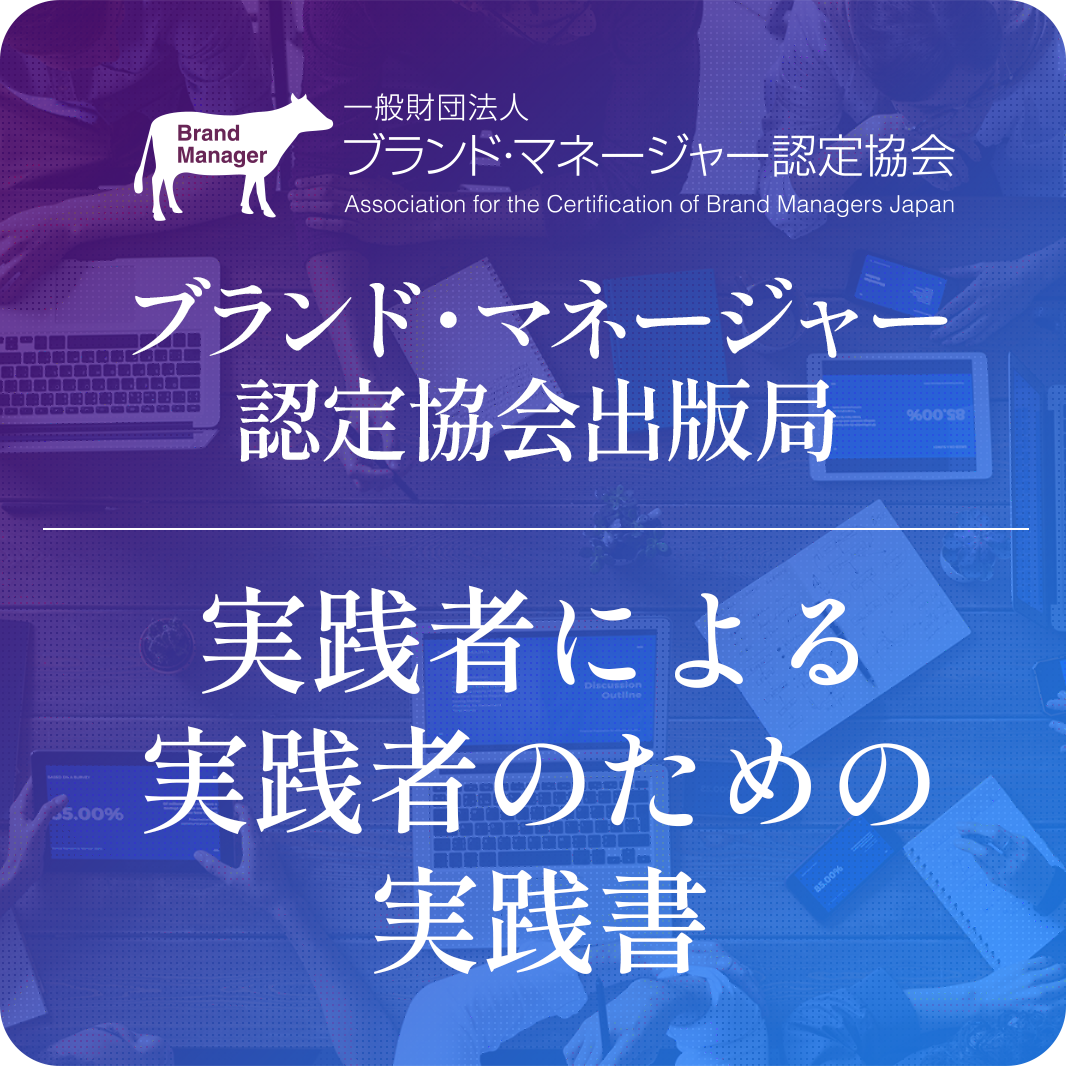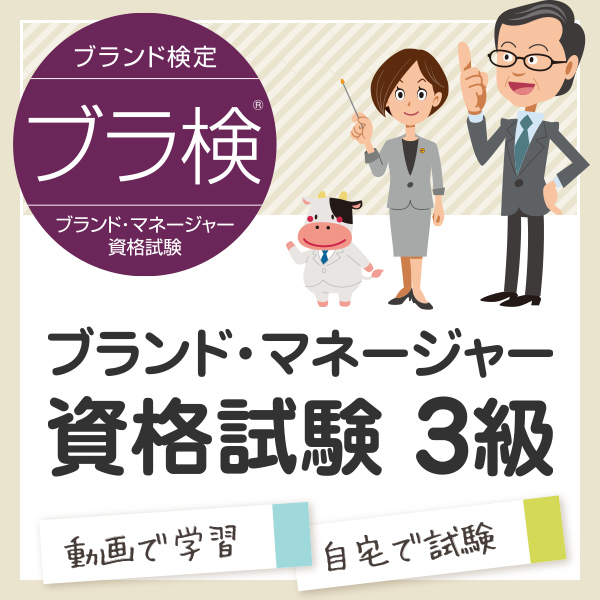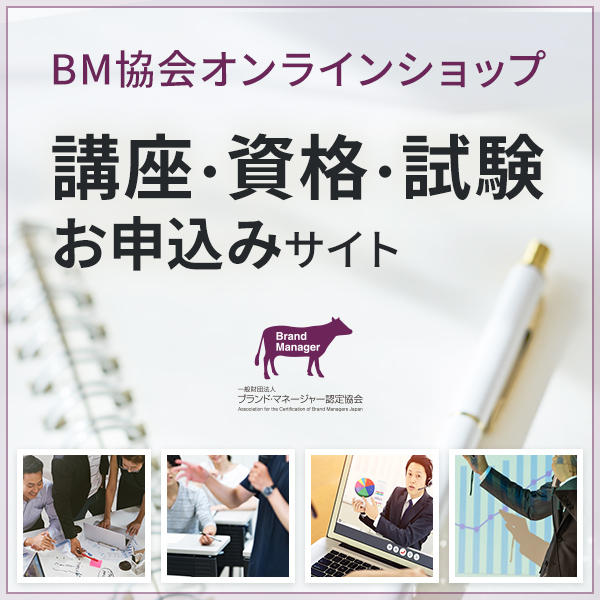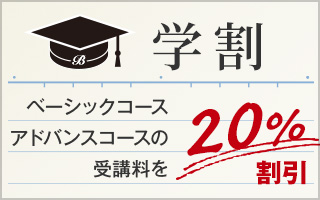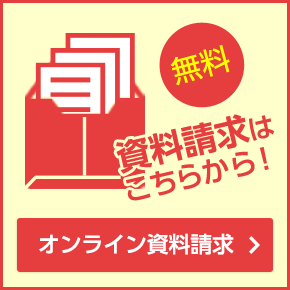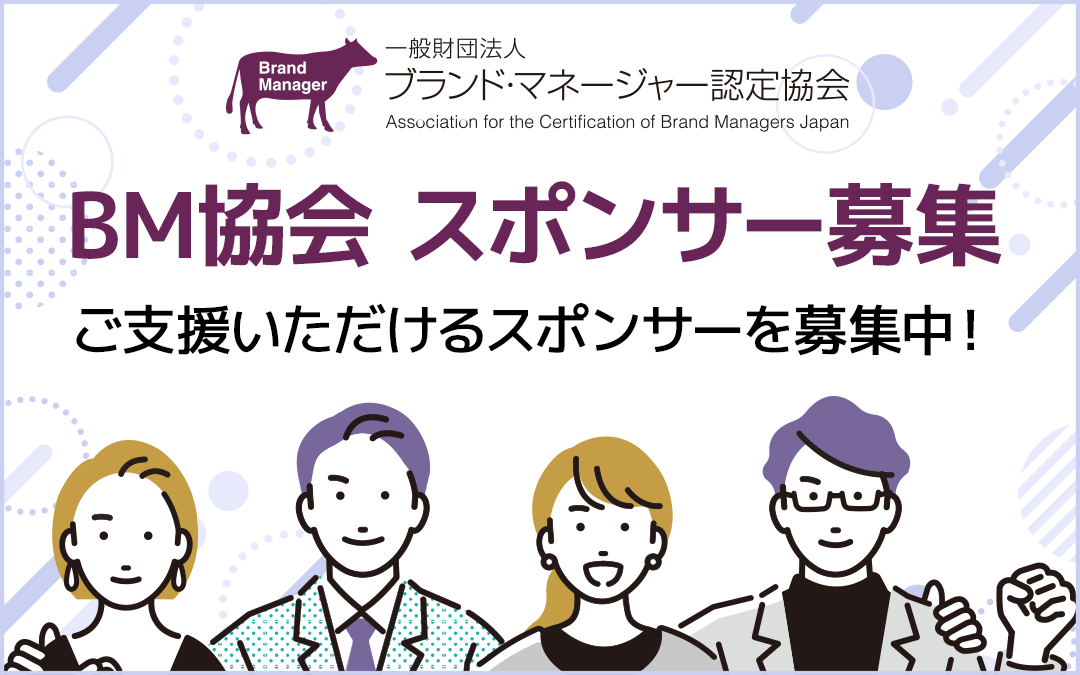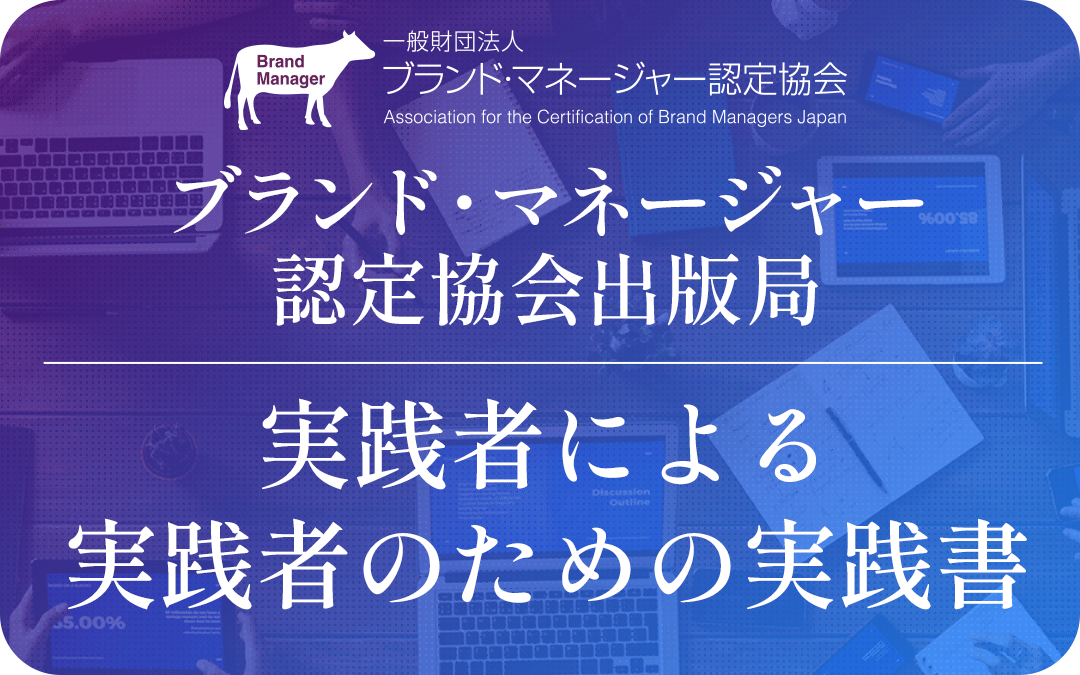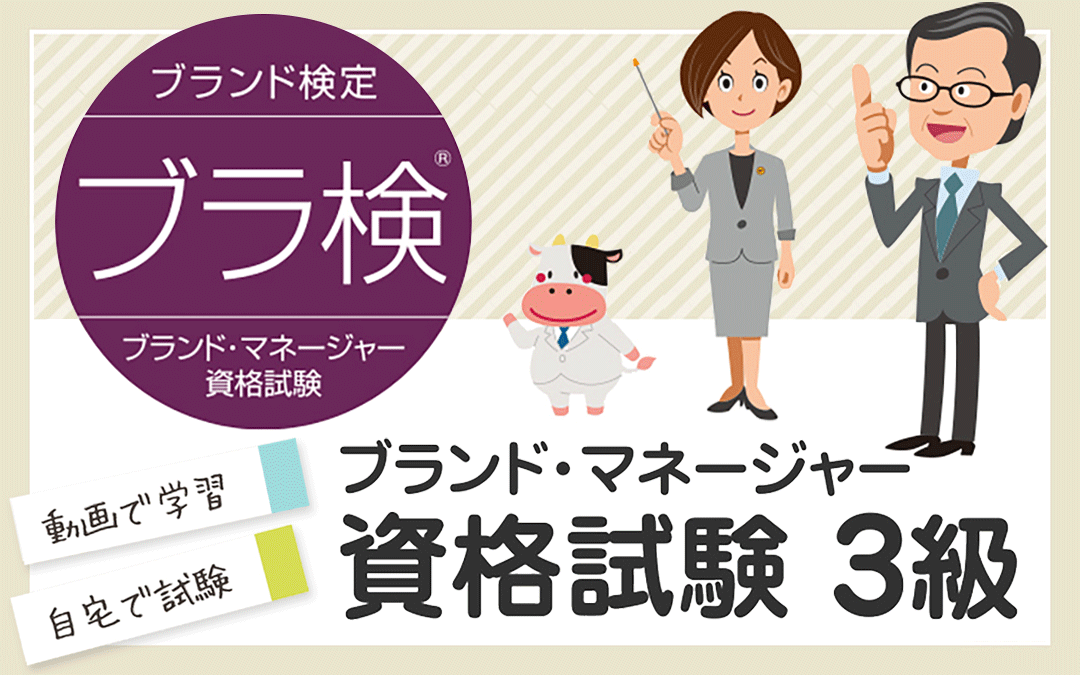ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >新谷 順子氏 Vol.2
ブランディングにおける<サブリーダー>の価値 – 後編
新谷 順子氏 Vol.2 ヨリタ歯科クリニック スマイルクリエータ―・感動クリエーター
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【新谷 順子氏のプロフィール】
ヨリタ歯科クリニック スマイルクリエーター・感動クリエーター
2004年、ヨリタ歯科クリニック入社。受付「スマイルクリエーター」助手、
「健康プロモーター」、医院ブランディング「感動クリエーター」、
人事採用、新人教育、イベント企画、新規医院事業などの業務を手掛け、メンバーと共に仕組みを構築。
現在も現場で働きながら、いかにスタッフと経営者が生き生きと輝くワクワク楽しい職場づくりができるかを追及、実践し続ける。
その成功例、失敗例すべてを包み隠さず、全国での講演にて発表。
「スタッフが主役になれる医院づくり」、
「チームワーク作り」、
「医院ブランディング」
などについて、歯科業界向けに講演するほか、企業向けには大手から中小企業まで、
「ワクワク楽しい職場づくり」
「サブリーダー論」
など講演を行う。
一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 ベーシックコース受講者<サブリーダー>としての考え方・取り組み
聞き手
新谷さんは、ご自身の役割を『サブリーダーシップ』であるとおっしゃっていますが、これはどういう能力なのでしょうか?
新谷
『リーダーの想いを形にする』というのが、サブリーダーの原点だと思います。いかにその組織のあるべき姿を追求して、それを見せていくかが大切です。
聞き手
リーダーの想いを引き出し、それを皆に伝えるという役割ですね。いろいろご苦労されていると思いますが、特に大変なところはありますか?
新谷
たくさんあります(笑)。たとえば院長は経営者であり、ここまでのことをやり遂げてきた人なので、社会人1年目の新人とは考え方などもまったくかけ離れています。共通の言語がないようなものです。ですから朝礼などで経営やビジョンの話をしても、新人には最初はなにを言っているのかわからない。言い続けているうちに、いつかはわかるときが来ますが、それまでの間はわかり合えていないわけです。その通じ合っていない期間に、新人は辞めたいと思ってしまうかもしれない。だから「院長はこういうことを言っていたんだよ」ということを、相手の目線や立場にあった形で、わかりやすく説明してあげるというのもサブリーダーの役目ですね。
聞き手
まさしく『翻訳者』ということですね。
新谷
そうです。相手に応じて伝え方を変えなくてはいけませんから、まずは相手がどういったものに興味を持っているのか、普段からとにかくコミュニケーションをとることから始めます。私生活の話とか、持ち物だとか、とにかくさまざまな方向から触れてみて、どこが相手の響くポイントなのかを引き出します。そうすることで、より相手の心に届く伝え方ができるのだと思います。こちらの意図が通じるかどうかで、相手のモチベーションを判断しがちですが、こちら側がその判断をしてしまった時点で、相手のモチベーションは絶対に上がりません。その思い込みを外して、相手の良さを引き出すことがサブリーダーの務めです。もちろん私もなかなか伝わらなくて、イライラすることはあります。ただ、イライラすることに時間を使うよりも、切り替えて前向きに時間を使おうとスイッチを切り替えるトレーニングをしてきました。また私がイライラしなくなったら、スタッフがどういうことにイライラするのかがわからなくなってしまいますから、イライラするのも必要なことだと思っています。

<人づくり>には時間がかかる
新谷
『クレドにはこう書いてあるから、あなたの行動は正しくありません』と注意しても相手には伝わりません。3年・5年たったとき、『クレドで言っていたことだな…』と本人が気づけば、それでいいと思いますね。
聞き手
子どもを教育しているような感じですね。
新谷
私自身もそうです。1年目は気づかなくて8年目でわかったクレドもありますし、7年前に外部セミナーで学んだことが、最近、ようやく理解できたこともあります。最初は自分の成長が追いついていないから、とにかくコピーしているのですが、そのうち自分の中で編集できるようになって、やっと自分の中に落とし込めるわけです。言われただけですぐわかることなんて、そんなにないと思います。
聞き手
なるほど。よく陥りがちな失敗ですが、経営者層・リーダー層は言ったとおりにすぐ変革したくて、一歩間違うと攻撃してしまったり、これで駄目なら…と、違う方針を出してしまうことがあります。そこは辛抱、ということですね。
新谷
経営者の方は数字を出さなければなりませんし、迷って当然だと思います。私は経営者ではないから、本当の意味での経営者の気持ちがわからない分、他にできることを探しているわけです。組織のイノベーションをしようと思ったら、長期的に見ないと強い体質の組織はできあがらないと思います。
聞き手
人の心はモノではありませんから、簡単には変わらないですよね。
新谷
人の心を変えられる魔法の薬みたいなものがあれば、私も欲しいです(笑)。
聞き手
まさにコツコツ伝え続けるしかない、ということですね。リーダーとサブリーダーでは、目線が違うと思いました。多分、私にはサブリーダーは務まりません(笑)。
新谷
岩本さんはミッショナーだから、良いと思いますよ。
聞き手
新谷さんがおっしゃるように、伝わらないことだらけです。だからそういう翻訳者が必要だということですね。ヨリタ歯科クリニックは、素晴らしい組織だと思います。
ブランドで大切なのは、やはり<人>
聞き手
最後に、新谷さんの考えられるヨリタ歯科クリニックにとっての『ブランディング』とはなんでしょうか?
新谷
ヨリタ歯科クリニックの文化風土に沿った『人づくり』ですね。
聞き手
『医院づくり』ではなくて、『人づくり』ですか。
新谷
見やすいホームページや快適な施設などは、お金をかければどこでもできることで、ここにしかないものは<人>です。内装にお金をかけて、受付を総合病院のようにカード式の自動精算にすればいいのかと言えば、そうではありません。当院の受付は4人いますが、患者様がお会計をしているときに、いつもと表情が違うなと思えば声をかけて、心配や不満を引き出そうとします。それがヨリタ歯科医院のブランド力で、これは<人>にしかできないことだと思います。
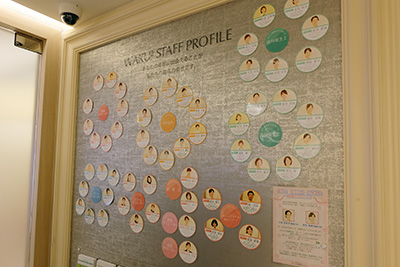
聞き手
とてもわかりやすいです。ヨリタ歯科クリニックの今後の姿、理想像はどんなものでしょうか?
新谷
そうですね……たとえば、院長が銅像になったとしても、ヨリタの文化というか、風土が根付いている組織づくりができればいいかなと思います。
聞き手
ヨリタらしい文化が生き続ける…理念が完全に浸透している状態ですね。
新谷
先日、その浸透を感じられて嬉しかったことがありました。当院には連絡用の通信インカムを充電する場所があって、つい機材を手前から置いてしまいがちなのですが、次の人のことを考えて奥から詰めて置いていく方がヨリタらしいですよね、というようなことをスタッフが言うわけです。こういう発言を耳にすると、浸透を感じて嬉しくなります。
聞き手
『ヨリタらしさ』という一言で表現できる凄さですね。『らしさ』というのは、とても曖昧な表現なのに、なにか統一感があると思います。
新谷
いつのまにか『ヨリタっぽい』とか『ヨリタらしさ』とか、『ヨリタマインド』という言葉を使い始めて、それが一人歩きするようになってブランドができあがってきたという印象があります。
聞き手
ちょっと硬い話になりますが、ブランドの価値には情緒的価値と機能的価値というのがあって、機能的価値とは時計であれば時を測るというような機能で、情緒的価値は新谷さんがおっしゃるような『らしさ』という世界観を作っていくところです。歯科医院においても、機能的価値は治療・予防と大事なことですが、それだけだと付加価値が付きません。そこを、<人>というテーマで情緒的価値を作ってらっしゃるのだな…と思いました。
新谷
まさに高級時計における、機能プラスαのような。
聞き手
そうです。だからこそ、高い金額になっても買われるわけですよね。選ぶ人は、そこまで考えていない場合もあるかもしれませんが、無意識で伝わっていると思います。<人>で情緒的価値を作る大切さは、サービス業全般に言えることですね。
新谷
歯科の技術は見えにくいものですから、いかに付加価値を<見える化>するかということも大切です。また、患者様が不安や緊張を持って来られるところですから、言葉遣いや表情なども、気をつけないといけません。
聞き手
まさにヨリタブランドは<人>でできている、ということですね。本日は貴重なお話を伺わせていただきまして、大変ありがとうございました。
※掲載の記事は2016年12月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。