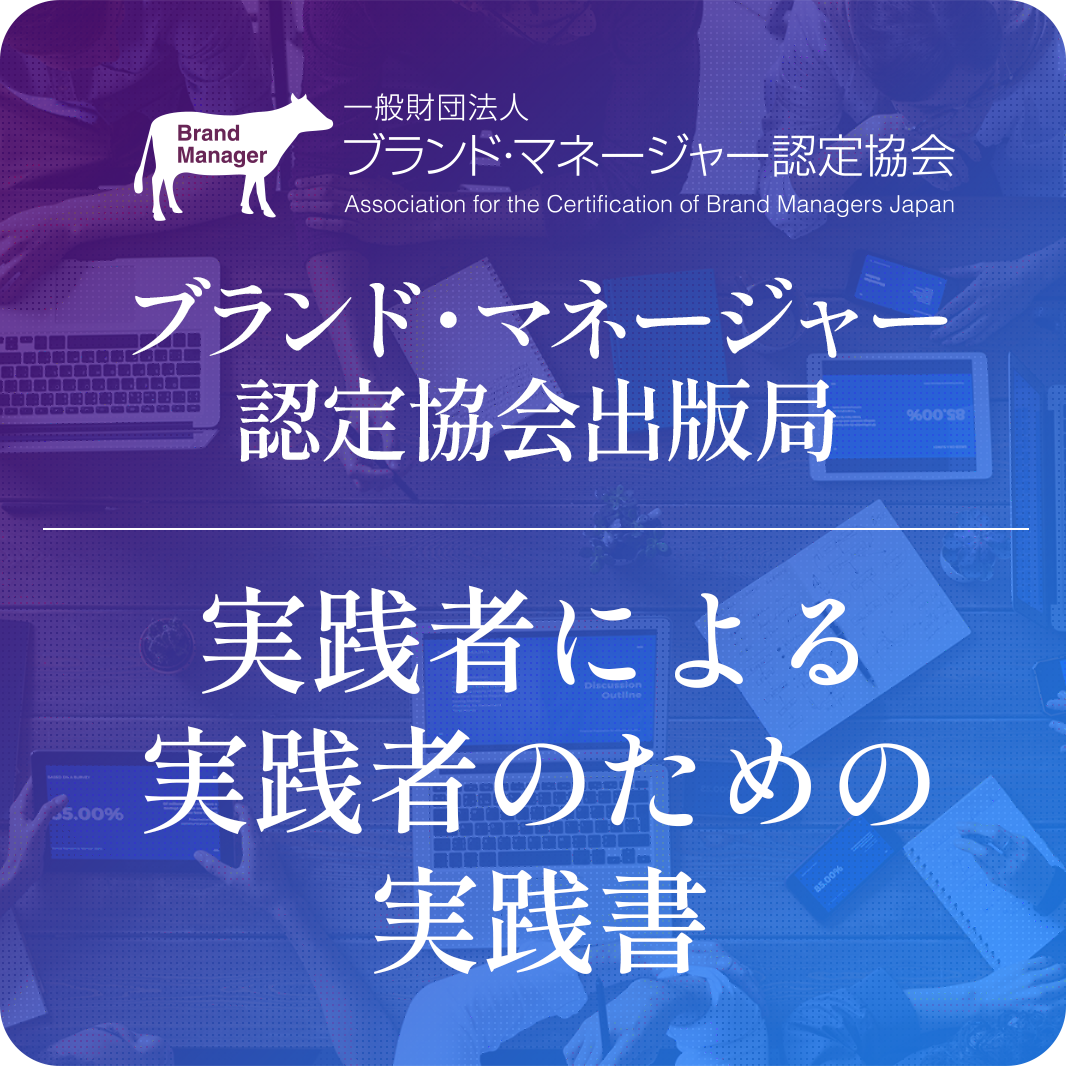ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >田中 洋氏 Vol.3
ブランドを組織の意思決定基準にする – 前編
田中 洋氏 Vol.3 中央大学ビジネススクール(大学院戦略経営研究科) 教授 一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 特別顧問
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【田中氏のプロフィール】
経済学博士(京都大学)。
(株)電通マーケティング ディレクター、法政大学経営学部教授、
コロンビア大学客員研究員などを経て2008年より現職。
一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会顧問。
日本マーケティング学会副会長。
Hiroshi Tanaka Official Site
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/cbs/index_j.html
ブランドを組織の意志決定基準にする
聞き手
さきごろブランド・マネージャー認定協会が主催した公開シンポジウムで「インナーブランディング」をテーマに取り上げましたが、まず田中先生のご感想からお伺いしたのですが。
田中
桂川レディースクリニック(LC)の活動が非常に印象に残っています。
一つは、実際に成果に結びついているということですね。
もちろん、ファシリテーターの技量もさることながら、もともと現場が抱えていた組織的な問題がクリアに解決されたというところに、シンポジウムに参加された皆さんは感銘を受けたというのだと思います。
組織の問題を単なる「小集団活動」で解決したということではなく、ブランディングを通して問題解決を図ったことが新しいし、意味がありました。
聞き手
ブランディングで組織を強くする手法はこれまでもあったのですか。
田中
ブランドという概念を使わない小集団活動は、昔から日本の企業にはよくありましたが、インナーブランディングのような考え方を使って組織を引きしめるとか、組織を一つの方向に向かわせようという活動もあるにはあったのです。
例えば、P&GのCEO(最高経営責任者)を務めたA.G.ラフリーは、「コンシューマー・イズ・ボス(消費者がボスだ)」という考え方をずっと社員に唱えていました。
彼は2000年から2010年まで、10年近くP&GのCEOを務め、会社を立て直した立役者です。
これなどはインナーブランディングそのものとは言えませんが、それに近い考え方の成功例だと言えます。
聞き手
会社の考え方の軸を明確にしたわけですね。

田中
もう一つ有名なのが、ジョンソン&ジョンソンの「クレド(信条)」です。このクレドも一種のインナーブランディング活動だと言えるでしょう。
「コンシューマー・イズ・ボス」も「クレド」も、社内の意志決定の基準に使うことを目指したものであることがポイントです。
私も以前から、ブランドは社内の意志決定の基準として使うべきであるという考え方を持っています。
社内の意志決定規準はさまざまです。その会社に昔から引き継がれてきた伝統や家訓で判断する企業もあれば、いろいろなマーケティングデータをベースにして判断する会社もあります。
今回、シンポジウムで発表された桂川LCは、組織を構成するメンバーが仕事に対する考え方の規準をブランドに持ってきた、という点に新しさを感じます。
しかも、それが大企業ではなくて非常に小さな組織で実行したということに意味があると思います。
聞き手
組織の意志決定にいろいろなものがある中で、ブランドを意志決定の規準にもってくるメリットとは何でしょうか。
田中
そもそもサービスのブランド化とは、「お客さまにこういうふうに見せたい(思われたい)ので、それを規準にして私たちはこう振る舞いましょう」という決め事のようなものです。
外のことを考えずに会社の中だけでそれを言うよりも、やはり外を意識してこうしようという方が組織に対してはインパクトがあります。
もちろん、その考え方も特別新しいものではなくて、1980年代のCI(コーポレート・アイデンティティ)のころからあったものです。しかし、うまくいきませんでした。
そもそも、ブランドを意志決定の規準にしなければいけないといのは、何か組織が抱えている問題を解決したいという動機付けに裏打ちされていなければいけないと思うんです。
それに対して、CIに着手したころの日本の企業は、問題意識が希薄だったのではないかと思います。
だから、社名を変えたり、ミッションステートメントを新しくしたり、社旗を作り変えたり、社歌を作ったりしました。あまりにもいろいろ変えてしまったために、CIを行った結果、企業のアイデンティティがはっきりしなくなった、という悲劇も起こったほどです(笑)。
しかし、何を解決しなければならないのか、またそれをどう解決するのかという問題意識が希薄だったために、CIが根付くことはありませんでした。
90年代にバブルが崩壊した後、CI運動は急速にしぼんでいったのはそういう理由があったからです。
本当は、会社が問題を抱えているときにこそ、CIは有効であるはずだったのですが、実際に危機になったときは、それがまったくワークしなかった。
今思えば、80年代のCI運動というのは非常に空疎なものだったなと感じます。
聞き手
なるほど。今回発表した桂川LCがチームブランディング(チームビルディングとブランディングを合わせた造語)に着手した背景には、組織がバラバラという問題が存在していました。
田中
桂川LCは産科チームと不妊チームという似ているようで性質のまったく異なる2つの組織を抱えていて、その間に一種の壁が存在していました。
その壁を取り払わなければならないという非常に明確な目標がありました。
その壁を取り払うためにブランドという概念を使った。
しかも、ファシリテーターが、クラブ活動のように楽しくやる工夫を凝らしながらブランディングを進める中で、その壁をうまく壊すことができました。
その点を非常に興味深く感じました。
聞き手
さきほど、先生は「80年代は問題意識が希薄だった」と言われましたが、それが現代は顕在化されているということでしょうね。
ブランドは危機の産物である
田中
ブランドで問題解決を図るときには、何のためにブランドの概念を使うのかということを、どんな場合でも意識していなければなりません。それはチームブランディングでも、商品ブランドや企業ブランドの場合でも同じです。
「ブランドを強くしたい」とか、「ブランドの価値を高めてお客さまをもっと引きつけたい」とか言う人はたくさんいるのですが、その程度の問題意識ではたぶん継続できないと思います。

聞き手
田中先生は、「ブランドは危機の産物である」とおっしゃっていますね。
田中
例えば、危機が顕在化したときに、ブランドをよく分かっているリーダーがブランド活動をやるとうまくいくでしょう。
しかし、企業が割とうまくいっているときに、周りの企業がやっているからうちもなんとなくやってみようと思ってやってもうまくいきません。
逆に言うと、危機に陥っているときほど、ブランド活動をやった方がいいんです。
例えば、今の電機メーカーですね。
たぶん、営業状況が悪いときのブランド活動こそ、本当は経営の手法として生きるんです。
しかし、日本の経営者はブランドの知識が頭の中に入っていないから、考えることは同じで、事業売却とかM&A(買収・合併)とかリストラとかマイナスの方向に行ってしまう。
電機メーカーのように問題を抱えている今こそ、ブランド活動に注力すべきだと思います。
実際、欧米の企業がブランドに真剣な関心をもったのは、80年代の末のことで、米国式経営はもうダメではないか、と思われ危機に陥っていたころです。
同じ80年代末、日本企業はジャパンアズナンバーワンという標語に酔いしれて浮かれていたのです。
聞き手
大手メーカーはなかなかそこまでの意識にまでいっていないのが現実ですね。
田中
実は、シンポジウムの後に、桂川LCの院長にも話をお聞きしたのですが、やはりかなり問題意識を明確に持っておられて、チームブランディングによって組織を立て直そうと考えられたのは、非常に的確な判断だったと思いました。
聞き手
ブランドセッションのときに、田中先生は日産自動車のカルロス・ゴーン氏の例を出されましたが、あれは会社が危機のときに、日本人ではないCEOに代わって、まさに会社が変われる条件が整ったということだったのでしょうか。
田中
そのとおりです。
ゴーン氏はルノー社の人ですが、日本に来る前、タイヤのミシュランの北米CEOも務めた人です。
そういうところで社内のブランド活動が有効だということを実際に体験していたのです。
ですが、日本のCEOはそういう経験を積む人が少ないんです。
経営者の教養科目の中に必須項目として、ぜひ「ブランディング」を入れていただきたいですね。
経営の一つのスキルとしてブランドがあるということを経営者には分かってもらいたいと痛切に思います。
聞き手
話は戻りますが、そもそも80年代に、日本の企業の間にCIが流行った理由は何だったのでしょうか。
田中
このあたりは前回のインタビューでもお話したことになりますが、80年代は多くの企業が業務の多角化を推進していました。
それが結果的にCIの大きなモチベーションになったのです。
どの企業も景気がいいときは経営の多角化をしようとするし、それが当時は経営の定石だったんですね。
当時の多くの日本企業は「総合化」を志向しており、総合化すれば経営はより安定するだろうと考えていたのです。
そうすると、本業が不明確になって、自分がどのような企業であるかわからなくなってきます。
そこで、あちこちの企業がCIを確立しようとやっきになったのです。
CIに熱心であったもうひとつの理由は、それまで日本の会社が持っていた戦後からの社名や企業ロゴが古びて見えたことです。
公共事業体である電力会社やガス会社までもがCIで衣替えしたりして、CIは非常にブームになりました。
聞き手
そう捉えると、CIは70年代からありましたね。
田中
ええ、そのころのCIはデザイン的な美意識が重視されていました。
会社の認知度を効率的に上げる活動も70年代から盛んになっています。
いずれにしても、前述したように70年代、80年代のCIはファッションのようなもので、もともとの問題意識が非常に希薄だった。
ですから、CIをやっていても本当は何がしたいのか誰も分かっていなかったと思います。
聞き手
そもそも、CIとコーポレート・ブランディングとは何が違うのでしょうか。
田中
80年代当時は、ブランディングという言葉はほとんど使われていませんでした。
CIをやって企業ロゴやマークを変えようという動きでしたが、ブランディングという意識はまったくなかったと思います。
ブランド・マネジメントが盛んに言われ始めたのは90年代に入ってからで、80年代末期までブランド構築という概念はほとんど存在していませんでした。
つまり、ブランディングの理論や支柱になるものがなかったのです。
90年代になると、ブランディングのセオリーがかなり出てきます。
そこから考えると、岩本さんたちが推進している「チームブランディング」は支柱となるセオリーをもっと作られてもいいと思いますよ。

聞き手
80年代に流行ったCIがバブルが崩壊で沈静化し、そこからブランド戦略が体系化された。
それが15~20年を経て、企業の問題意識が高まってきて、そして今、チームブランディングやインナーブランディングが必要とされる時代に来た。
というふうに実感しています。
特に中小企業の場合は、トップがそれにきちんとコミットした上で、再現性のあるブランド構築のプロセスを用意すれば、全ての業種業態にこのチームブランディングのノウハウが応用できるのではないかと確信しています。
組織の内部からブランドが出来上がっていくようなロジックはこれまでなかったのですか?
田中
例えばアメリカでいえばGE(ゼネラル・エレクトリック)社がやっていた「シックス・シグマ」による品質管理手法、日本企業でもZD運動(ゼロディフェクト運動=欠陥をなくす)的な、どちらかというとものづくりの現場で展開された運動はいくつかありました。
しかし、医院やサービス業の現場で、インナーブランディングに関する理論に裏打ちされた活動は、これまでなかったと思います。
※掲載の記事は2015年12月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。