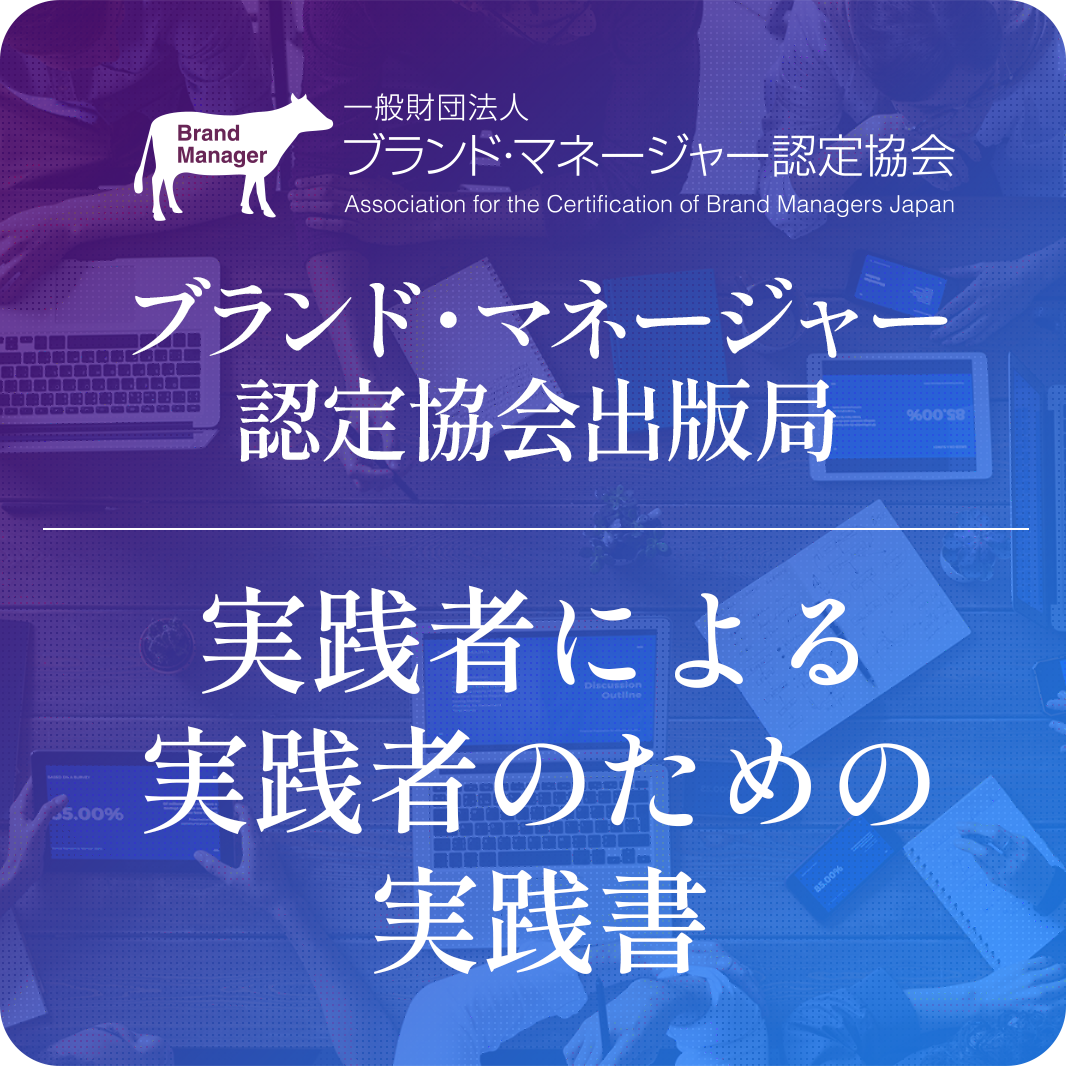ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >田中 洋氏 Vol.2
サッチャリズムがブランドの認識を変えた!? – 後編
田中 洋氏 一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 特別顧問 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【田中氏のプロフィール】
京都大学博士(経済学)。
(株)電通マーケティング ディレクター、法政大学経営学部教授コロンビア大学客員研究員などを経て2008年より現職。
主著に『大逆転のブランディング』(講談社)、『消費者行動論体系』(中央経済社)、『欲望解剖』(茂木健一郎との共著、幻冬社)、『企業を高めるブランド戦略』(講談社現代新書)、『現代広告論(新版)』(共著、有斐閣)、『広告心理』(共著、2007、電通)など。
その著作により日本広告学会賞を3度、中央大学学術奨励賞などを受賞している。
コーポレート・ブランディングから多角的CIへ
聞き手
1980年代の話をされましたが、田中先生ご自身がブランド戦略とブランド・マネージメント、ブランドとは何ぞやと思ったのは、その頃ですか?
田中
思ったのは80年代です。外資系の奴らと付き合っていて、日本では誰もそんなことを言ってなかったけれど、外資系の奴は例外なくブランド・エクィティ戦略を普通に考えていたので、「何じゃ、これは?」と思ったのです。
聞き手
それで研究を始められたんですか?
田中
これは研究の価値があると思いました。だけど、やると大変なことになるだろうと。その当時、分かっていた人はみんなそう思っていたと思います。
聞き手
そうすると何やかやで、もう20年ちょっと経ちますね。
田中
そういうことになります。
聞き手
話は変わりますが、私の中でちょっと今は区別がつかないのですが、コーポレート・ブランディングとCIというのはすごく近いのではないかと思うんです。動かし方とか根本の考え方は違いますが、その辺りの見解を聞かせていただけますか?
田中
CIが盛んだったのは、90年代はもちろんありましたが、やはり80年代でしょうか。一方、CIという考え方自体は実は70年代からあったのです。その先駆けになったのは、例えばIBMとか、日本ではミノルタとかが最初ですが、その火がついたのは80年代の前半、83、4年以降だと思います。
聞き手
そうですよね。
田中
その時といまと何が違うかというと、会社に対する、下の図でいうと一番下の経営戦略のところが現在とはそもそも違っていたと思います。一番の違いは何かというと、80年代はカネボウの伊藤さんが考えたペンタゴン(五角形)の経営スタイルに象徴されるところがあります。つまり繊維のみならず、日用雑貨、化粧品、食品、あらゆるところに進出するというヤミクモな多角化です。
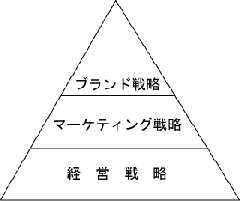
聞き手
あちこちに多角化したんでしたね。
田中
そうです。やたらめったら多角化してしまったので、企業の姿がよく分からなくなってしまったというのが根本にあります。その頃、日本企業は急速に成長していたので、一種のコングロマリットというか、いろいろな業種、業態を抱え込んでいきました。あのころサントリーでも日本航空でもセゾングループでも、みんな自分の会社は何かといったら「総合生活産業」というコンセプトでくくっていたのです。
聞き手
そうかもしれないですね。
田中
みんな同じことを言っていました(笑)。
聞き手
そういう意味では差別化されてないですね。
田中
みんな同じように、いろいろな業態の奴を抱え込んでいって、グループになっていって、バブルがはじけた時のクラッシュでそういうグループが一気にダメになってしまいました。90年代の不況期にはCIが後退したと思いますが、2000年代後半にまた持ち直して、いまはまたCIのプチブームなのです。なぜかというと、1つはCIをやった時からだいたい20年経っているからですね。20年くらい経つと、またどう変えようかとなりますので。ペプシコーラなどがそうです。
聞き手
たいていそういうふうになりますよね。
田中
そういう時期的な、車でいうと買い換えの時期みたいなものが来ているということが1つ。もう1つは、企業の姿も変わっています。例えば富士フイルムがそうです。昔は「富士写真フイルム」と言っていましたが、「写真」を取ってしまって「富士フイルム」になりました。新しい多角化ですよね。昔の多角化はどちらかというとコアがなかったのですが、いまはどちらかというとコアを据えて、それを軸に多角化するというふうに、もうちょっと全体が統合されたような多角化路線に来ています。そこが一番違っていると思います。80年代のころのCIは無定見な、とにかく広げればいいという感じだったような気がしますね。
聞き手
新しいことをどんどんやるみたいなことを。
田中
事業がダメになった時でも、いまいろいろなことをやっていけば、何とかなるよと。当時は成功した、ある程度うまくいった時代だったので。
聞き手
成功の確率も高かったでしょうし。
田中
ええ、日本も良かったのです。いまはそこをもうちょっと戦略的にやっていこうというふうになっています。多角化をもちろんしていますが、昔みたいにコア事業への、よく言う選択と集中という奴をやっている。そこが一番違うと思います。

イノベーションを繰り返し守られている「暖簾」
聞き手
話は変わりますが、日本企業にブランドの概念が入ってきたのは、もちろんヨーロッパなどと比べるとずっと遅いですよね。コア・コンピタンス的なこととか、リエンジニアリングとか、いろいろな戦略論が、欧米に影響されて日本ではちょっと遅れて流行るように言うではないですか。でも一方で、何かで聞いたのですが、創業200年以上の会社が日本には3,100社あるそうで、その日本にある創業200年以上の会社は世界全体の総数の40%らしいのです。例えば私がパッと思いつくのは、虎屋ですね。あそこはたぶん500年ぐらいだと思いますが、あそこの品質管理はすごく徹底されています。あと、日本では暖簾とかそういう考え方もあって、漠然とはしていますが長く継続していますし、ブランドという感覚的なものをすごく大事にしてきたように思います。ブランド・マネージメントという理論まではしっかりされていなくても、そういう文化みたいなものは日本にあるような気がします。その辺りについて田中先生の見解をお聞かせください。それはなぜだろう、とか。
田中
ロングライフを持ったブランドですね。たしかに古い企業はあります。一番古いところは金剛組。
聞き手
そうそう、お寺の建築の。
田中
578年創業ですから、1400年くらい持続したブランドとは言える。2005年にいったん破綻していますが。金剛組は寺社建築を主に手がけてきました。つまり、時代の変化をあまり受けないような産業の領域をやってきたところは長く生き延びるということがあります。ITなどはそういうわけにいきません。もう1つ、長く続いているようだけど、その中では結構変わっているわけです。どこかで体質をゴロっと変えてしまうような、一種のイノベーションや飛躍が起こっていると思います。ミツカンもそうです。あそこも200年以上会社が続いています。もちろんブランドを大事にしたと言えばそうなのかもしれませんが、途中のイノベーションが大きいのです。ミツカンですと何が一番大きなイノベーションだったか。戦後、お酢の売り方を変えたのです。どう変えたか。昔は樽とかそういう単位で売っていたやつを瓶詰めにした。瓶にして、小分けにして、それを小売店に持っていった。その小売店も伝統的な酒販店とかお酒の小売店ではなくて、スーパーマーケットのような後に急成長した流通経路に流すということを先駆的にやったのです。これはいまでもインパクトがあります。それを先にやったゆえに、地方の小規模のお酢屋さんはほとんど滅びてしまって残っていません。だから、いま7割ぐらいのシェアだと思います。これが1つの典型的な例です。暖簾をちゃんと守ったからですよと言えばそうですが、それは本当の答えになってないと思います。
聞き手
それなりにきちっとイノベーションを起こしながら、時代の変化に合わせて変えていっている。そういう企業が日本には40%ある。ということは、もちろん一方では金剛組のようにずっと生き残れる、変えないでもいい理由もあったでしょうが、イノベーションをやっていった企業が割とあるということになりますか?
田中
僕はそう思います。
トップのブランドに対する無理解をどう克服するか
聞き手
ところで、田中先生はプロダクト・マネージャーや、ブランド・マネージャーの方々といろいろご交流されているかと思います。皆さん、どんなことに悩んでいらっしゃるのか、聞いたことはありますか? また、企業の中でいろいろ苦労されていることでも、何か共通している事項がありますか。
田中
共通してあることの1つは何かというと、トップの無理解です。トップの人がブランドに理解を示さないので、どうしたらいいでしょうというのは割と多い相談の1つです。
聞き手
そういう時はどうお答えになりますか?
田中
それが一番難しいことです。私ごときが社長のところに乗り込んでいって、じゃ、社長が変わるかといったら、変わるわけがないのです。具体的な説得の仕方を伝授したりしますが、それにしても非常に難しい話です。トップになる奴というのは、だいたい人の話を聞きません(笑)。これは僕が言ったのではなくて、デビッド・アーカー先生が言っていました。私がアーカーさんを90年代にある企業に連れていった時、当時の社長はブランドのことは全く理解などしようもないわけで、全然関係ない話をしているわけです。それで終わった後、アーカーさんに「社長はあなたの話を全然聞いてなかったよね」と言ったら、「いや、たいていトップの人は私の話など聞いてないものだよ」って(笑)。これは世の中、どこにでもある現象だと思います。
聞き手
悩みの相談みたいなものがあった時、ここをこういうふうに啓蒙したほうがいいのではないかとか、具体的にご指導をされたりしますか?
田中
アメリカだったら自分が会社を辞めるというやり方があります。これはつい最近ありました。僕の友達で、昔、ケロッグとかマクドナルドにいた優秀なマーケティング畑の人が、シカゴの交通システムの会社に就職しました。そこにマーケティングのチーフ・マーケティング・オフィサー(以後、CMO)として雇われたのです。そこは地下鉄とか交通システムのオペレーションをやっている会社でして、会社というより公社と言ったほうがいいかもしれません。そんなところでなぜCMOとかブランドが大事かというと、毎日毎日、地下鉄を使っている人がわれわれの本当のお客さんではないか。その人たちに対してわれわれはどう思っているか、どう思われているか。従業員はどう働かなければいけないか。そういうことを考えるのが大事だということを前のCEOが考えて彼を雇ったのですが、上が代わってしまったわけです。代わった新しいCEOはまったく理解がない。それで彼は辞めてしまいました。ですから、1つのやり方としては自分が辞める。もう1つの考え方として、社長に対して啓発するというのがあると思います。啓発するために何が説得材料になるかというと、「儲かりまっせ」と言うのがいいわけです(笑)。
聞き手
それは効きそうですね(笑)。
田中
それからもう1つは、有名な経営者の例を持ってくる。
聞き手
成功事例みたいな感じですね。
田中
そうです。「有名な、あなたも知っているこの経営者はブランドのことを言っていた、考えていたのですよ」と説得の材料として持ってくるのがいいのではないか。ただ、それで成功するかどうかは私にはよく分かりませんが。
聞き手
優秀な方々に共通するマーケティング・マネージャー、もしくはブランド・マネージャーの資質みたいなものを先生はどう捉えていますか。例えば、忍耐強いとか。
田中
僕はあんまり資質というふうには考えたことがないので分からないのですが、根っこはマーケティングが好きというのが一番大事ではないかと思います。マーケティングという職業が好きで、自分がプロフェッショナルとしてやっていきたいという心意気みたいなものがあるかどうかではないですか。
聞き手
ある方が、その商品を徹底的に好きになることだと仰っていましたが、それに近いですか。
田中
近いかもしれないけれど、僕は商品を個人的に好きになる必要はないと思います。むしろそこはクールヘッドでいたほうがいい。例えば車を扱っている人などによくそういう人がいます。車がすごく好きな人は、いまなぜインサイトやプリウスが大衆に売れるのかということが分からなかったりする。自分の趣味に走るという意味で分からない人が多いのです。ですから、自分自身がそうある必要があるかというと、別にそんな必要はないのではないかぐらいにしか思っていません。
聞き手
むしろ客観的にとらえた方がいいということですね。
田中
そうそう。その方がよいのではないですか。
聞き手
中小企業の町の社長が、自分のところの商品がやたら好きになってくると、消費者の顔が見えなくなったりするとか、そういう感じなのでしょうか。
田中
もちろんそれに対して情熱を持つのは必要ですから、そこはちょっと微妙なところがありますが、どこかでクールヘッドを持っていたほうがいいと思います。
聞き手
共通の何かがあるかもしれないですね。ありがとうございました。
※掲載の記事は2014年8月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。