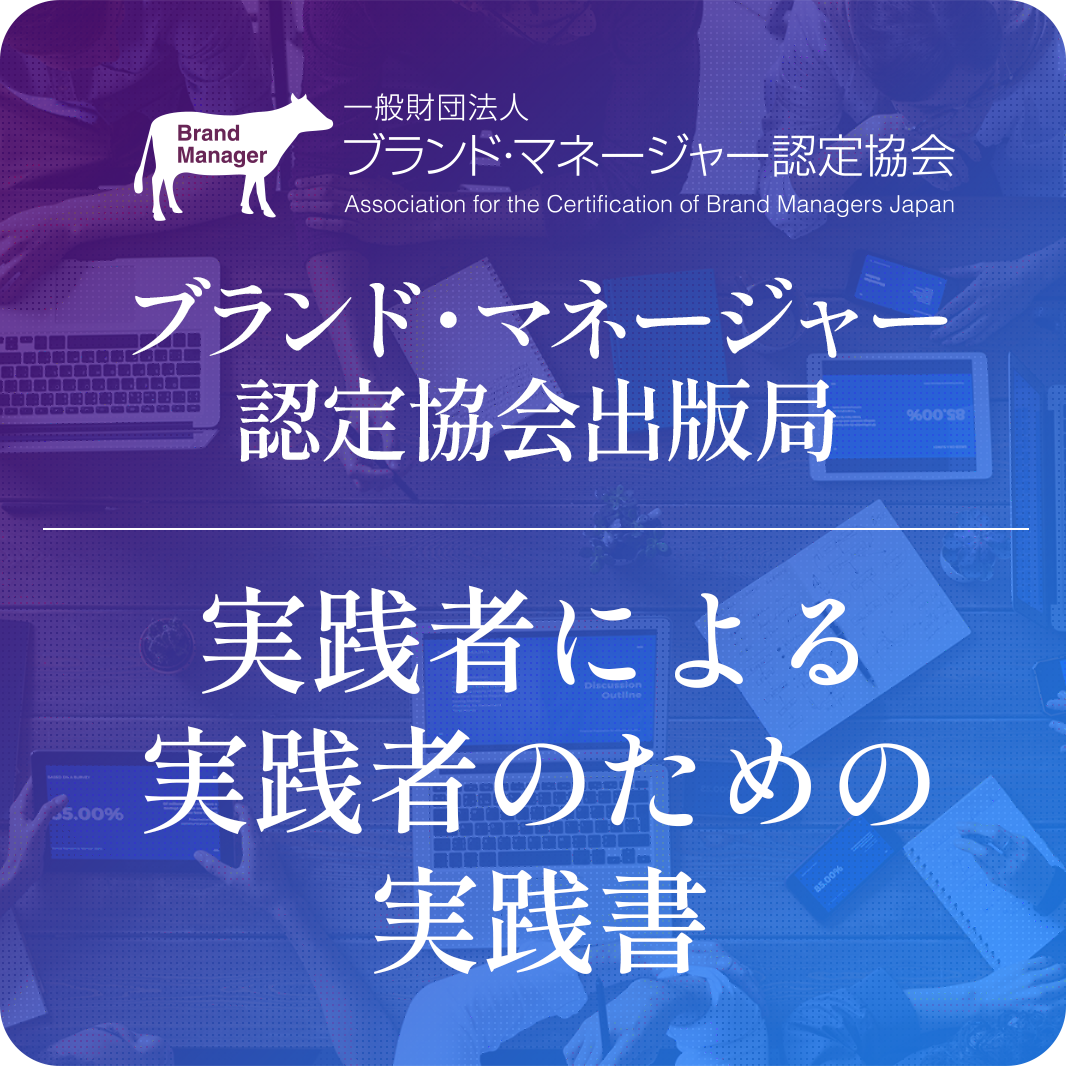ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >高野 登氏 Vol.1
~存在そのものがブランド~リッツカールトン流ブランディングとは 前編
高野 登氏 Vol.1 人とホスピタリティ研究所主宰
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【高野登氏のプロフィール】
1953年長野県生まれ。
元 ザ・リッツカールトンホテル日本支社支社長。
プリンス・ホテルスクール(現日本ホテルスクール)
第一期卒業後、ニューヨークに渡り、
ホテルキタノ、 NYスタットラーヒルトン、
NYプラザホテル、SFフェアモントホテルを経て、
1990年ザ・リッツカールトン・サンフランシスコ入社。
1992年に日本支社立ち上げのために来日。
その後ホノルルオフィス開設のため
ハワイへ転勤後、1994年に日本支社に転勤。
1997年にザ・リッツカールトンカンパニー大阪開業。
2007年3月にザ・リッツカールトンカンパニー東京を開業。
2009年、ザ・リッツカールトンカンパニーを退社。
2010年、人とホスピタリティ研究所を設立。
著書に『リッツカールトンが大切にするサービスを超える瞬間』
『絆が生まれる瞬間 ホスピタリティの舞台づくり』(どちらもかんき出版刊)。
アメリカ研修旅行がホテルマンのきっかけ
聞き手
高野さんがホテルマンになりたいと思ったきっかけは何だったのですか。
高野
特にきっかけはなかったんです。
もともと極端な人見知りで、子どものころは人と遊ぶのが苦手で、家に人が来るのも嫌でしたね。
野球とかはいつも補欠の補欠で、引っ込み思案だから結局、試合に出られない。
ですから、自分でもなるべく人と会わない仕事に就こうと思っていたんです。
父親は、中学を出たら町の大工さんに弟子入りさせようと思っていたみたいです。
聞き手
一人遊びが好きな少年だったんですね。そんな少年がなぜホテル業界に?
高野
今も性格は基本的に変わらないんですけど(笑)、根っこのところは同じなんですよ。
例えば、「パソコンや携帯を持たずに1週間山小屋にこもる」という仕事がきたら何の抵抗もなくできますよ。
なぜ、そんな人間がホテル業界に入ったのか自分でも不思議でしょうがないですね。
高校は、帳簿付けの仕事なら人に会わなくて済むと思って商業高校に行ったのですが、商業の仕事で人に接しないわけにはいきません。
高校の先生にも「君には商業は合わない」と言われました(笑)。
「でもまんざら成績が悪いわけではないので、工業系や理工系の大学に行って技術者や研究者を目指したらどうか」
と勧められまして、それもそうだと思い、理系の勉強を高校2年の終わりから始めたんです。
ところが3年の夏休みに、「日本初のホテルマン養成スクール」(プリンス・ホテルスクール:現日本ホテルスクール)の募集を目にして、気がついたら何かに導かれるように資料請求していました。
その資料に載っていた外国人のホテルマンの姿が自分にだぶって見えたんです。
なんだかデジャブ(既視)感というか妙になつかしい感覚で、「そこに戻らなければ」という気持ちになったんです。
で、高校の先生にそっちに進みますと報告すると、「君には一番向いてない」って言われましたけど(笑)、親にも話して入学の準備を進めたんです。
聞き手
養成スクールでは、ホテル業に対してしっくりくるものがあったのですか。
高野
それが入ってはみたもののまったくないんです。
何か現実の人生との一体感がないんですね。
この感覚はそれからもずっとあって、実は今もそうなんです。
自分を客観視しているということではなくて、並行する複数の人生があって、それが同時進行している感じなんですね。
たぶん、死ぬまでそうなんだろうなって思いますね。
聞き手
でも、ホテルマンの養成スクールは、その後の人生の分岐点になったのですよね。
高野
スクールでの2年間が自分の性格改造にものすごく役立ったのは確かですね。
新しくできたばかりの学校の第一期生に入ってくるのは、変わった人が多かったですね。
マグロ漁船で働いていて事故で指を失った人とか、高校生時代に女子生徒を何人も妊娠させて退学寸前までいった人とか、とんでもない奴ばっかりなんですよ(笑)。
でも人生って面白いもので、マグロ漁船の男は、今では北海道で英会話スクールを6店舗経営しています。
女子生徒に悪さをした男は、今は大阪で旅館を2軒経営しています。
そのときに真面目に勉強していた同級生たちは、ホテルに就職して定年を待っている人生ですけどね。
聞き手
その中で高野さんはどういう学生だったのですか。
高野
私は学校に行っていてもアルバイトのことで頭がいっぱいでした。
入学金は親が出してくれたのですが、学費と毎月の生活費をかせぐのにアルバイトばかりしていました。
今でもその時代で記憶にあるのは、スクールで学んだことよりもアルバイトで働いたことですね。
聞き手
それでも2年後に卒業してアメリカのホテルに就職しますよね。
高野
スクールではホテルで現場研修した時の研修費を積み立てたお金で海外修学旅行に行かせてくれるのですが、私たち一期生の行き先はアメリカでした。
2週間半の研修旅行で、バンクーバーから入ってロサンゼルスまでに長い道のりを、ホテルやモーテルに泊まりながら2週間かけてバスで移動するのです。
1973年ごろですから、当時は今と違って何もないころで、見渡す限り麦畑やとうもろこし畑なんです。
移動中のバスの中から見ていると、セスナ機がとうもろこしを刈った後の畑に農薬を散布していました。
1時間ぐらい走っていくとまた散布用の別のセスナ機が飛んでいる。
日本ではそのころ、人が農薬の噴霧器を背中に背負って散布していましたけど、アメリカは飛行機を使っていたんですね。
そのとき、やはりアメリカに来なければと思ってしまった(笑)。
それがきっかけでアメリカのホテルに興味を持ったんです。

リッツカールトンは同業者として気になる存在だった
聞き手
リッツカールトンに入るきっかけは何だったのですか。
高野
ザ・リッツカールトンホテルが開業したのは1984年ですから、私がアメリカのホテル業界に入ったのはその10年前ですね。
最初はニューヨークのホテルで、その後ヒルトン、プラザ、ウエスティンを経て、サンフランシスコのフェアモントホテルに移りました。
その3年後に、サンフランシスコのリッツカールトンホテルが立ち上がったのです。
聞き手
リッツカールトンへ転職はご自身で選んで行かれたのですか。それともヘッドハンティング的なオファーがあったのですか。
高野
当時、フェアモントで働きながら、間近でサンフランシスコのリッツカールトンホテルが建設されていくのを見ていました。
やがて、フェアモントのキーパーソンがリッツカールトンホテルに転職したり、私のボスのボスだったレオ・ハートがリッツカールトンホテルの副社長としてヘッドハンティングされたりしていきました。
しかし、私はレオに引き抜かれたわけではありません。
レオはフェアモントの従業員には誰一人声を掛けていませんでした。
部下を引き抜きしないというのが、フェアモントホテルのオーナーに対する彼の仁義だったんですね。
私はそのころ、フェアモントとの3年の契約が切れるころで、契約更新はどうするかと打診されていました。
更新のためにオーナーの部屋を訪ねると、その部屋の窓から工事中のリッツカールトンホテルが見えたんです。
私は更新のサインをせずにそれをじっと見ていました。
すると、オーナーはふっと笑って、「行きたいんだな」と(笑)。
「できれば挑戦してみたい」と告白すると、オーナーは「分かった。やってみなさい」と言ってくれました。
それで、ちゃんと入社試験を受けて、1990年にザ・リッツカールトン・サンフランシスコに入社したのです。
聞き手
じゃあ、やはりご自身の意思で。
高野
リッツカールトンホテルは同業者としてとても気になる存在でしたからね。
フェアモントもいい会社で地元では尊敬されていましたから、あそこで契約更新していたら、ずっとフェアモントで働いていたでしょうね。
聞き手
そのあと、日本支社開設ということで、中心的に動かれるわけですね。
高野
リッツカールトンの全体会議のときに、「半年後に日本にも支社を開設する」という発表がありまして、私は全くの”寝耳に水”だったのですが、「君にやってもらう」というわけです。
それからは、まずアトランタでザ・リッツカートンホテルカンパニー・オブ・ジャパンの本社を立ち上げて、日本に支社を開設するというだんどりでした。
ですから、ジャパン社の本社はアトランタにあったのです。
そのあと1994年に日本に帰国して従業員を募集したり、日本支社立ち上げに向けて動き出したのです。

リッツカールトンのブランディングが成功した理由
聞き手
リッツカールトンは、ホテル業界でブランディングが最も成功したホテルだと言われています。
高野
いや、そんなことはないと思いますよ。
ブランドで言えば、やはりヒルトンが一番強いでしょう。
例えば、銀座で歩行者に「ヒルトンホテルを知っていますか?」と聞けば、10人中8人は知っていると答えるでしょう。
でもリッツカールトンホテルはどうでしょう。
今は六本木にもあるので10人中5人ぐらいは知っているかもしれません。
ブランディングに成功したといってもまだそれぐらいの認知度です。
聞き手
しかし、経営者層などリッツカールトンのターゲット層の認知度は高いのではないですか。
高野
ブランドづくりをするには対象を絞り込まなければなりません。
ですから、リッツカールトンでは「ターゲットはトップ5%」と言い切っています。
「トップ5%」といっても富裕層なのか、知名度の高い人たちなのかイメージが湧きにくいですよね。
つまり、リッツカールトンはイメージを沸かせないために「トップ5%」と言っているのです。
逆に言えば、95%はイメージの中で切り捨てることができます。
だから絞り込めるのです。
対象を絞り込めば絞り込むほどブランドは先鋭化していきます。
聞き手
逆に対象を広げれば広げるほど、ブランドは壊れてしまうということですね。
高野
例えば、日本航空の子会社が「ジャルパック」という素晴らしいブランドがあるのに、近鉄に対抗して、「ジャルパック」のセカンドブランド「AVA」を立ち上げました。
すると、本来は近鉄に対抗するはずだったのに、「ジャルパック」を利用していた上得意のお客さままでがみんなそっちの安い方に行っちゃった。
あるいは、有名なファッションブランドが同じブランド名でトイレットペーパーまで作ったら、本業のプレタポルテの方がガタガタになってしまった。
ブランドを立ち上げるときの怖さというのはそういうことなんです。
知人に川崎でブテックを経営している人がいるのですが、そこのブランドはターゲットを絞り込んで、「25歳の5月生まれのOLがコンパに着ていく勝負服」というコンセプトを打ち出しています。
聞き手
そこまで絞り込んで具体的にすることが重要なのですね。
高野
それぐらい絞り込めば、主婦や学生も「5月生まれの25歳のOL」が利用する店やブランドに興味が湧いてきます。
「どんなブランドなんだろう。一度行ってみよう」とね。
それぐらい絞り込まないとブランドはできないですね。
多くの会社は「ターゲットは5%」と言いながら、少し業績が良くなってくるともっと対象を広げようとします。
「25%まで広げよう」と。
その瞬間にブランドが壊れ始めます。
.jpg)
聞き手
リッツカールトンでは、「自分たちのお客さまはトップ5%」ということを従業員に言い続けているのですか。
高野
ずっと言い続けています。
ですから、一般のお客さまは、イメージの中で敷居が高いホテルと思っている。
これは実はイメージ戦略でもあるのです。
立ち上げの最初のころは、「少し敷居が高いらしい。でも興味があるよね」というイメージでブランディングしていったのです。
ですから、日本で初めて開業したザ・リッツカールトン大阪は、大阪では半年間、客室稼働率が最下位でした。
聞き手
あせりはなかったですか。
高野
怖かったですね。このままいったらどうなるのかと。
聞き手
我慢されていたんですか。
高野
料金が隣のホテルの2倍以上もするわけです。
隣のホテルが1泊1万2000円のときに2万7000円でしたから、普通に営業していても稼働率を一気に上げられるわけがないと思いました。
そのため、付加価値をどうやって付けるか、もっと付加価値を付けられないか、そればかりを毎日みんなで脳みそが汗びっしょりになるくらい考えていました。
そのかいがあって、6カ月目ぐらいから一気に稼働率が上がっていきました。
聞き手
その6カ月間をいかに我慢できるかですね。下手すれば値段を下げたりしてブランドを壊しかねない。
高野
何のために我慢するかが分かっていれば耐えることができるんですよ。
リッツカールトンは宿泊施設をつくっているのではなく、ブランドをつくっている。
宿泊率を上げるのではなく、ブランドをつくるという目的があったから我慢できたんです。
聞き手
ブランドづくりを目的にできたのはなぜですか。
高野
理解しづらいかもしれませんが、リッツカールトンを仕事にしていること自体がブランドづくりなんです。
我々の営業活動とはブランドづくりそのものだったわけです。
聞き手
それは本社から言われて?それとも高野さんの使命としてですか。
高野
いや、リッツカールトンの成り立ちそのものがブランドづくりなのです。
1984年に開業したときから、リッツカールトンはホテルをつくるとは言っていません。
「リッツカールトンはブランドをつくる」
としか言っていないのです。
存在そのものがブランドなのです。
それをそのまま大阪でも実践したに過ぎません。
聞き手
お客さまの認知度が上がり、利用客が増えていく中で、従業員に徹底したのは何ですか。
高野
「リッツカールトン」というブランドを意識したふるまいや行動を常に言い続けることでした。
※掲載の記事は2015年10月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。