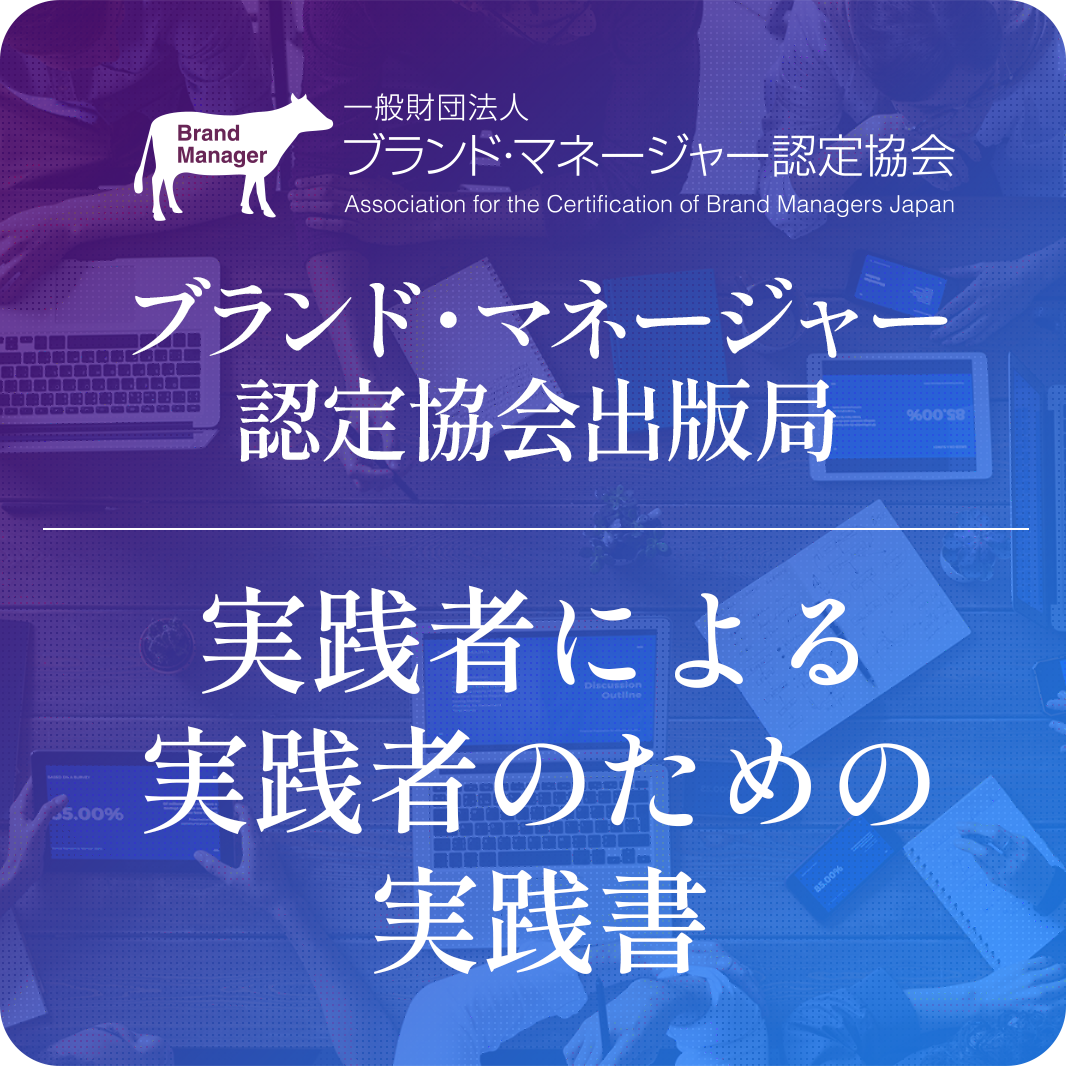ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > スペシャルインタビュー >上村 孝樹氏 Vol.2
これからのビジネス戦略に必要な「顧客にもたらす付加価値」と「ブランド戦略」 – 後編
上村 孝樹氏 Vol.2 事業創造大学院大学客員教授
聞き手:一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 代表理事 岩本俊幸

【上村氏のプロフィール】
「付加価値向上戦略」を提唱する経営ビジネスアドバイザー。
1949年新潟県生まれ。青山学院大学経済学部卒業。
日本ビジネスコンサルタント(現日立情報システムズ)を経て、
80年日経マグロウヒル(現日経BP社)に入社。『日経コンピュータ』副編集長、
『日経情報ストラテジー』編集長、『日経アドバンテージ』創刊編集長を歴任し、
2005年日経BP社を退職。04年から10年まで金沢工業大学大学院客員教授。
07年から事業創造大学院大学の客員教授に就任。
著書に『21世紀を勝ち抜くIT戦略』(日経アドバンテージ)、
『IT経営百選データブック』(著・監修、アイテック)、『経営革命者』(アイテック)、
『IT経営百選データブック2』(編・著、アイテック)など多数。
付加価値向上戦略のフローチャート
聞き手
付加価値向上戦略のフローチャートはどういうステップになっているのですか。
上村
まず、最初は市場認識からスタートします。
20世紀と21世紀のマーケットの違いを確実に認識させます。
ここから始めないとマーケティング戦略もブランド戦略もあり得ません。
つまり、20世紀のような右肩上がりのマーケット成長は終わったということ。
市場成長、成長と言っているのは現実を見つめていないということをしっかり認識してもらいます。業種別に見ても、先進国では買い手市場に転換しておりほとんどの業種で市場規模は下がっています。それが市場認識です。
成長しない市場、マイナス成長の市場、あるいは停滞市場の中で生きていくためには、ターゲットをより明確化して、良いお客さまと長いお付き合いをしていくという基本戦略をつくるというのが2番目のステージになります。
3番目のステージでは、その戦略を実現するビジネスモデルをつくり、確実に実行しなければなりません。
そのためには顧客にアプローチして、仕事を受けて、ものづくりであればものを作り、ストックして、それを物流で届けて、またお客さまにリピートしてもらう。その一連の流れをビジネスモデルとしてつくり上げます。
そのビジネスモデルをスマートにつくるためには、21世紀はインターネットがグローバルなインフラになっていますから、それを徹底的に利用して情報を全てデジタル化して共有、効率良く仕事が出来るようにします。そうしないと、無理、無駄、ムラが発生します。
仮説・検証もうまくいきません。情報をデジタル化そして、大福帳(帳簿)のように時系列生データをデータベース化して、リアルタイムにビジネスウオッチングできるようにします。

上村
ビジネスモデルをつくってしまえばそれで終わりでなく、必ず環境は変化し、お客さまも進化しますから、ビジネスモデルはその変化に合うように修正されなければなりません。
これをタイムリーにやらなければなりません。
それはコンピュータが自動的にやるわけではなく、人間が修正しなければならない。それがマネジメント力なのです。
このマネジメントモデルが革新されていかないと、ビジネスモデルは適合できるように修正されなくなります。
お客さまの動向が変わった、法律が変わった、環境が変わった・・・。じゃあ、製品を変えなければいけない、物流を変えなければならない、販売方式を変えなければいけない。
これを実行する力がマネジメントモデル、すなわち「やる気創造」力です。
このマネジメントモデルをしっかり考えなければならない。
つまり、ビジネスモデルを維持・運用するためのマネジメントモデルの革新が必要不可欠になってくるのです。
聞き手
いわゆるPDCA(plan-do-check-act=計画・実行・検証・改善)でしょうか。
上村
20世紀型のPDCAではなく、もっとそれを戦略の時点から実行段階まで一気通巻に厳密にやるわけです。
マネジメントモデルができたらいいのかというと、実は落とし穴があって、いいものはつくったけども会社は倒産してしまったというケースも出てくる。
そこで4番目のステージとして「経営の自立化」というテーマが出てきます。
これはブランド戦略でも同じだと思います。
たくさん売れたけど、その8割は同じグループの得意先だったという構造をつくってしまうと大きな経営リスクを抱えることになる。
つまり、特定の顧客に依存してしまう事になる。
経営の自立化には、「金融に対する自立性」「自社ブランドの浸透」など主要な5つの要素があるのですが、筆頭にくるのが一つの顧客(グループ企業)の下請けでなく自分の力で顧客開拓して「顧客分散すること」です。
まず、この「経営の自立化」がなされているかどうかが重要になります。それがビジネスモデルのチェックです。
もう一つ重要なのは、マネジメントモデルのチェックです。そのためには経営のオープン化が必要です。
良いマネジメントモデルかどうかを検証していくために重要な要素として必要なのが「経営情報の開示」です。
社内のチームにビジネスの状況がリアルタイムに正確に開示されているかどうか。
社内だけでなく、取引先、顧客、社会に対しても必要情報の開示・共有を実施しているかどうか。
それを検証していかなければなりません。それらがすべてクリアされていくと、最終的に前述した「4つの満足度(ES、CS、PS、SS)」が達成されるはずです。最後に株主など資金提供者の満足度を入れてもいいでしょう。
これらの要素の毎期ごとの目標値を設定して、その満足度が達成されたかどうかを計測する。
モニタリングして評価し、翌年にフィードバックする。そこでまた、PDCAが必要になってくる。それぞれのステージでPDCAを繰り返すわけです。
つまり、付加価値向上戦略とは、企業の質の成長戦略でもあるわけです。
大事なことは結果的に進化しているかどうかなのです。環境はどんどん変化していきますから、企業は進化していかなければ環境変化に対応できません。
企業の「存在意義」とは何か
聞き手
大学院の講座では、今の話をどれぐらいのスパンで教えているのですか。
上村
大学院の講座だと1回90分で上期15回しかありません。15回でやるのは非常に大変ですね。冒頭の30分間は、前回の講義の質問や意見に対して回答していますから、実質1回当たりは約60分ですね。
でも、質疑応答をやらないと、受講者の情報共有が進みません。全体がレベルアップしませんから重要な事です。
経営戦略ですから全体を包括して、どういう流れの中でその部分がなぜ必要なのかを理解させなければならない。
講義では付加価値を向上させて経営を進化させるPDCAのダイヤグラムを見せて、要所ごとに診断シートで企業の状況を評価できるようにします。
ビジネスモデルの項目では、ビジネス情報のデジタル化の状況、ITツールの高度活用しているかどうかなどの診断シートがあったり、経営戦略とビジネス戦略が合っているかどうかの診断シートがあったり、従業員満足度や経営のオープン化など多くの評価診断シートがあります。
そのほか、ターゲットにリーチして市場獲得するため情報発信がホームページなどを使い戦略的レベルでできているかどうか、どうかの診断シートもあります。
聞き手
それは全て上村さんのオリジナルですか。
上村
そうです。2004年から3年間、経済産業省の「IT経営100選」選考委員会の委員長を務めたのですが、そのときに優秀企業を評価するのに原型を適用しました。その後改良して現在の形にしました。
それを基にして21世紀に生き残っていける中小企業の戦略的経営、IT経営と謳っていますが、ITの活用はあくまで手段であって、それ自体は目的ではありません。経営絵戦略を実行するツールです。
経営の評価項目の4分の3がビジネス戦略、経営戦略、マネジメントなどに焦点を当てたのです。あとの4分の1をIT活用に当てました。
過去3年間の売上げ、利益、ITにかけている経費、自社のビジネスのこだわり、独自性、強み、ビジネスモデル、マネジメントモデル、顧客満足度、従業員満足度の計測方法など全て記入してもらい評価するわけです。
それらは経営の根幹であり、まさしく経営戦略です。
それを書いて応募してきた企業を審査して、優秀な企業には実際にヒヤリングに行きました。
その上でもう一度書き直してもらい、再提出してもらいました。
トップの企業が最優秀企業として認定しました。
聞き手
企業の経営データの根幹を公開するわけですから、嫌がる企業も出るでしょうね。
上村
IT活用だけで表彰されたいと思って応募したのに、BS(貸借対照表)、PL(損益計算書)まで提出が求められますから抵抗するのは当然ですね。
しかし、このプロジェクトは応募してくれた企業を表彰するのが目的ではなくて、ほかの中小企業にお手本を示そうというのが目的ですから、それは成功した企業の社会的義務であるという考え方です。
実際に応募してくる企業はないのではないかと行政は心配しましたけど、私がこれはと思う企業100社に主旨を打診したところ、そのうちの70社が応募してきてくれました。
行政の方でも各地域ごとに優秀企業を中心に応募を募りました。

聞き手
その中で結果的に何社を選定するのですか。
上村
最優秀賞、優秀賞、奨励賞、IT活用企業賞の4つのレベルで評価しました。
最優秀賞は業種別に選定しましたから、04年度(第1回)に認定したのは20数社あります。
第2回は2年間の経営データの比較から進化のプロセスが見られるように前回受賞した企業にも応募資格を与えましたから、当然ながら2回連続で最優秀賞を受賞する企業もありました。
聞き手
業種別の傾向などはありましたか。
上村
例えば、IT企業だとIT活用の項目が傑出するわけですが、ビジネス戦略、経営戦略が弱い。
なぜなら、IT産業は大企業の下請けでこれまで営業してきた部分が大きいから経営の自立化度が弱い。
基本的に、日本の中小製造業は圧倒的に下請け企業が多いのです。だから、経営の自立化が大変遅れている。
しかし、21世紀はインターネットがグローバル化していますから、年商1億円の会社でも80%が海外の顧客という会社の出現もあり得るでしょう。
サービス業・流通業は顧客接点の場を持っていますから、ある意味、経営の自立化は達成できているのかも知れませんか、経営哲学、経営ビジョンが魅力ない。
自分だけ儲かればいいと経営者は考えがちです。従業員満足度の最大化を掲げる企業はごく少数です。
飲食業の店長の年収の低さは全産業の中でも目立ちます。
聞き手
選定基準で何が最も重要なのでしょうか。
上村
経営者の哲学、美学ですね。最優秀企業に選定された企業は、この点が非常に魅力がある。経営者が何のために起業したのか、何のために会社を存続させていくのかという企業理念の追求がしっかりなされているは素晴らしい企業です。
われわれはその経営理念やビジョン、ミッションも評価しているわけです。
日本の中小企業は、地元経営者の会合や寄り合いが好きです。
そういうものにばかり出席していると、だんだんとそういう理念やビジョンを追求しなくなります。
聞き手
理念は非常に概念的なものですが、どういうふうに評価するのですか。
上村
例えば、評価項目の中の「満足度の追求」であれば、従業員満足度の追求は具体的にどのようなプログラムで、どのような目標設定で、具体的に何をしてきたか、また賃金体系はどれくらいの水準か、というふうに行動レベルまで落とし込み評価します。
聞き手
どんなに立派な理念を掲げていようが、行動レベルに落とし込まれていなければ全く無意味ですね。
上村
理念を掲げている以上、それに行動が伴っていなければ、それは偽善であり詐欺みたいなものになる。いくら美しいことを並べても、それを実行しなければ、うそつきと一緒です。
同様に、いくら立派なブランドを展開し立派な利益を出していても、その会社で働いている従業員の平均給与が業種平均を下回っている企業がある。
それはどう考えてもおかしいことでしょう。
要するに、会社が苦しいときに金を出せと言っているのではなくて、儲かったら従業員を筆頭としたステークホルダーに還元しなさいと言っているわけです。
利益に応じて皆で山分けしなさいと言っているのです。
それは努力して結果を出せば報われるということです。それができないならば良い会社ではありません。
結果を出して報われる会社なら皆のやる気にスイッチが入ります。それが「やる気創造」の原点です。
GNH(国民総幸福量)という概念
聞き手
ブランド戦略において、付加価値向上戦略を取り入れるべきポイントは何でしょうか。
上村
ブランドとは価値を明確な形として認知してもらうためのものですから、製品やサービスに限らず、企業そのものや従業員も該当します。
その意味で言えば、付加価値向上戦略も、魅力ある企業としての価値を顧客や社会に認めてもらおうと言っているわけですから、定義は同じです。
何をブランディンの選択にするかは戦略です。もちろん、従業員をブランドにしてもいいわけです。
聞き手
ブランドの一貫性を保つためにすべきことは何でしょうか。
上村
一貫性を保つのに重要なものは企業文化ですね。ブランドは企業文化を表現したものでなければいけないと思います。その整合性が図れているかどうかでしょうね。
聞き手
でないと消費者は違和感を持ってしまいますよね。
上村
その商品やサービスが企業文化を反映しているかどうか。その背景には経営哲学や経営の美学がなければならない。経営理念も経営ビジョンもそうです。
聞き手
結果的に、理念から始まって経営戦略になってブランド戦略につながる。
上村
その通りだと思います。企業文化というのは1000社あれば1000通りのものが存在します。みんなが同じものをコピーしても意味がありません。
どういう企業文化を形成するかは、経営者が中心となって考え、それを明確化して、その文化に合う人を呼び込む必要があります。
その文化に合わない人は、共に価値観を分かち合えませんから良い結果は生まれない。
優秀な大学を出た人からという評価基準で採用するという人事方針は、企業文化を共に分かち合うのとはまったく違ったことで失敗する最大要因です。
ブランド採用選択の基準設定はしっかりやる必要があります。
その意味では企業文化も一つのブランドなのです。
聞き手
企業理念に合った価値観を持つ人を集めるということですね。
上村
企業文化もこれまでのような利潤追求型の文化ではなく、CSR(Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任)のような考え方がどんどん浸透してきています。
ファイブフォース分析を提唱したマイケル・ポーター(米国ハーバード大学経営大学院教授)は、CSRを発展させて最近「CSV(Creating Shared Value=共有価値の創造)」を提唱しています。
これまで、アメリカの企業は、CSRで企業活動をイメージアップに利用したり、一人よがりで貢献活動をしていきましたが、果たしてそれは社会を良い方向に変革することにつながっているかと疑問を投げかけています。
社会の変革とは、企業が活動している地域に対しても良い影響を及ぼしているのか、ということです。
地域の環境を良くするために、その地域にある企業の活動が地域の環境や健康推進にどれだけ貢献しているか。
あるいは取引先の地域のある地域の産業が良くなるように、どれだけいい関係を維持しているかということを考えて実行するのがCSVです。
例えば、ポテトチップスを製造販売している会社が、ジャガイモ農家が質の高い農産物を健全な生計を営みながら生産できるるように、彼らの地域環境にどれくらい貢献しているのか。
それを早く矯正しなければならないというのがCSVの概念です。
それはCSRを追求した延長線上に出てくるものだと思いますが、それを意識的に分けるために、マイケル・ポーターはCSVの概念を提唱したのだと思います。
さらに私たちは、「最終的に利益や売上げだけ追求しても楽しくないでしょう?」ということに耳を傾けなければなりません。
1973年にブータンが提唱した「GNH(Gross National Happiness=国民総幸福量)」が、GDP(Gross Domestic Product=国内総生産)に代わる新しい概念として先進国で見直されてきています。
インドと中国にはさまれたブータンは人口75万人ぐらいの小さな国です。
その小さな国の国王が、今から40年近く前に提唱したGNHの概念が、今や世界的に注目されているのです。
聞き手
GNHの概念は、私たち経営者も参考にしなくてはいけない点が多そうですね。本日は大変興味深いお話をありがとうございました。
※掲載の記事は2015年5月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。