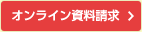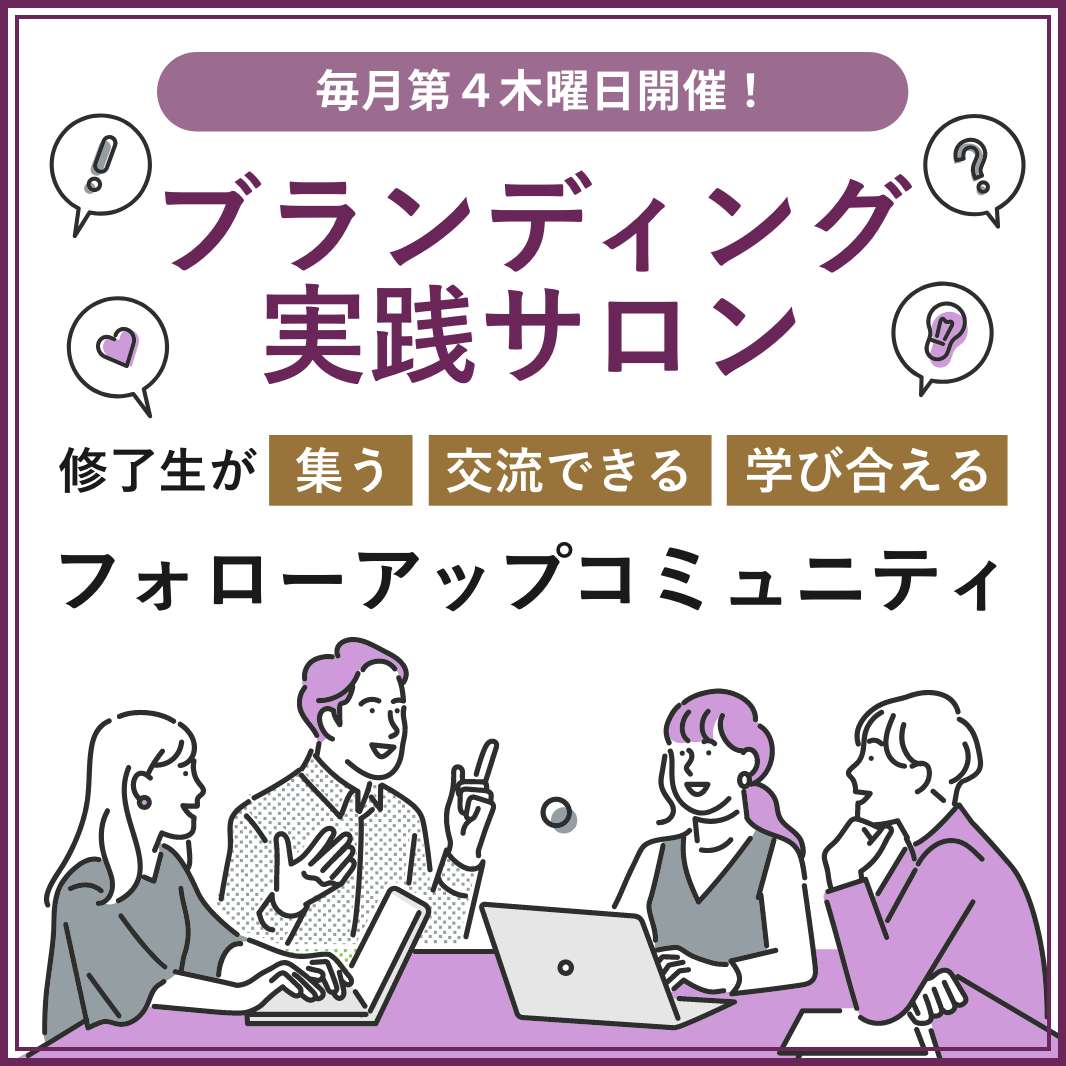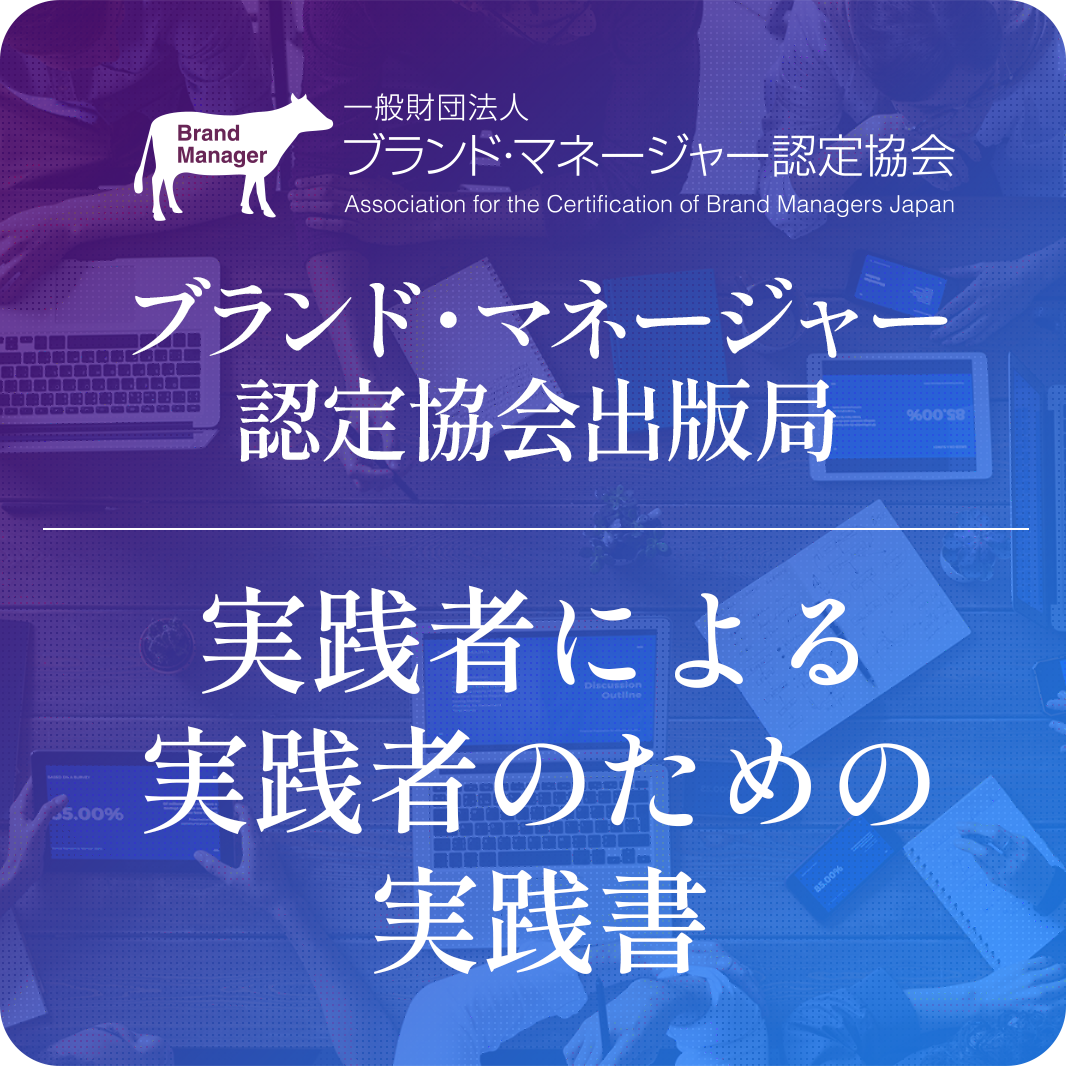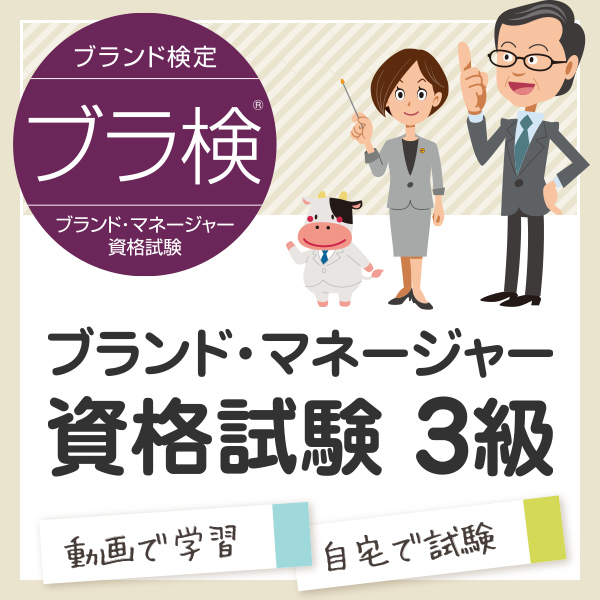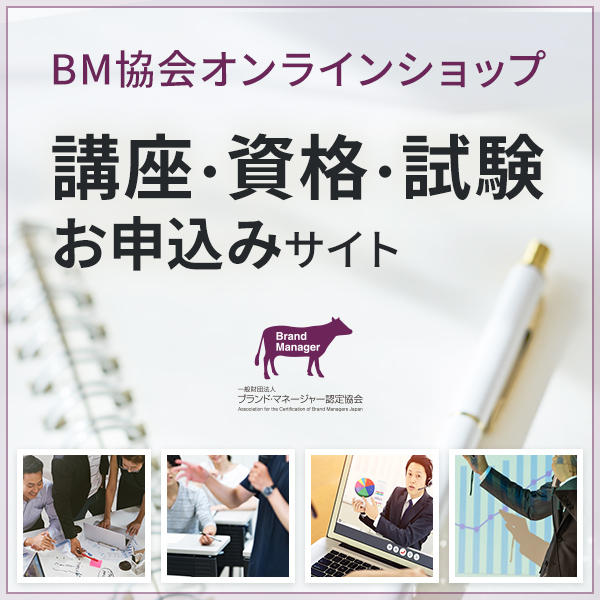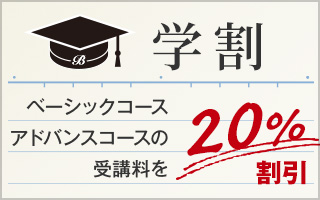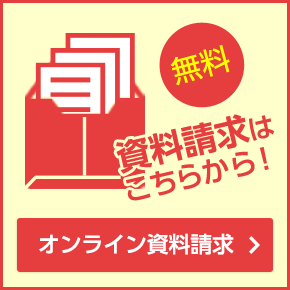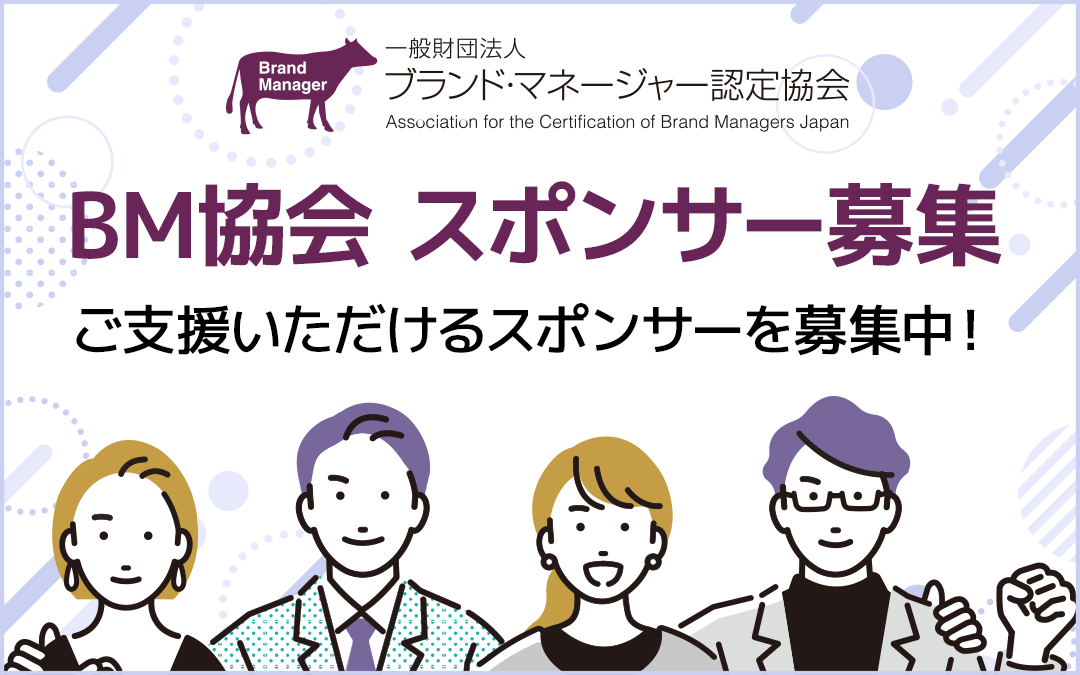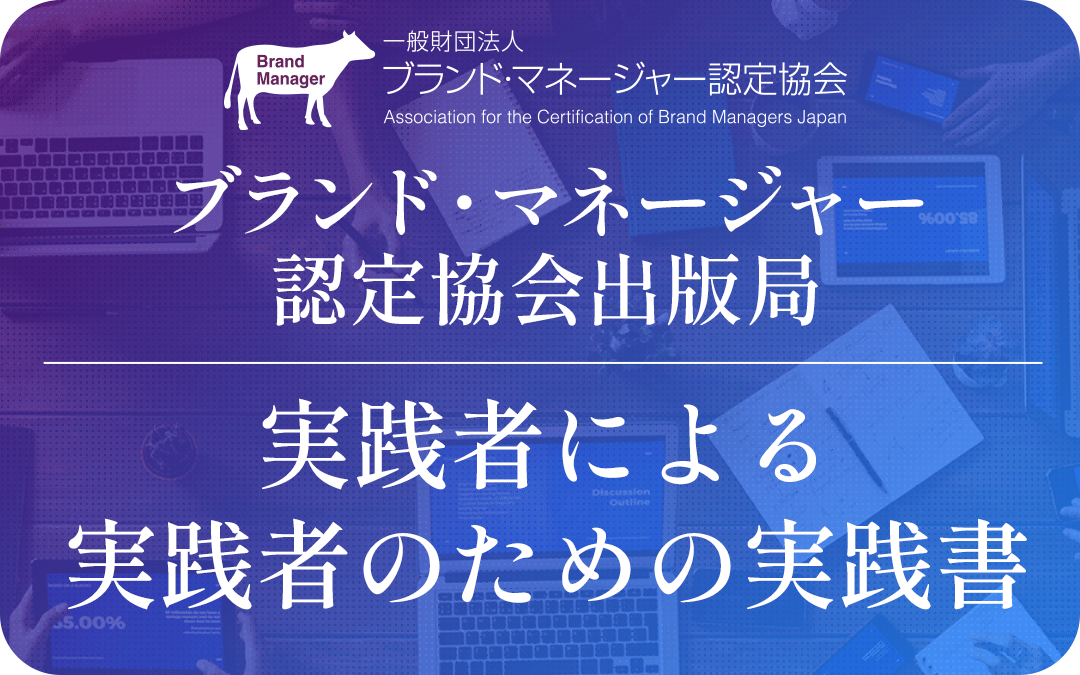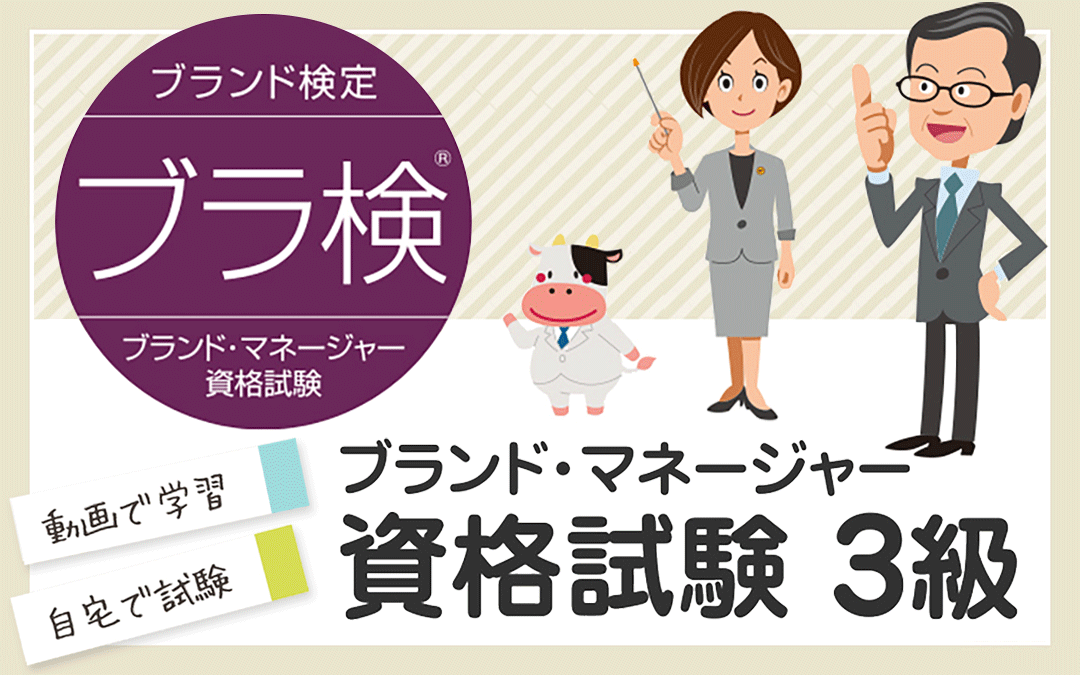ChatGPTで付加価値づくりを促進
生成AIを活用したブランディングとは?

株式会社りんごの木島田 良氏
Profileプロフィール
株式会社りんごの木 代表取締役社長
一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 理事/グランドマスタートレーナー
長野県長野市生まれ。
2011年長野県長野市・須坂市で美容室を複数店舗経営する「株式会社りんごの木」の代表取締役就任。
強みを活かした従業員参画型のブランドづくり「チームブランディング」で、様々な成果を上げる。
2010年より、当協会 認定トレーナー、2019年より、当協会 理事就任。
講師、コーチとして、ブランド人材の育成や地方都市におけるブランド戦略の浸透と活用に尽力。
現在は、ブランディングや人材育成、業務変革の領域での生成A I活用の研究と実践にも注力している。
ChatGPTと描くブランドの設計図
生成AIをチームメンバーに迎えるブランディングのステップとは?
現在、様々な分野でChatGPTに代表される生成AIが話題を集めています。
ビジネスの世界でもその活用に大きな期待が寄せられていますが、はたしてブランディングにおいてはどのような効果が見込めるのでしょうか。
今年7月に『ChatGPTと描くブランドの設計図 生成AIをチームメンバーに迎えるブランディングのステップとは?』(ザメディアジョン)を出版した一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会の理事であり執筆者のひとりでもある島田良氏に、同書の内容や、ChatGPTのブランディングにおける活用についてお話を伺いました。
ブランド構築ステップをChatGPTと一緒に
本書ではブランディングの基本やChatGPTを活用したブランディングの方法などが詳細に記されていますが、なぜ今回このような本を出版されたのか、背景を教えてください。
ChatGPTについては、Tips的な単発なコツを紹介する本が多く、使い方を体系立てて説明する本や専門領域に特化した本は、1年前はほとんどなかったんです。
最近は専門的な情報の本も多少出てきていますが、当時は専門的ではなく「ChatGPTはあれにもこれにも使えますよ」という内容の本が多かったんですね。
そこでブランド・マネージャー認定協会としては、専門領域のどこでどのように使うのかを解説する本には出版する意義があるのではないか、と考えたわけです。
出版するにあたっては2つの前提条件を設定しました。
1つ目は「ChatGPTと人間が役割分担し、協働することで、ブランディングの効率性と効果性を向上させる新たなアプローチを示す」ということ。
2つ目は「ChatGPTを活用し、体系的ブランド構築法である『ブランド構築ステップ』を効率的かつ効果的に行う具体的な手法とプロンプトを提供する」ということです。
つまり理論的なことだけではなく、実際にどう使えばいいのか、その手法を提供しようと考えたのです。

また、本書では「ChatGPTをチームメンバーに迎える」という表現がありますが、これは役割分担して協働するというコンセプトが重要だと思っているからです。
要するに、「ブランド構築ステップをChatGPTと一緒にやっていきますよ」ということですね。
「チームメンバーに迎える」というのは、全体の流れの中でChatGPT、生成AIに何を担当させるかを決めていく、という意味で、たとえば「ブランド構築ステップ」をワークフローのように分解するとステップごとに実践する内容が分けられますが、このステップの中でChatGPTに何を担当してもらうかを決めるのが「チームメンバーに迎える」ということなんです。

設定した仮想のブランド・マネージャーと対話しながらブランドを構築
具体的にはどのようにChatGPTを活用するのでしょうか。
本書で取り上げた例でご説明しますと、まずはブランド構築を行うためにChatGPTにブランド・マネージャーの役割を設定し、この仮想のブランド・マネージャーと一緒に、市場機会の発見からブランド・アイデンティティの作成までを行っています。
ブランド・マネージャーの人格設定は、プロンプトという指示文を入れることで行います。
そしてプロンプトを入れて出力すると、生成結果が出てきますが、それを鵜呑みにするのではなく、人間が「これでいいかな、もう少しここを足してほしいな」などと考察し、必要があればまたプロンプトを打ち、生成結果を出してもらい……という流れで進めていきます。
そして、その考察結果を次のステップのプロンプトに入れていきます。
つまり、入力情報を反映させて出力し、それに対して考察していく形ですね。
そのようにして設定したブランド・マネージャーと対話を繰り返しながらブランド構築を進めていくわけです。

プロンプトの入力例など具体的な細かい手法は本書を読んでいただければと思いますが、まずPEST分析について言うと、これまで人の力でPEST分析を行った場合は、情報収集に時間が掛かるうえ、「全体的に情報が少ない」「特定の分野に偏った情報しかない」という具合に情報収集が不十分なケースが多々ありました。
ですが、ChatGPTを使うことにより、幅広い情報源から情報を効率的・網羅的に収集することが可能になります。
また、3C分析では、顧客分析を起点に競合分析、自社分析を行いますが、一般的なやり方で顧客のニーズや不満を探っても、ありきたりのものしか出てこない場合があるんです。
それがChatGPTを活用することで、顧客のニーズ、不満を網羅できるうえ、指示によっては重要性の評価もしてくれるわけです。
競合分析でも、直接競合の情報を探してくれるうえ、分析する際の重要な項目も教えてくれます。
このほかにも、たとえばペルソナになりきって質疑応答をしてもらえたり、ポジショニングの軸となる様々なキーワード候補を挙げてくれたり……ということもChatGPTは可能です。
ブランド構築ステップで積み上げてきたものに基づいてブランド・アイデンティティの候補を挙げてくれるのも、大きなポイントですね。

ChatGPTをメンバーに迎えてチームブランディング
私が最近お手伝いをさせていただいた、ある小売業のチームブランディングを紹介します。
ちなみに「チームブランディング」は協会の造語で、小集団でブランディングとチームビルディングを同時に行う手法ということを指します。
つまり、組織の中で横断的に集められた中心となるメンバーを集めてその人たちとブランド構築ステップを行いながら、同時にチームビルディングも行っていく手法ですね。
小売業のチームブランディングということで、目的は、事業の継続と長期的発展でした。
業績が悪いわけではありませんが、量販店的な内容を更にブラッシュアップし、新しい体験価値を生み出したいという話だったんです。
安定感はあるけれど、新しい取り組みはあまりしていないというイメージを、「新しい取り組みをしている会社」に変えたい、と。
そして周りを巻き込んだ形で新しいことをやっていきたいという目標がありました。
つまり逆に言うと、量販店的で質的差異がないという問題があり、「価格勝負からの脱却」「外部と積極的に関わる」という課題があったわけです。
そこで、定性的変化と定量的変化も明確にしました。
まず、定性的変化は、リーダークラスの当事者意識を高めることが課題です。
一方、定量的変化は「この会社があってよかった」と思う人や地域が増える、ということを目指してブランディングしていきました。

このときのChatGPTの活用範囲は、ペルソナの作成とポジショニングマップのキーワード出し、そしてブランド・アイデンティティをまとめることと、それを反映させた「4P/4Cマーケティング・ミックス」です。
なぜこのプロセスにしたかというと、「当事者意識を高める」という目的があったので、最初からChatGPTを使うより、苦労しながら議論を重ねたほうが、当事者意識が高まるんじゃないかと考えたからです。
それでAチーム、Bチームに分かれてそれぞれの思いや考え方を共有し合い、ブランディングを進めました。
そのようにして出した市場機会の仮説からセグメンテーション、ターゲティング属性リストなどの情報をChatGPTに与えてペルソナを作成するところから、ChatGPTをチームメンバーに迎えてのチームブランディングを行いました。
ここでは、ChatGPTが出してくれたものに対して、チームでミーティングして修正を加えていきました。
たとえばポジショニングのキーワードもChatGPTに出してもらってポジショニングマップを作成し、ブランド・アイデンティティの候補もChatGPTに出してもらって、チームで議論をして決めていったのです。
ブランド・プロミスやブランド・パーソナリティもChatGPTに書き出してもらい、それに対してもいろいろな視点で話し合ってまとめていきました。
「4P/4C」もペルソナ、ブランド・アイデンティティ、ブランド・プロミス、ブランド・パーソナリティをもとに、ChatGPTに候補を出してもらいました。
このように、チームのミーティングの中にChatGPTというひとりのメンバーを加える形をとり、目的に合わせてChatGPTを活用する、というプロセスをたどったわけです。

ChatGPTを活用して付加価値づくりにチャレンジ
ChatGPTをはじめとした生成AIを優秀なアシスタントとして味方に付けることでコストや時間、労力などを削減しつつPDCAを高速で回して付加価値づくりにチャレンジできます。
効率化を図ることも大切ですが、仕事ではやはり付加価値づくりへの効果的なアプローチをすることが重要なのかなと思います。
生成AIの時代は、AIが人の仕事を奪うのではなく、AIを体系的に駆使する人が仕事を総取りする時代と言われています。
10年後は、人間は何もやらなくていい状態になっているかもしれませんが、少なくともこの2、3年以内は、生成AIをうまく活用できる人や企業が飛躍的に価値を高める時代になっていくのではないかと思っています。
※掲載の記事は2024年11月時点の内容です。
掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。
【登録無料】

会員サイト「メイク」