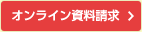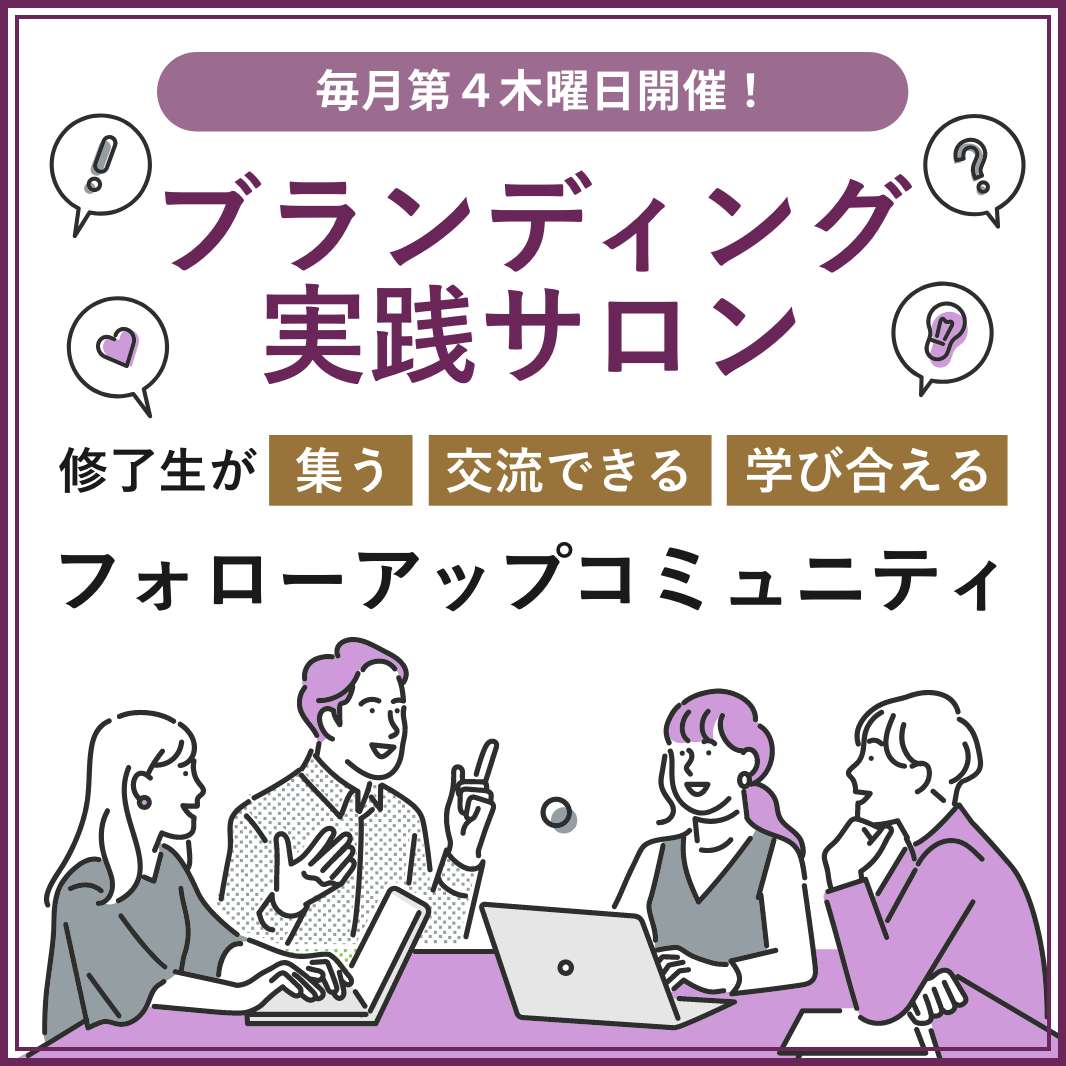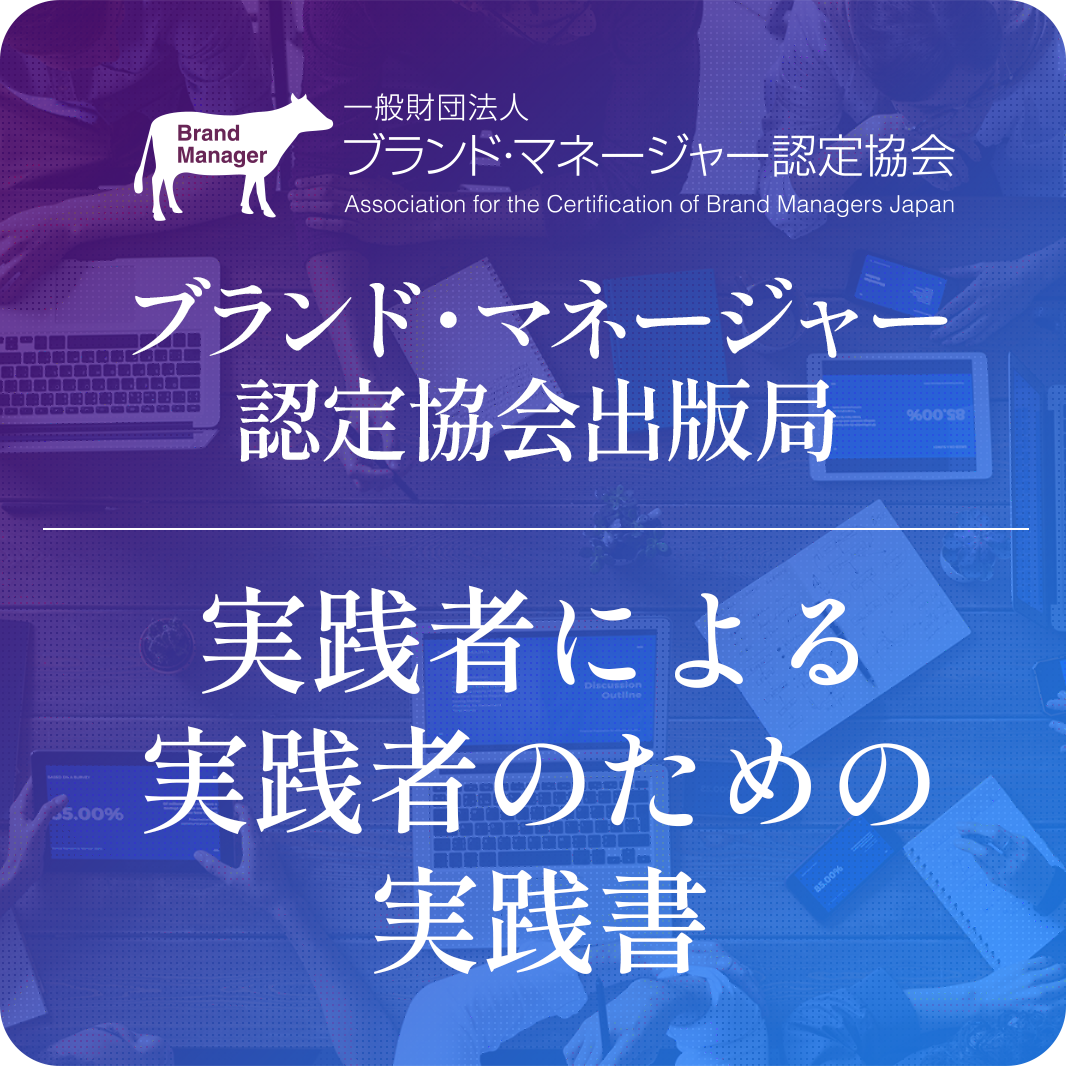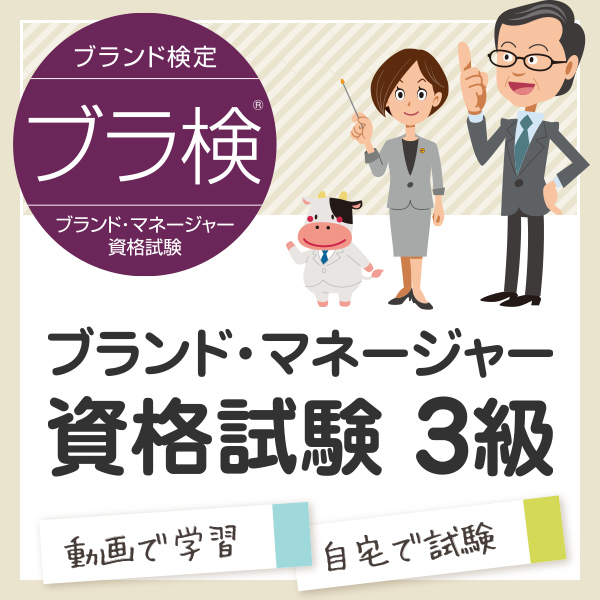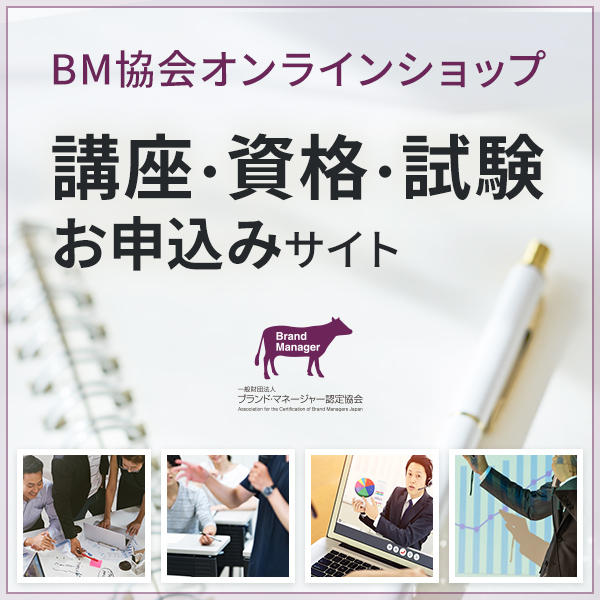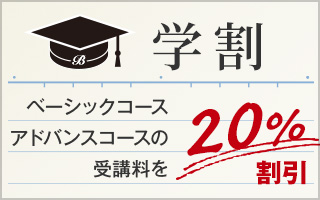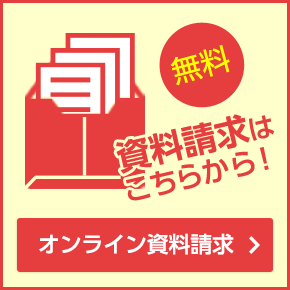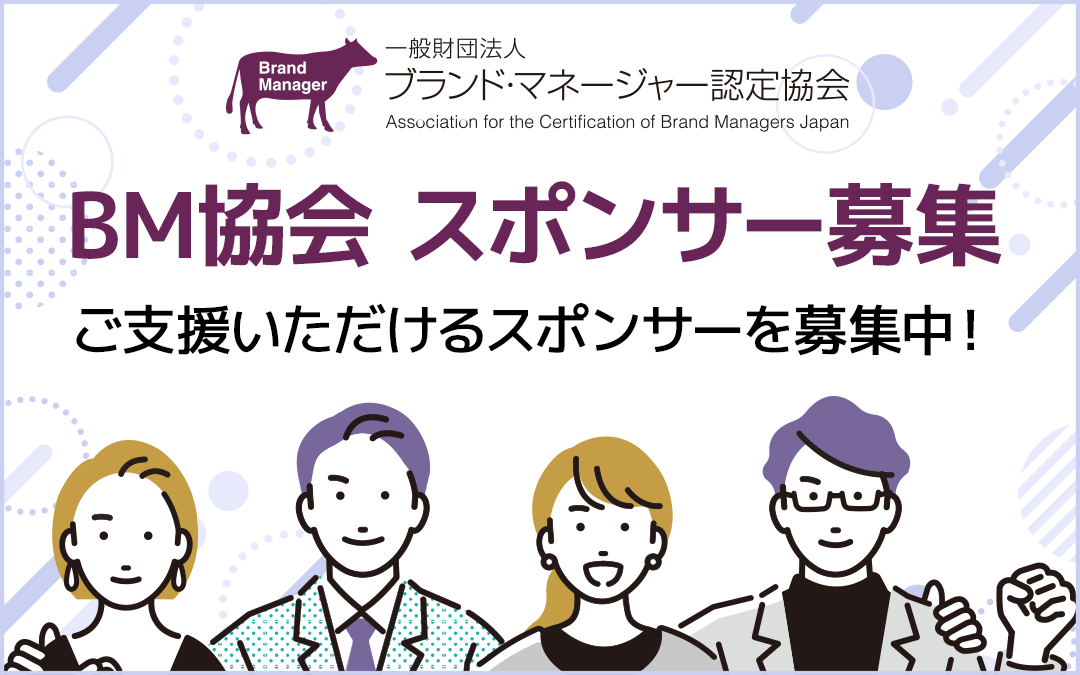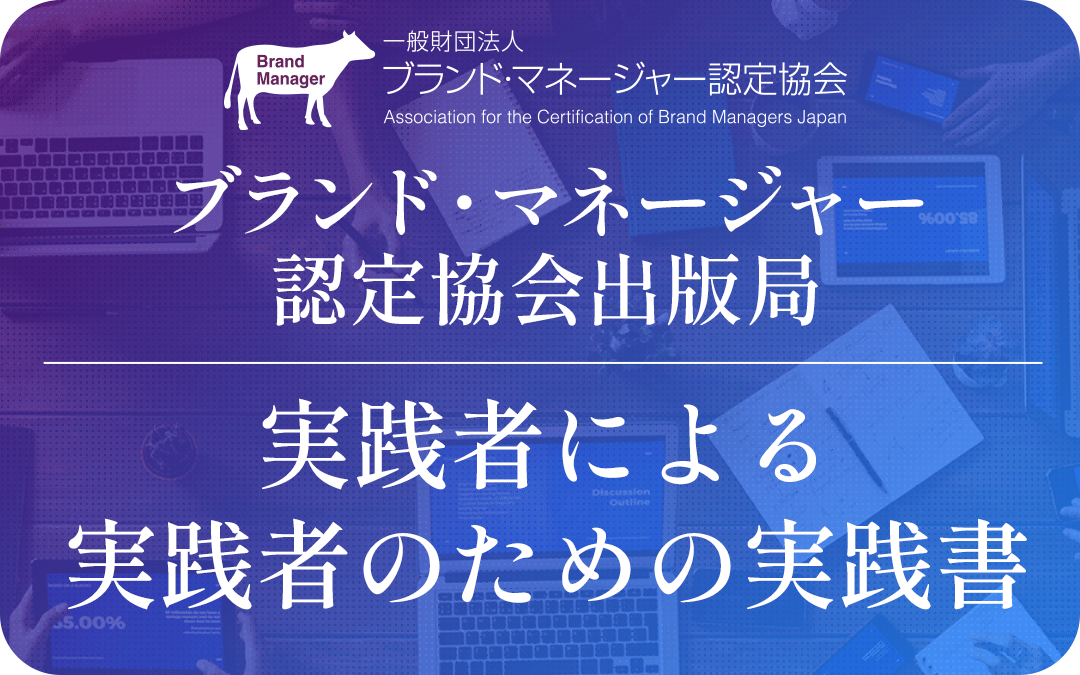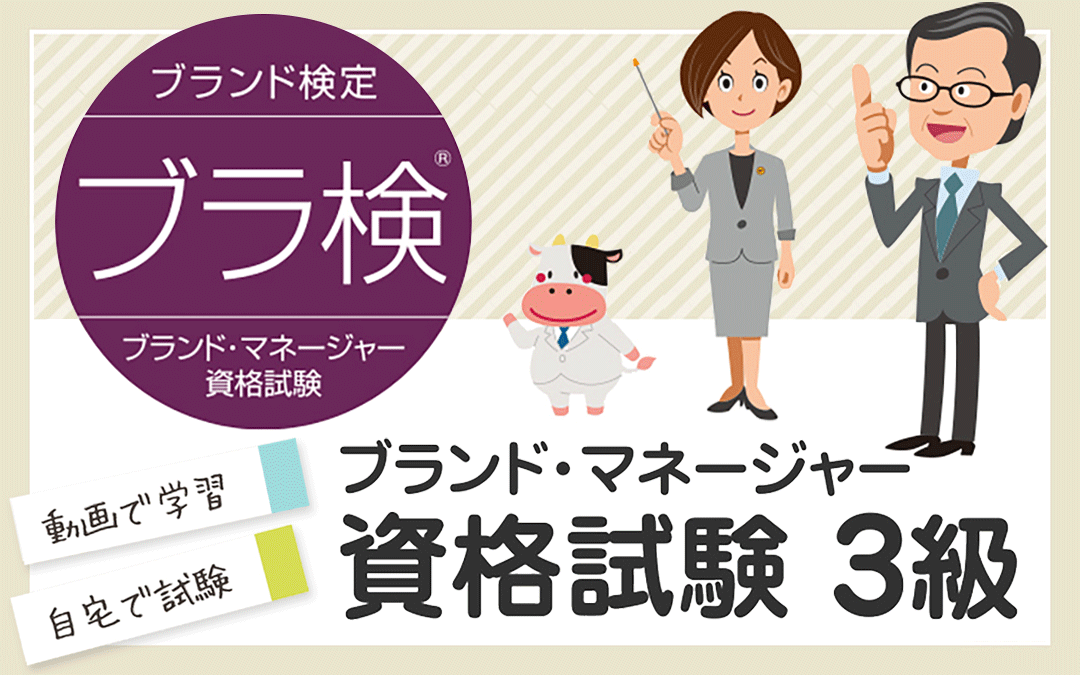ブランディングに実践の『型』を取り入れた日本で最初の専門機関~マーケティングにおいて重要なブランド・マネージャーの標準化と資格制度~
一般財団法人 ブランド・マネージャー認定協会 > インターナルブランディング勉強会 > 第3回インターナルブランディング勉強会
2024年7月26日第3回インターナルブランディング勉強会

内容
・第1部
エキスパートトレーナー/シニアコンサルタントの平野朋子氏による事例発表
・第2部
グループディスカッション
・第3部
グループディスカッションの発表
・第4部
城戸先生による解説
・第5部
佐々木理事によるBEAの活用方法のポイント解説
日時
2024年7月26日(金)15:00 – 17:30
開催方法
オンライン(Zoom)
ご参加者
13名
ご登壇者
産業能率大学 名誉教授
ブランド・マネージャー認定協会 IBカリキュラム編集委員 城戸 康彰 氏
株式会社イノベーションゲート 解析研究員
ブランド・マネージャー認定協会 理事・IBカリキュラム編集委員 佐々木 研一氏
ブランド・マネージャー認定協会 エキスパートトレーナー/シニアコンサルタント 平野 朋子氏
4事例をあげていただき、成功した要因とうまくいかなかった要因について、発表いただきました。
各事例について取り組みのプロセスについてお話しいただき、うまくいった要因とうまくいかなかった要因について、深堀して解説いただきました。
また、ブランド・エンゲージメント診断の結果を受けて導入した改善策についても発表いただきました。
事例を通しての気づき事項を共有いただき、ご参加者の皆様にとって、実践的な学びを提供いただきました。
事例発表を受けて、各グループごとに、事例発表で得られた気づきについて話し合いました。
成功する要因と失敗する要因について、各参加者が自身の経験をもとに意見を交換しました。
それぞれの視点から多様な要因が考えられ、具体的な事例を挙げながら議論が進められました。
平野朋子氏の事例についてさらに深く解説いただきました。
失敗の裏側には成功のヒントがあり、失敗を避けることで成功に近づくと示唆いただ、改めて事例を分析することの重要性について、説明していただきました。
社会関係資本(ソーシャルキャピタル)の概念が紹介され、組織内外での交流やフィードバックの重視、対話の活発化が成功の鍵であることや企業理念が社員の働きがいや生きがいに繋がることが紹介されました。
企業理念の共有が個人と組織の成長に寄与することなどについて、解説いただきました。
診断の主要な評価項目について解説と診断結果の見方や要素間の関係性について解説いただきました。
診断の活用方法についても説明がありました。
ブランド・エンゲージメント診断の結果を基に、組織の強化ポイントを明確にし、適切な改善策を導入することで、変革プロセスの効果を最大化し、ブランド価値と従業員エンゲージメントの向上を図るという内容でした。
BEA診断ツールを活用することで、組織内でのブランド浸透と従業員のエンゲージメントを高め、より効果的な組織変革を実現することが可能です。
プラクティショナー以上の資格をお持ちの方は、勉強会のアーカイブ動画をMe:ikuよりご視聴いただけます。
https://www.brand-mgr.org/meiku/contents/
※Me:ikuをご覧いただく場合は、会員登録が必要です。
その中からいくつかの声をご紹介します
・失敗事例と成功事例を通じて、失敗要因や成功要因を探る内容が非常に実践的で役立ちました。これからの組織変革に大いに活かせると感じました。
・ブランドエンゲージメント診断の説明が理解を深める良い機会となりました。今後、提案して活用してみたいと思います。
・インターナルブランディングの支援をまだ経験していないため、経験者の現場のリアルな感想を聞けて非常に参考になりました。失敗談も非常に役立ちました。
・社会関係資本に関する話がとてもためになりました。今後はこの視点も意識しながら支援していきたいと思います。
アンケート結果と今後の取り組みについて
第2回インターナルブランディング勉強会でのご意見を受け、第3回は、事例発表とグループワークを行いました。アンケートによると、ご参加者の皆様に勉強会の内容に満足していただくことができました。
事例から学ぶことが多いという意見を受け、今後の勉強会でも事例の共有を増やし、それに対する改善策を議論いただくグループワークを行います。
また、ブランド・エンゲージメント診断の結果を具体的な改善にご活用いただけるよう、活用方法について継続的に皆様にご共有できる場を設けてまいります。
これからも皆様のご期待に応えられるよう、勉強会の内容を充実させ、さらなる改善を図ってまいります。