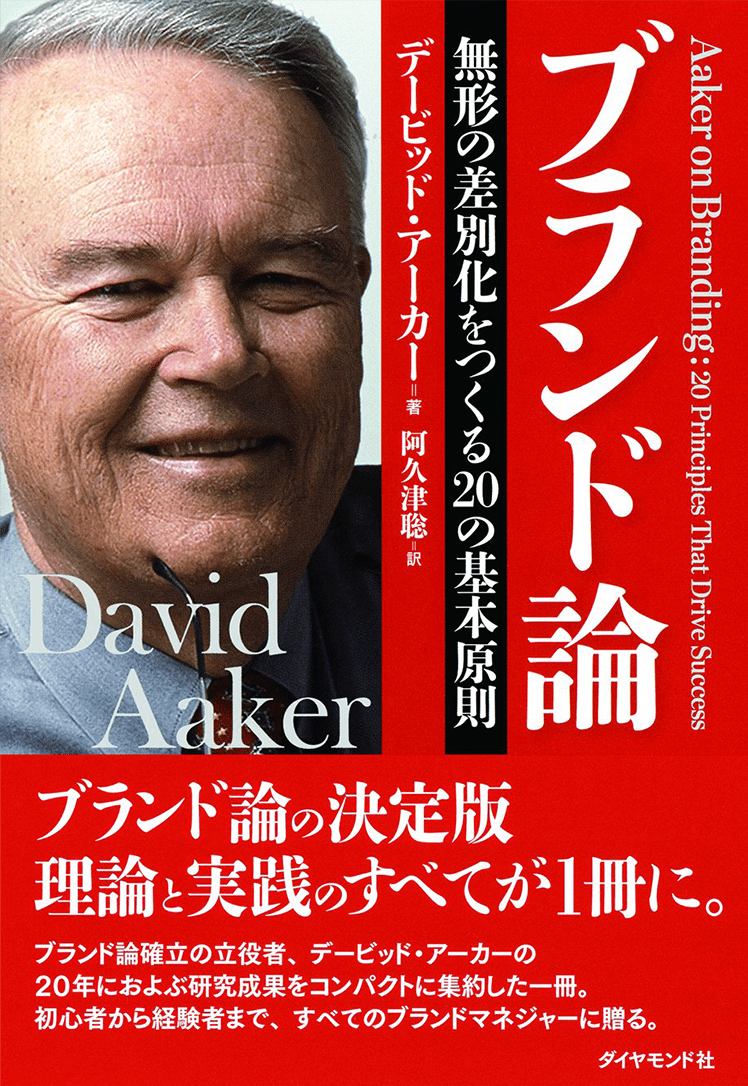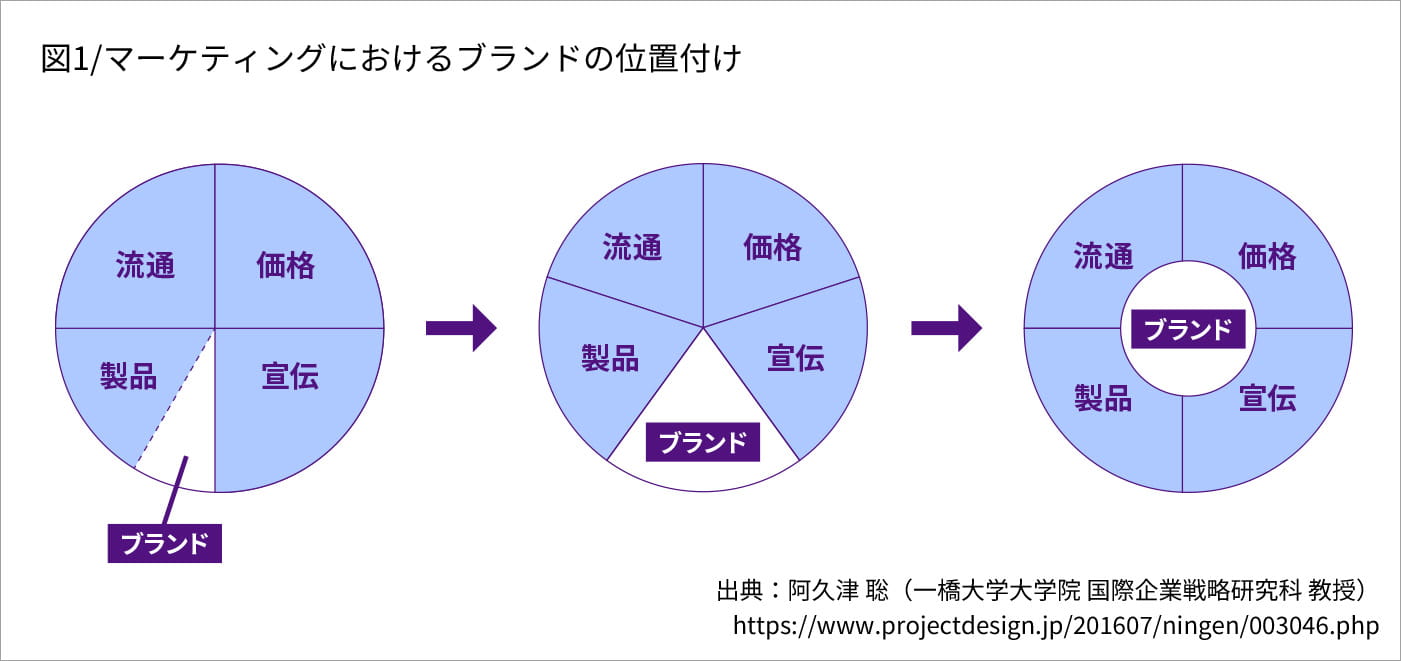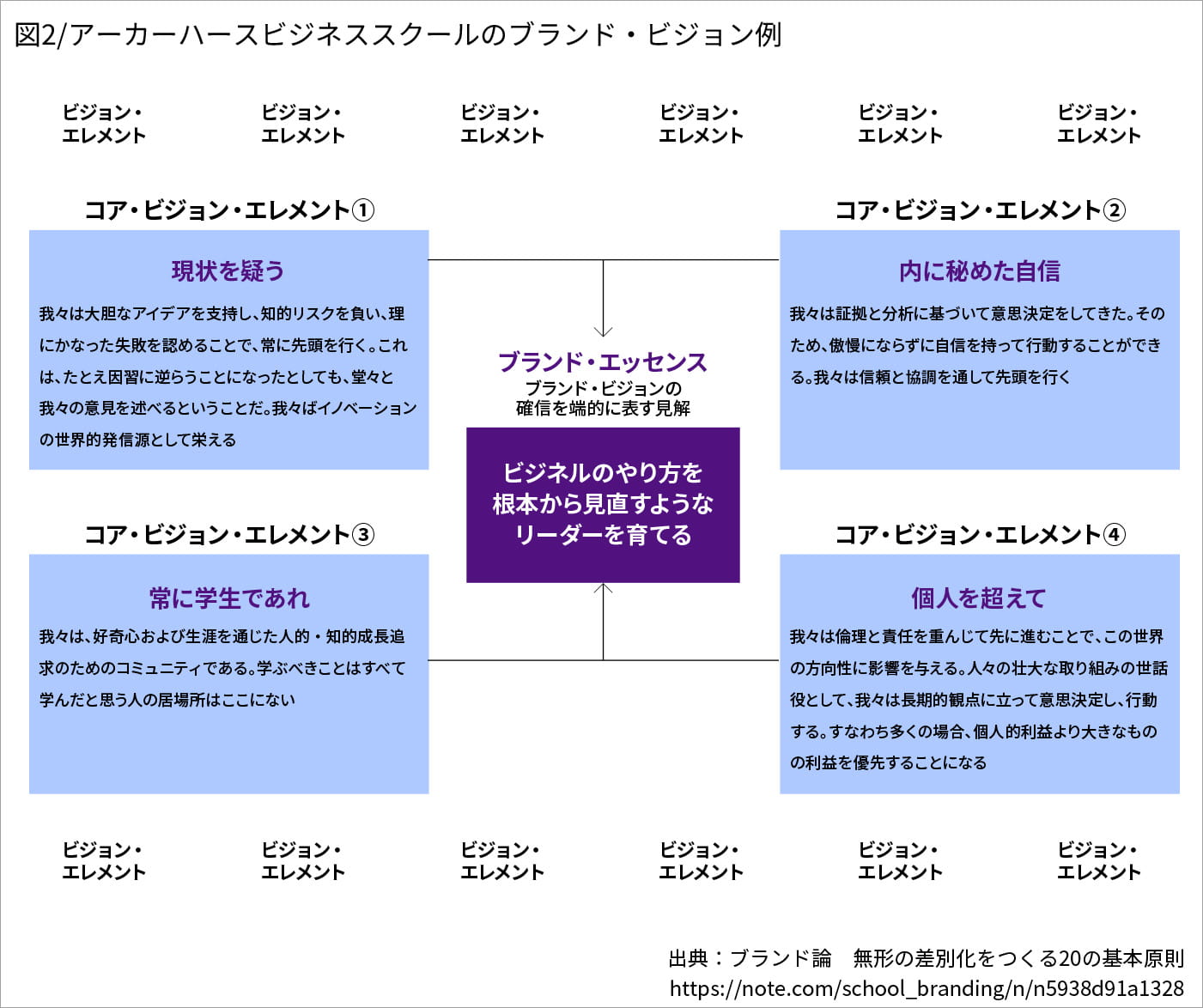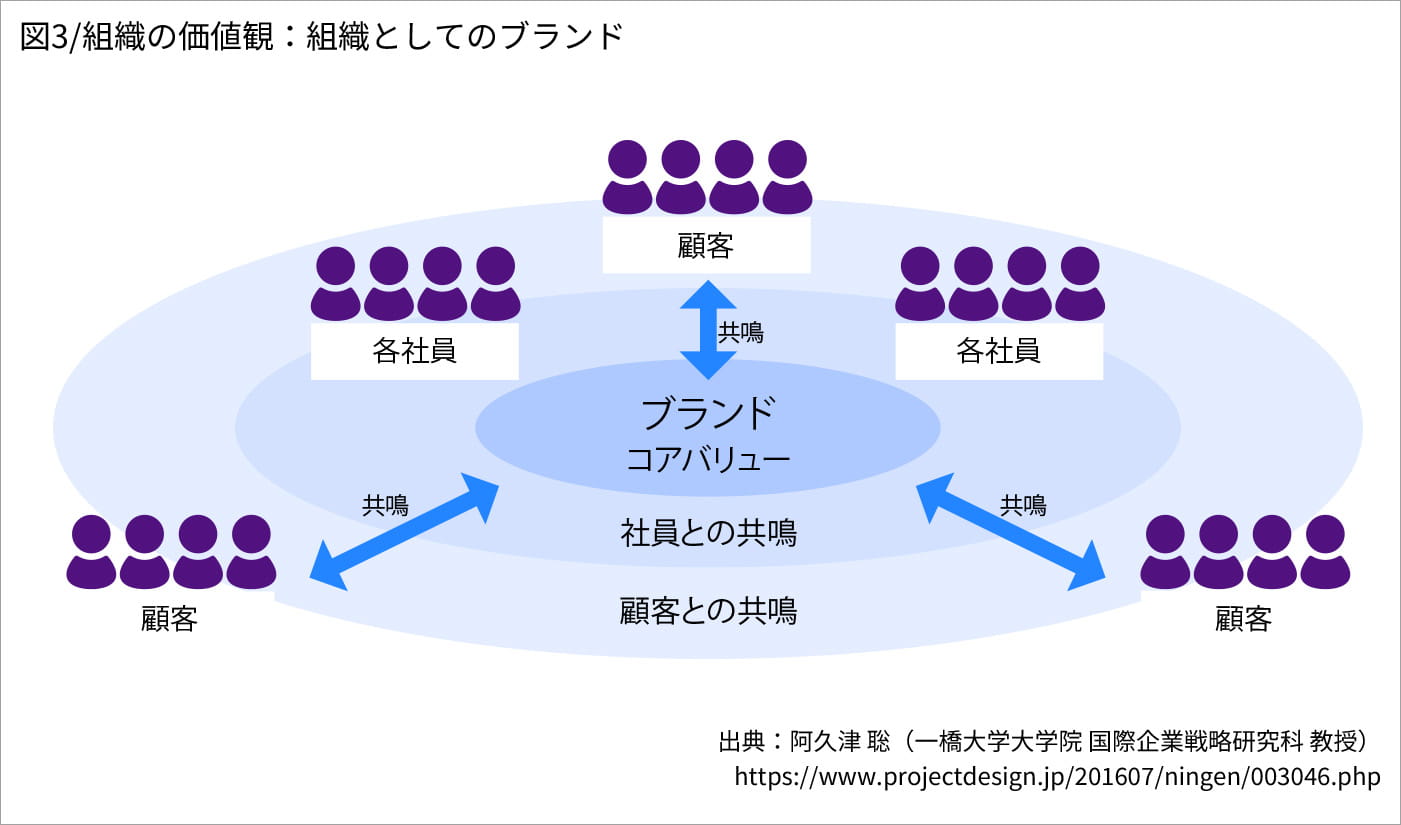本書を選択した理由は?
デービッド・アーカーとは?
今回紹介する本は、デービッド・アーカー先生の著書『ブランド論-無形の差別化をつくる20の基本原則-』です。この本が出たのは2014年。アーカー先生がブランドについて本格的な本を書き出されるのは1991年ごろで、それから約20年にわたって6~7冊を出版されており、それらを集大成した本がこの『ブランド論』です。これを読めばアーカー先生が考えていることの全体像が掴めるのではと考え、今回は同書を選択いたしました。
まずは、アーカー先生の人となりから紹介したいと思います。アーカー先生は現在80代で、カリフォルニア大学のビジネススクールの名誉教授です。1970〜1980年代にかけて、「モデラー」という数理的なモデルを作り、そこにデータを当てはめてモデルをテストするという、マーケティングサイエンス的なアプローチをされていました。同時に、市場調査や広告論についての様々な本も書いているほか、経営学的な『戦略市場経営』という本も書くなど、非常に幅広い分野でご活躍された方です。そして、アーカー先生が1994年に出した『ブランド・エクイティ戦略』という本は、非常に影響力を持ちました。アーカー先生のブランドについての著書は『ブランド・エクイティ戦略』以降、日本語版が出版されたものだけで5冊ほどあり、ブランド論について非常に幅広いと同時に影響力もある研究者、と言えるでしょう。